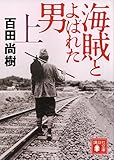 | 海賊とよばれた男(上) (講談社文庫) 810円 Amazon |
http://booklog.jp/item/1/4062778297
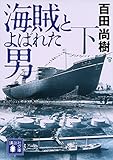 | 海賊とよばれた男(下) (講談社文庫) 810円 Amazon |
http://booklog.jp/item/1/4062778300
2012年の本屋大賞に輝いた、有名な百田尚樹氏の小説。モデルは民族系石油元売会社出光興産創業者の出光佐三です。この本が発売されて、取引先の社長の薦めもあり、購入すぐに読了していたのですが、読書メモでカタチに表すのが遅いのが不徳の致すところです。
出光興産は、創業時から日本的経営を貫き、2006年の上場前まで「大家族主義」でタイムカード・定年制・労働組合のない会社でした。その理念は、「人間尊重」。
佐三氏が戦前・戦中・戦後と信念を貫き、官僚・外資ら国内外の既存勢力といかに戦ってきたか、その集大成は出光が対外資産のほとんどを失った戦後直後の「ただちに建設にかかれ」で社員一人の首も切らず会社を立て直した実績であり、「日章丸事件」のような国内の官僚や英国とその石油大手メジャーを敵に回してでもイランと日本の国益を考え貫いた実行力であると言え、尊敬に値するものです。そういう人が政財官にもっと出てきて欲しいもの。
ただし、百田氏は深く狭く事実を綿密に拾い出した素晴らしい作品を出す一方で、たかじんの最期の結婚生活を描いた「殉愛」での騒動でも見られたように、対象となる本質としてのものの見方において、光は見えても影は見えない、あるいは無視をしているのではないか、とも思うのです。すなわち出光興産の光と影です。
私は百田氏の「永遠の0」もこの本も氏のいい面が出ているとは思うのだけれど、反安倍はすべて敵、沖縄のジャーナリズムを切り捨てたかのような百田氏の意見については、賛同しかねる部分があることも事実。
「人間尊重」の「大家族経営」出光と一体といっていい出光佐三は尊敬すべきリーダーシップで会社の発展させてきた創業オーナー経営であり、別の言い方をすれば出光佐三のワンマンで、定年がなく首切りなき温情主義が一方では自分の意見に異議を唱える役員社員を容赦なく切り捨ててきたことも事実でしょう。
これは、社員から見た出光・出光佐三の影の部分を描いたといっていい高杉良氏の「虚構の城」に詳しい。是非、経営者側から見た出光である百田氏の「海賊」本だけではなく高杉氏の本もセット読んでみることが物事を深く理解する上で欠かせないものではないかと思います。
もちろん、これは出光佐三への尊敬が揺らぐことではありませんが。理想に燃え、信念を貫き、国家のため国民のためにモーレツに事業を展開するのはオーナーとしては当然だからです。知るべきは物事に光と影があるというところ。
 | 新装版 虚構の城 (講談社文庫) 853円 Amazon |
http://booklog.jp/item/1/4041028906
出光は、2006年に上場し、来年は昭和シェル石油との経営統合に向けて動き出しています。
石油の世紀だった20世紀からその様相が変わってきているのも事実ですし、出光創業家がその経営統合に反対していて話題になっています。時代の流れで佐三の信念を貫くことは難しくなってきていることもあるでしょうし、生き残りを賭けた国際的な会社に出光が変わっていく様子がこれから見えてきそうです。
出光佐三は「私は、人間を信頼するという考え方を広めていくことこそ、日本人の世界的使命と言っています」と言いました。その言葉通り、その使命を日本のエスタブリッシュメントが是非とも果たして欲しいところです。
読書メモ↓
・「日本には三千年の歴史がある。戦争に負けたからといって、大国民の誇りを失ってはならない。すべてを失おうとも、日本人がいるかぎり、この国は必ずや再び立ち上がる日が来る」
・「ただちに建設にかかれ。昨日まで日本人は戦う国民であったが、今日からは平和を愛する国民になる。しかし、これが日本の真の姿である」
・創業以来ひとりも馘首がない
・店員は家族と同然
・選り好みせずありとあらゆる仕事を探せ
・銀行は単なる金貸しではない。採算ある事業、たしかな未来のある事業と思えばこそ融資もする。融資は金を貰ったわけではない。きっちりと返済し、絶対に事業を成功させなければならない
・大東亜戦争とは石油のための戦争であり、石油のために敗れた戦争。石油は本来平和な産業に用いられるべき
・「困難な仕事だからやり甲斐もある。よそがやれないと尻込みする仕事だからこそ、うちがやる」
・家族の中に規則があるのはおかしい、と労働組合は不要に。社是は「社員は家族」「非上場」「出勤簿は不要」「定年制度は不要」「労働組合は不要」
・「店員たちはぼくの息子だ。息子に裏切られるような親なら、親たる資格はない」
・アメリカの石油資本が日本の石油業界を支配する前に手を打つ
・アメリカのすごいところは、利用価値があるとわかれば即座に決める
・戦前の日本政府の石油政策は拙かった。アメリカに石油輸入の8割を頼り、それを断たれて戦争を起こした。油田のある南方を制圧しても、制海権を奪われてしまった
・経済は生き物。市場が混乱すると、いちばん損をするのは消費者であり、得をするのは利権を持った者
・「日本は戦争に敗れて、何もかも失ったが、これからは平和な国として、武力ではなく経済で世界と闘っていく。そのための石油自由化」
・情報は速さが何より
・日本という国や官僚の悪いところは、国全体の利益を見ようとせず、目先の利、狭い集団の利益ばかりを追求する。かつての陸軍もそう
・生産者と消費者を結びつける役割を持つ商人の存在が大きくなると予測
・「自分の商売をするだけだ」
・店主は投機と中間搾取を嫌い、常に消費者の利益を考えていた
・同じ土俵で正々堂々と自由競争で勝負する
・戦前から日本輸入原油の8割以上をアメリカが占める現状を中東にシフトすることを考えていた
・会社は人間尊重を追求するひとつの大家族
・末端の仕事をする人間がどれだけ必要かを決め、その上に最小限の統括する人を置く
・即断即決
・日本の石油会社は外油にほぼ乗っ取られた。でも外油とは提携しないことを決断
・世界に打って出るタンカーを持つ
・不急のものでなくても、商人は5年10年後を見据えていなければならない
・息子をアメリカに行かせる。日本人としての誇りを失わず、日本人の良さを持ちながら、アメリカ人の長所を身につけよ
・イランとともにメジャーと戦うため、イランの石油を買う
・信頼を裏切らない会社
・日本国のことを考え、メジャーと手を結ばず国際石油カルテルと戦う
・日本人が信義を果たす国民であることをイランの国民は知る
・日章丸をイランへ派遣
・世界の石油業界は七人の魔女と呼ばれる欧米の石油会社に長い間支配され続けてきた。イランはそれに立ち向かった勇気ある国。イランはそのために厳しい経済封鎖を受けているがイランの石油を輸入することによってイランを助け、日本の石油業界の未来に貢献する
・同業者から「海賊」と恐れられた自分が40年後に大英帝国を相手に戦うことになる(1953)
・アメリカの会社にタイムレコーダーがあることは人間を信頼していないこと
・悪い社員を止めさせ、すぐれた社員ばかりでやっていく、これは少数精鋭主義ではなく単なる利己主義
・人の心がひとつになったとき、合理や計算では考えられないことが起きる
・自由主義社会の敵であるソ連から原油を買う、という批判には、ソ連とのビジネスは東西両陣営の平和的共存に役立つ。民間貿易から交流が始まれば、複雑な政治の世界をはじめいつか両者は結びつく
・過ぎ去った過去を悔やんでも仕方がない。歴史をやりなおすことはできない。大事なことは現状でベストを尽くすこと
・妥協を排し、人間尊重の信念を貫きとおした
・官僚や銀行の天下りを受け入れない。会社の利益は店員のもので、株主のために働くのではない
・ケンカをしても力づくではなく、世論や産業界に多くの見方をつける
・講演は、成功譚や経営学の話ではなく、日本お伝統と道徳であり、人間尊重の精神
・20世紀の文明は石油なくしては有り得ない
・「戦後日本の驚異的な経済成長を支えたのは、中東の安い石油のお蔭だったが、その成長はない。日本は新しい道をこれからの日本人が見つけなくてはならん。難しい道だが、日本人なら必ず見つけることができるだろう」
・オイルショックに「国民は享楽に慣れきって、節約を忘れてしまった。そこで天がモノを大切にせよと反省の機会を与えたのではないか」
・一番大事なのは日本人の誇りと自信を失わないこと
・「私は、人間を信頼するという考え方を広めていくことこそ、日本人の世界的使命と言っています」
・人間尊重の精神は、日本人がいる限り、世代から世代へと受け継がれていく