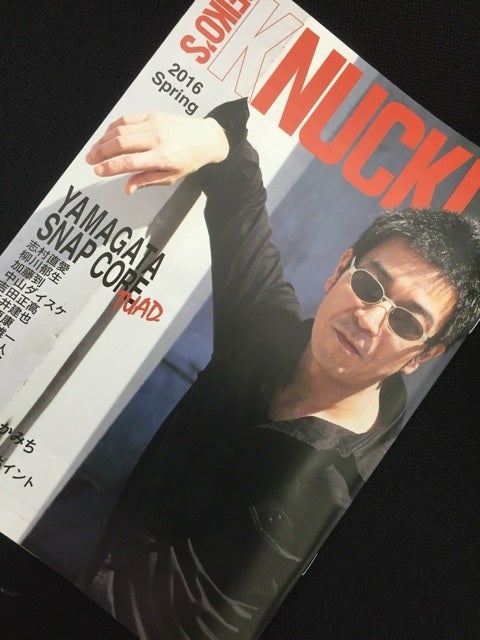ファインダ画面のなかの1ピクセルの孤独
西新宿の広々とした公園沿いを歩き、横断歩道橋に上ってみる。
街路灯が消え、空は柔らかな光をためて水色に輝きはじめ、ケヤキの樹が風に葉を揺らしている。
こんな時、ぼくはハイパーカードを作ったアップルコンピュータの伝説の人物、ビル・アトキンスのこんな言葉を思い出してみるんだ。
「ぼくらは広大なファインダ画面のなかの1ピクセルにすぎない」
ファインダというのはマック上の机みたいなもので、簡単に言ってしまえばモニタ画面の全体のことだ。ピクセルとは、画像を表示する最小単位のことだ。西新宿の空が、広大なファインダ画面に見える。
Virtual Realityという言葉がある。仮想現実、と翻訳されている。ありもしない現実、といったニュアンスだろうか。だけどVirtualという言葉は、PowerBookG4にインストールしてあるLogoVista EtoJという英和辞書によると、“事実上の現実“という意味なのであって、ありもしない現実、という意味ではない。
抜粋:: 山川健一. “希望のマッキントッシュ”。 iBooks.
希望のマッキントッシュ
最初のマッキントッシュを買ってから、気がつけば8年が過ぎた。オーバーなようだが、マックと出会ったからこそこの8年がきらきらと輝いたのだと思う。長い年月の間には、さまざまなことがあった。出会いと別れ、かきまくった恥の数々、失ったものや手に入れたものや……思い出したくもない出来事だってある。
しかし、である。
いずれにしても、素晴らしい時間の連続であった。そして、この8年間はマッキントッシュなしには考えられない。この話をするとたいがい唖然とされるのだが、ぼくはこれまでに30台以上のマックを手に入れたのである。
考えてみればずいぶん無駄な金を使った気もするが、マックがあったからこそぼくは雨が降る日にも……これはもちろん比喩的に言っているのだが……微笑むことができた。
恋愛に関する本を読んで得られるのが知識で、実際に異性を好きになり喜びを感じたり酷い目にあうことによって得られるのが知性である。それを絵画や音楽や文学で表現した時に、多くの人々が共有できる英知というものが誕生する。
Windowsマシンでも、知識を得ることはできるだろう。知性までいくと、どうだろうか。ま、これはユーザー次第だから断言するのはやめておこう。
だが英知となると、マッキントッシュの独壇場である。マッキントッシュは、スティーヴ・ジョブズが東洋知と西洋知を合体させることのなかから生み出したコンピュータなのだから。
古くからのマックユーザーの間に、こんなジョークがある。
「でもあなたは、アップルのマークが入ったジャンボジェットに乗る気がしますか?」
マックがよくフリーズする、という事実を前提にしたブラックジョークである。
だがOSXはUNIXベースだからフリーズしない。やる気になればターミナルを使い、UNIXにアプローチすることも可能だ。
マッキントッシュを窓口にすると、デジタルは人間に優しく深い。
デジタルの向こうに、温かな未来が見える。
抜粋:: 山川健一. “希望のマッキントッシュ” iBooks.
真夏のニール
沈黙。
やがて、男は言った。
「いいでしょう。それでは、あのテーブルの上をかたづけて下さい」
男は、窓際に置かれた丸テーブルを指さした。ぼくは立ち上がり、テーブルの上に置かれたカメラや郵便物、ブルースを吹くためのハーモニカ、ぼくが撮った写真が掲載されている雑誌、パンフレット、銀行からの振り込み通知、カード会社からの請求書などをきれいにかたづけた。男の言葉には、そうさせずにおかない不思議な力がこもっていた。
「明かりを消して下さい」
ぼくは明かりを消した。ブラインドを下ろしてある部屋は、仄暗くなる。島路大助とぼくは、カシの木で作った丸いテーブルをはさんで向かい合った。
「わたしの手のひらの間を見てください。心を落ち着けて、この世界で最も良きものをイメージするのです」
男は、今までとは違った静かな調子で言い、左右の手のひらをテーブルの上に、焚火にでもあたるようにかざした。ぼくは彼の手のひらの間を覗きこむ。
「さあ、心を落ち着けて、この世界で最も良きもののことを考えるのです」
深い湖を覗きこんだ時のように、男の手のひらの間にすいこまれてしまいそうな気がした。やがて、男の手のひらの間がぼんやりと光りはじめる。きらきらした透明な光は、やがてサッカーボールほどの大きさの球になった。
光の球がテーブルの上に浮かんでいる。透明な光は、中心から、少しずつグリーンに染まっていく。ぼくは息をのんだ。
よく見ると、輝くグリーンは森なのだった。陽光をいっぱいに浴び、新鮮な葉を風にそよがせる樹木がくっきりと見える。テーブルの上に浮かんだ森が、美しい光を放っているのだ。
「マインドランドです……」
男の声が、どこか遠くから響いてきた。

抜粋: 山川健一“真夏のニール.” 株式会社幻冬舎. iBooks.
山川健一デジタル全集、特別価格は8月31日まで。
8月も既に半ばとなりました。
「山川健一デジタル全集」は、2016年8月31日まで、83作品をすべて100円(税込)、また『山川健一デジタル全集Jacks』は通常価格19,800円(税込)のところ7,800円(税込)の特別価格で販売しています。
まだの方は是非この機会に、iPhoneやiPad、Macで山川ワールドをお楽しみください。
幻冬舎のサイトへ
http://www.gentosha.co.jp/s/yamakawa/
文芸学科からは、作家や漫画家が続々と在学デビューしています。
電撃大王 2016年 09月号 [雑誌]/KADOKAWA/アスキー・メディアワークス

¥680
Amazon.co.jp

これで、6年間で8人が作家デビューしたことになります。1期生の荒川匠君は「ガンスミス」(幻冬舎文庫)で、笠原伊織君が「アノヒカラ ジェネレーション」(藝術学舎/幻冬舎)でデビュー。樋口サキさんは 「女子大生に超人気の美術の授業」(有賀三夏著藝術学舎/幻冬舎)の編集とライティングを担当し、卒業後は幻冬舎に入社。
2期生の吉川皓也君は月刊サンデー『ゲッサン』で、53回GET THE SUN新人賞に佳作入選して漫画家デビュー。「ふたりの日曜日」「いい日」「甘い生活」などを発表しています。
同じ2期生の佐藤アスマ君は「天才とはしる」で「アフタヌーン四季賞2016夏のコンテスト」で準入選を受賞しました。コンテストの内容や講評は『月刊アフタヌーン2016年9月号』に掲載されています。
3期生の丸山千耀さんは「星屑のブロンシュ」で第1回文芸ラジオ新人賞を受賞し、作品が『文芸ラジオ』第2号に掲載されました。
そして1期生の大久保開(おおくぼ・ひらく)君が卒業後、第5回集英社みらい文庫大賞の優秀賞を「青に叫べよ」で受賞しました。集英社みらい文庫は小学生&中学生を対象とした児童文学のシリーズで、みらい文庫大賞はその新人賞です。
学生に負けてられないよなぁと思う今日この頃です。
わんぱく小僧の恋愛学講座
ジョークの一つもまじえながら、それでもそれなりに真剣に女の子に対しながら、ぼくはもう既に逃げ腰になっていたわけだ。
それが果たして恋愛と呼べるものだったのかどうか、今ではもうよくわからない。恋愛と呼ぶにはあまりにも直接的で、貧しく、独得なイマジネーションに欠けていたような気もする。
当時の十代の女の子たちはそれぞれによく本を読んでいて、それも特に十九世紀の外国の恋愛小説が専門分野で、ぼくなどもそのうちの何冊かを借りて読んでみたりもしたが、そのたびに考えたことは、この青年はなぜこんなにいろんなことを考えるのかな、ということだった。ああだこうだと考える暇があったら、マディ・ウォーターズのように「やらせてほしい」と一言いえばいいのに、と。
今は十代のぼく自身に向かって、おいおい君、ただやればいいってもんじゃないんだぜ、と言ってやりたい気がする。ほんとうは、そのことはほんのスタート・ラインにすぎないのだから。しかし、十代の少年には、女の子と寝るということが、あたかもゴールのように見えたのだ。
だが、いずれにせよ、そうしたいささか滑稽でちぐはぐな、それでも本人たちには輝かしく見えた数々の献身的な努力はやはり恋愛だったのだろう。そう認めてやらなければ、あの頃の十代の少年たちは行き場を失ってしまうではないか。
学生ズボンの前をふくらませていた少年。クラス・メイトの女の子の裸を思い浮かべながらオナニーしていた少年。公園のベンチで、どうやったらキスできるだろうかということばかり考えていた少年。女の子をベッドに連れこみ、急いでブラウスのボタンをはずしていた少年。彼女が帰ってくれた後、ほっとして煙草を喫いながら、シーツの間に貝殻細工のボタンを見つけて舌打ちしていた少年。やはり、彼らこそは恋愛物語の主人公だったのだ、と言うべきなのかもしれない。
もちろん、ただやればいいというものではない。しかし、ほんとうは、そんなことはあの頃のぼくらにもよくわかっていたのだ。だが、複雑に見えはじめた世界の中で、せめて自分だけはシンプルでいたいと思っていたのだろう。形而上学的な問題は明日勉強することにして、今はとりあえず自分の精神と肉体を解放してやりたい。そんなふうに、無意識のうちに思っていたのかもしれない。
性欲と恋愛の輝かしい一致。それこそが、わんぱく小僧達の恋愛学講座の第一章なのであった。
抜粋:: 山川健一 “マギー・メイによろしく”。 iBooks
「わんぱく小僧の恋愛学講座」
夏休みに読むiBooks:山川健一


2016 年 8 月 21 日(日)午後 1:00
Apple Store 銀座 で
「夏休みに読むiBooks:山川健一」という公開講座を行います。
小説の書き方についての出張講義です。
まずぼくが1人で、MacintoshとiPhoneとiPadでいかに文学するか、という話をします。その後、東北芸術工科大学、文芸学科の石川忠司教授と2人で「小説の書き方」の講義をします。
ちなみに、2011年に創設された東北芸術工科大学文芸学科からは、既に8人の作家(小説家3名、ノンフィクション作家2名、漫画家3名)がデビューしています。
2人いっしょに文芸学科で講義をやり、東北地方の高校の文芸部のイベントなどに招かれて講義をし、ぼくらの「文芸漫才」は今や円熟の領域に入りつつあります。東北地方の高校から、2人指名で引っ張りだこの人気コンビです。いや、ほんとの話。
はっきり言って、超絶おもしろいです。世界が一気にひらけるはずです。文芸学科門外不出の内容なので、本にはしてません。ラーメン屋さんの秘伝のタレ、みたいな話です。
ぼくらは小説家と批評家なので、もともと犬猿の仲ですが、その真面目なバトルが学生や高校生達にはウケるみたいです。文芸学科のジャガー&リチャーズと言うべきか、西郷隆盛と大久保利通と言うべきか、はたまた近藤勇と土方歳三と言うべきか。
「おまえが大久保でも土方でもいいけどさ、いずれにしても俺が先に死ぬんじゃん」とぼく。
「たかが1年じゃん。いやぁ、今が幕末ならな。俺達いい仕事したよな」と石川。
以下の方、是非ともいらして下さい。
・会社に勤めてるけどいつか作家デビューしたいと思っている人
・小説というものを立体的に知りたい方
・小説を書くことに興味のある高校生の皆さん
・高校の文芸部顧問の先生の皆さん
・シンプルに石川忠司もしくは山川健一の読者の皆さん
・「Macintoshは希望だ」と信じているマッカーの皆さん
お待ちしております!
ぼくのロックンロールさえもが、死のうとしている。
爺さんは私の肩を叩き、白いマントみたいな服を羽織ると、青い革のシューズでステップを踏みながら表へ出て行った。
入れ違いに、花子が部屋に入ってきた。毛足の長いグレーのカーペットに、赤のドレスがくっきりと映えて見える。
「ねえ、今のお爺さん、誰?」
「ロックンロールの神様さ」
「神様? わたし、キスされちゃったけど、大丈夫かな」
抜粋:: 山川健一. “クロアシカ・バーの悲劇”。 iBooks.
「“ぼくのロックンロールさえもが、死のうとしている。」
カブト虫の日々
検索機能のことは書いたが、夜眠る前に、iPhoneでなにか単語をひとつ検索してみる習慣がついた。今夜調べてみたのは、「カブトムシ」「カブト虫」である。今週はずっと山形で、学生達が時々カブトやクワガタを持って来てくれて、研究室に置いてあるプラスチックケースでしばらく飼ってみたりする。
「カブト」でヒットしたのはJacks全体で10箇所ぐらいである。そのうちのひとつを紹介しよう。今後も不定期に、エッセイや小説の一部分をここで紹介していこうと思う。
カブト虫の日々
夏の思い出を、もうひとつ。いつだったかの夏の日、長野周辺を車で走っていたら、ガソリンスタンドにこんな看板が出ていたことがある。
〈満タン、カブト虫一匹差し上げます〉
ぼくは思わずブレーキ・ペダルを踏み込んでしまった。ガソリンゲージをチェックしてみたが、残念ながら給油するほどガソリンは減ってはいなかった。
それからしばらく走り赤信号で停止すると、国道ぞいの薬局にもこ“んな看板が出ている。
〈カブト、クワガタあります〉
殺虫剤を売りながら虫も売るとは勝手な店だと思いながら、ちょっと覗いてみたい気になった。先を急いでいたのであきらめたのだが、カブト虫を手にしたら自分の少年時代がかえってくるような気がしたのだ。
とにかく、ぼくはカブト虫が大好きで、大人になってからの夏がなにか物足りないと思っていたのだが、その原因はどう考えてもカブト虫にありそうだ。
子供の頃、夏休みの課題は毎朝カブト虫をとりにいくことだった。朝、起きる。そして、自転車に乗り、誰よりも早くカブト虫をとりにいくのである。ひと足遅れると、誰かがやってきた後で、一匹もとれないということになってしまうのだ。カブト虫がいる林は子供達どうし、それぞれ秘密にしておいたものだ。
いつだったか母親が、ぼくと弟に、ごく控え目にカブト虫のいる林を教えてくれないかと切り出したことがあった。いろいろお世話になっている近所の人が、こんなふうに言ったのだそうだ。
「息子がカブト虫のいる林の場所を教えて欲しいと言っているんですけれど、一ヵ所だけでかまわないから教えていただくわけにはいかないでしょうか……」
ぼくと弟は、即座に、絶対にいやだ、と答えたものだった。カブト虫のいる林の場所はトップ・シークレットで、親戚の子供にだって教えたりしないのだ。
母親は困ったようだったが、仕方がないとあきらめてくれた。
ぼくと弟は、あちこちの林や森をくまなく歩き回り、カブト虫がいそうな林はかなり遠くの場所まであらかた知り尽くしていた。そして、カブト虫かクワガタ虫がとれたそれぞれの林には、秘密の名前をつけていた。
ある日、雄のカブト虫が二匹とれた畑の横のクヌギの林は〈カブ2〉、クワガタが三匹とれた林は〈クワ3〉、といった具合である。赤い羽をしたカブト虫はよく飛ぶとされていて、特にアカバネと呼ばれていたが、アカバネが二度つづいてとれた場所が〈アカバネ〉である。
そんなふうな名前のつけ方をしていたのだが、ある朝新しい森に分けいってみると、なんと数十匹のカブト虫とクワガタ虫をつかまえることができたのだった。ぼくらは狂喜し、だがなんという名前をつけたものか困ってしまった。
そこで、こんな名前を思いついた。
〈KS地帯〉。
ぼくがケンイチで、弟の名前はサトシといい、それぞれのイニシャルをとったわけだ。そのうち、脱脂綿に砂糖水をつけてクヌギの木につけておく、なんてこともやるようになった。クワガタが穴に“入ってしまった時は、一人がその場所で待っていて、もう一人のほうが急いで父親を呼びに帰る。穴に煙草の煙を吹き込むと、たまらなくなったクワガタ虫が出てくるのである。
市販の虫籠では間に合わないので木材と金網で大きな籠を作り、それを青いペンキで塗った。子供にしては、たいそう立派な出来だった。
たまにはカブト虫の短いほうの角に糸をつけ、ぐるぐる回して無理やり飛ばしたり、カブト虫とクワガタ虫を闘わせたりしたが、ぼくらはもっぱら、この余りにも雄々しく優雅で美しい昆虫をただ眺めていたものだ。カブト虫にしてもクワガタ虫にしても、それこそ何時間眺めていても少しも飽きないのだった。
いちばん悲しかったのは、やはり虫籠の中のカブト虫が死んでしまうことだった。秋がくれば死ぬものとわかってはいても、彼らが少しずつ弱ってきて、やがて死んでしまうと言いようのない気持ちになった。ある時、ぼくと弟は相談して、新しくとってきたカブト虫は三日だけ虫籠に入れておいて、その後は林に返してやることに決めた。
朝、三日前につかまえたカブト虫とクワガタ虫を虫籠に入れ、自転車で出かける。まず、いちばん誰にも見つかりそうにもない〈KS地帯〉に古いカブト虫達を逃がしてやり、それから新しいカブト虫をつかまえるのである。
ぼくが中学に通うようになると、クラブの朝の練習があったりして、夏休みと言えどもそう毎日カブト虫ばかりとりにはいけなくなってしまった。
弟は、一人で自転車で出かけていった。見る見るうちに、成績が落ちていった。手ぶらで帰ってくる日が多くなった。多い時でも、二、三匹といった具合だった。
ぼくは、彼に言った。
「なんだよ、おまえ。一人じゃこれしかとれないわけ?」
「バカヤロー、にいちゃんは何も知らないくせして!」
翌日、久し振りに弟といっしょにカブト虫とりに出かけ、ぼくは啞然としてしまった。〈カブ2〉も〈クワ3〉も〈アカバネ〉も、ブルドーザーでクヌギの木はなぎ倒され、赤茶けた土が剝き出しになってしまっていた。広々とした〈KS地帯〉も下草が刈り取られ、とてもカブト虫がいる感じではなかった。
ぼくらは、カナブンとシロスジカミキリしかとることができなかった。カナブンやカミキリなんて、昔はカブト虫が多くてとる気にもならなかったのに、と思ったものだった。
そんなふうに、カブト虫はあっという間に消えていってしまった。まったく、悪い夢を見ている気がしたものだ。
今でも、ちょっと郊外に行くとクワガタ虫のほうは見つけることができるようだ。だが、カブト虫のほうはむずかしい。カブト虫の幼虫は、堆肥の中で成長するからだ。堆肥が使用されない現在、カブト虫の幼虫が成育する場所はほとんどないのである。仕方ないこととは言え、やはり淋しい気がする。
そう言えば、つい二、三日前、ぼくは夢を見た。ぼくはどこかの大学の研究員で、ある薬草の採集に出かけるのだ。森の中を歩き回り、薬草を採集する。すると、その薬草の根元に、黒光りするカブト虫がいた。ああ、君達はこんなところに隠れていたのか、とぼくは思う。大丈夫、誰にも言いやしないから……ここで、そっと生き延びておくれ。そう、思うのだ。
「どうかしましたか?」
同僚の女性研究員に声をかけられ、ぼくは努めて冷静に答えるのだ。
「いや、なんでもありません」
あの夏の日のカブト虫達は、ほんとうに素敵だったと思う。そして、いくら懐かしいからと言え、デパートなんかで養殖されたカブト虫を買うような愚かなことは決してするまいと思う。
なぜなら、今ではもう、三日後に彼を返しにいく林が存在しないのだから。
抜粋: “山川健一デジタル全集 Jacks”。 iBooks.
『いつもそばに仲間がいた』所収「カブト虫の日々」より