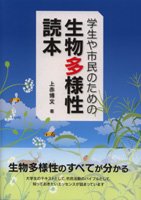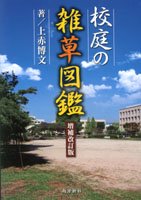坂田さんに初めてお会いしたのは、今年8月の福津での植物と色彩の歴史にまつわるお話会でつい最近なのですが、
一瞬にして
様々な視点から多観点的に、純粋なる興味と愛情を持って事象を捉えて
そこから立ち顕れる曼荼羅のように語られるこの世界の美しさに
(ひとつひとつのエピソードが珠玉❤️)
そのパッションとファンキーさ溢れるお人柄と旅ゴコロに
時々ブッ込まれる民俗学者の宮本常一氏とかがいちいちツボ過ぎて
もう瞬殺で惹きこまれてしまったのでした。
今回は森と里山についてのお話だったのですが、
琵琶湖のほとりに緩衝地帯のように復活させた田んぼにフナが遡上し、
田んぼに卵を産みつけ、孵った幼生たちは、豊かで安全な稲の影で過ごした後、再び琵琶湖に戻っていく円環。
そして、その地域の安全なお米食べたーいって、琵琶湖ほとりから武蔵野への人々のいったりきたりの円環
(Uターン、Iターンに加えてOターンという新しい人々の流れ)
子供たちがもはや高級品になりかけた鮒寿司を復活させていく流れ、
森の地面の下にはもうひとつの森、
水の森、菌の森
菌根菌の世界があること
人を変えることはできないけれど、、、
(特に団塊の世代は百姓継ぐな!田舎には価値がない!勉強して都会に行って給料貰え!って教え込まれた世代、、)
しかしながら、豊岡のコウノトリ復活の事例だと
コウノトリは稲を倒す害鳥だ!反対!反対!
↓
役場の方がコウノトリは40数歩でやっと1本稲を倒し、
そのコウノトリによって倒された稲はまた立ち上がることを
執拗な調査によって突き止める
↓
孫に安全なお米食べさせたいし、いいよーうちの田んぼでやってみるよー
という農家さんが現れる
↓
農薬を使わなくなった田んぼにコウノトリが食べる虫や両生類などが戻ってくる
↓
コウノトリがもどってきたー!
そして
コウノトリや小さな生き物が戻ってきた田んぼに子供たちが集まってキターーーーーー!
↓
コウノトリや子供たち集まってワイワイ楽しそう!
うらやまし~
うちもやってみようかな・・・
↓
今や、もともと反対していた方々が「今日はうちに〇〇羽来てん」「うちは〇〇羽やで!」
と日常会話で自慢しあう事態に・・・♡
他にもいろいろ、地域の方々がその価値を再発見して生き生き胸を張っていらっしゃる姿が何というか、新しい時代の示唆と可能性に満ちてなんとも幸せな気持ちになるのでした・・・・
坂田昌子先生からのおすすめ動画はこちら
相模原生物多様性ネットワークチャンネル
めちゃくちゃわかりやすいです
(ファンキー感は抑えめ!?)
この講義無料で観れるなんて、意図を感じて痺れる!
一時間くらいあるけどあっという間です。
小学高学年生くらいに聞きたかった!(笑)
(私の世代だと生物多様性という言葉ができたのが中学生?高校生?くらいやん!)
津波でお母さまを亡くされた漁師さんが
それでも津波は海を豊かにしてくれるんだって語られた話が深く染み入ります・・・
今回の台風も、海をかき回して去って行かれましたね。。。
なんというか、
はじめて意識の探求にコミットするきっかけとなった、とてもとてもお世話になった方の相方さまが生物多様性の研究の先生だったり、
たまたま惹かれて入った蝶の絵の個展の画家さんが、生物多様性条約会議COP10の絵を描かれていたり、
(小松孝英さん 日本画で描かれる虫たちが活きいき美しいすぎます、、、写真は小松さんのTwitterからお借りしています)
東チベットで一緒に野山を歩いていろいろ教えてくださった先生が、生物多様性読本を書かれた上赤博文先生で、チベット移動中の車内でもビオトープのお話など色々聞かせて頂いたり、、、
人生の要所要所ででてくるキーワード。
そこでたち顕れててくるのは経典の中身のような世界。
そして
「私たちの身体の中にも生物多様性がある」
意識とハートと身体を繋いで
多観点的に 知覚を拡げながら
なんかまとまらずに失礼致しました。。。
昨日の朔日参りで地元の神社 松の香り
薬草のてしごと笑み草
(新しいショップ開設しました)
teshigotoemisou.stores.jp