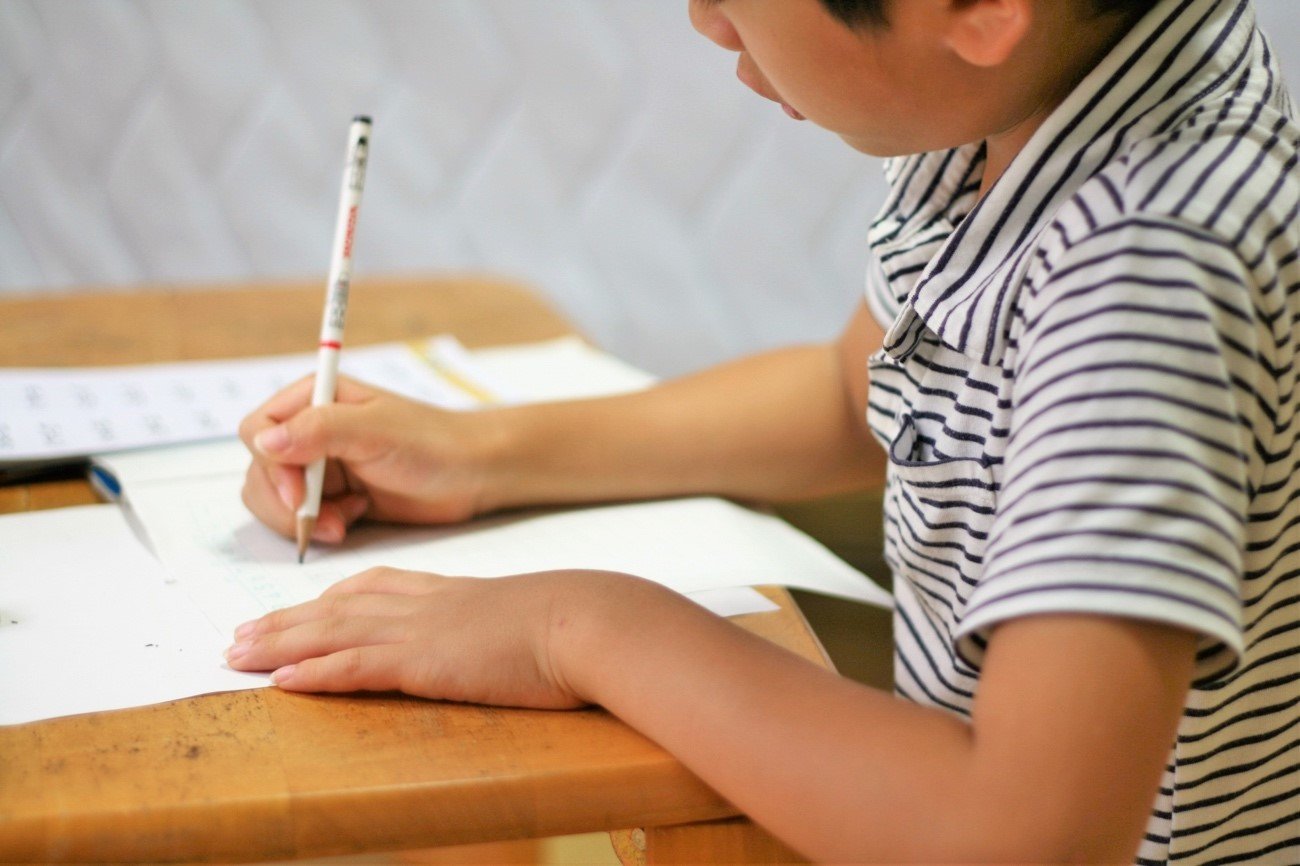こんにちは、訪問ありがとうございます
前回の続きです。
幼稚園までは、耳、口、目、体を使って体験する学習
読み聞かせ、パズルしたり、正方形の積み木を使った遊びや数え方
例えばピラミッド9、4、1、なんて積んだり次は土台16個が良いんじゃね?
1段、2段は2+2個必要だね、3段は3+3+3だね
次はじゃあ、4個が4ついるね、
なんて自然に平方数を教えたりね。積み木積んで壊さずに使った積み木かぞえれる?
なんて事してました。
脳細胞は、脳神経細胞です。
発表概要:
経験的に、学ぶことで頭をよく使えば、学習能力が高まることが知られているが、この際脳の細胞にどのような変化があるか、詳細について不明であった。マウスの海馬において、今回、学習の際に特徴的に現れる脳回路活動(シータ波)によって、記憶形成を担う海馬新生ニューロンの分化が促進されることがわかった。「学ぶほど頭がよくなる仕組み」の一端を垣間見ることができた。
脳神経細胞は、「学ぶほどに分化し枝分かれが増えていく」
「神経回路網が発達すると、難しいことを理解する手助けになるし、
新しいことも、得た知識をもとに覚えやすくなる。」
→勉強すると
「暗記力も上がるし、理解力も向上する」
簡単にいえば、河野玄斗さんが2時間勉強するのと
私が2時間勉強するのでは、
勉強効率は河野玄斗さんのほうがずっと良いだろうと言うこと。
幼稚園から私と毎日勉強していたので、
小学校に入るとことには
長男くんは勉強する「習慣」を身につけました。
これが、私の言う環境整備です。
毎日勉強して、勉強する習慣をつける
塾にいく
家庭教師をつける
親が勉強をみてあげる
本を買い与える
参考書、問題集を用意する
わからないことがあれば教えてあげる
ゲーム機、スマホを与えてやりたい放題にさせない
などなど
どのような方法であれ、毎日毎日勉強すること続けることで
勉強するのが当たり前(習慣)になります。
嫌とかじゃないんですよね。
もう「習慣化」してしまえば。
幼稚園から小学低学年に毎日60〜90分くらい一緒に勉強してました。
私が家庭教師して
難しい問題をとくのですけど、
大手の塾などは
小4〜小5で一通り終わらせて、
小6の1年間で志望校対策
ただ、小4から塾へ行くと、
いきなり難しいことやり始めるので、
小3から塾へ行くための下積みを家庭ですることも多いようです。
長男くんは、年長さんで小1
小1でハイクラス算数、スパーエリート問題集などをやり始めました。
スーパーエリート問題集とかめちゃくちゃ難しいからね。
小3で教科書レベルの算数6ねんまでやってと
スーパーエリート問題集してと
年長さんから毎日私とマンツーマンで毎日勉強してました。
数学以外は勝手に覚えてたので、
漢字とか書けないとかなかったですね。
成績が良い子の親に聞いてみた!
https://coeteco.jp/articles/11235
抜粋すると、
「小学校の頃も勉強はしていました。ただ友達に聞かれて『3時間』とか答えると驚かれたり、逆にからかわれたりするのが嫌だったらしくて。『宿題だけ』と答えている、とは言っていましたけど」
「息子は幼児期から飛び抜けて記憶力が良かったんです」
4人とも、幼児期から子どもに本を与え、時には読み聞かせをし、自由に本を選ばせていたといいます。
「本が好きな子に成績が良い子が多い」は事実のようで、次のようなデータもあります。このグラフは、小5から中3まで約4万人の「平日の読書時間」と「主要教科の平均偏差値」を調べた結果です。
あるデータによると
読書を全くしない子と、30分以上の読書をしている子とでは、平均偏差値が大きく違います。
小学校時代に、タバコを吸って夜遅くまで遊んでいるような
悪ガキの私が、
思い出すと、
私は、「シートン動物記」「ファーブル昆虫記」「江戸川乱歩の少年探偵シリーズ」
などは、図書館にあるだけ読んでました。
全部合わせてもそんなにないけどね
家では読まないで、学校の授業中?に授業が暇すぎて読んだり、
休み時間に読んだりと
本が好きでしたね。
塾にも、対して勉強しなくても、
一発でなんでも記憶しちゃうような才能(遺伝情報)持つ人もいるけれど、
まあ端的にいって、
ほとんどの頭の良い子ってのは、
「勉強をする習慣が小さい頃から身についている」って
ことだと思います。
小1や小2子がが自分から勉強できるわけがないから、
親が勉強する環境を整備しているんです。
ここが、低収入かつ低学歴の保護者さんが、
高収入、高学歴保護者と差がつくところじゃないかなと思います。
しかも、才能=遺伝情報も優れていれば、
鬼に金棒です。
自分で勝手に勉強して、勝手に頭が良くなって
進学校に通うようになって、東大に行ったり、医者になったなんて
そんな、甘い話はないんですよ〜
(常人離れした記憶力でもない限り、、、)
やはり、小学生から、中学生から、
必死に努力して、親もそのために家庭教師やら塾やら
自分が教えるやらで、お金かけたりして
勉強する環境を整備しているんですよね。
これが出来ない家庭の子は
よほど才能がない限り、高学歴、高収入ってことは難しくなるのです。
勉強が出来る子は、
本人だけでなくて、保護者もそれなりに努力しているってこと。
本人は努力と勉強する習慣を身につけさせられ、
親は金や学力を駆使して勉強する環境を整備する
勉強できない子は
本人の努力も、保護者の努力も足りないってことです。
こうして、二極化は親とその子供の努力によって
より一層進んでいく世の中のなると思います。
私なんて、今でも子供に
毎日毎日3時間くらいの時間を割いていますからね。
大変よ、、、
※20:00から22:30くらいなので、実際は2時間半でした。
年長さんから、小6、中学2年と
9年間で、毎年350日、1、5時間勉強一緒にしたと計算すると4725時間。
こんなに時間をかけたんだな〜と思います。
時給2000円だと945万円もかけたことになるわ。
(時給2000円じゃ大学生家庭教師くらいしか雇えないと思うけどね。
私が時給とって家庭教師するなら最低3000〜4000円は欲しいわ〜)
そりゃ、賢くなるわね。
長男くんの友達が、どうしてそんなに数学が出来るの?
って聞いてきて、
青チャートやってるだけだよって言ったみたいなんですが、
青チャートやるまでに、体系問題集、チャート式体系数学を繰り返しやってマスターして
日々努力してきたっちゅうの。
ちょっと、青チャートを自習でやってるだけちゃうで?
これまでの、積み重ねだっていうの。
と私は思いましね。
このようにして、
継続して努力をしてきた親や本人の成果によって、
貧富の差は作られていくのです。
親も本人も努力してこなければ
当然、年収の高い職業に就くのは難しいよ。