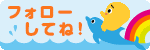そう・・・「ブリティッシュロック」ではなく、この時期に「UKロック」という呼び方が日本ではスタンダードになったのです。
前者はブルースベースのオールドウェイブな語感が強くて、ニューウェイブ以降の音をその名で呼ぶのがそぐわなかったために、この用語が開発されて定着したのでしょう。
英国ニューウェイブの大波は、大西洋を超えてアメリカ大陸を侵食するほど活況を呈していたわけですが、'80年代も後半になるとDURAN DURANのような派手なバンドも落ち着いてきて、入れかわりのようにSIMPLY REDなどの地味目なR&Bがウケるようになって、その分ギターロックは衰退した感じになっていき、'87年のTHE SMITHSの解散がそこにトドメを刺したような形になりました。
刺激を求める若者達は、ライブハウスへロックバンドを見に行くかわりに、倉庫なんかで行われる無料のパーティーに集まるように。
デトロイト・テクノやアシッド・ハウスが流れる中、E(エクスタシー=MDMA)というアッパー系のドラッグで夜通し踊る、それは「レイブ rave」と呼ばれてひとつの文化となり、非合法性の度合は低いながら現在の日本にも存在しています。
近年、日本でもダンスを風営法の改正で規制したり、その緩和措置が取られたりしていますが、英国では'94年にクリミナル・ジャスティス・アクトという法律が制定されて事実上レイブは禁止されることに。
社会問題になるほど盛り上がったということですが、その頂点'88年には'67年のサマー・オブ・ラブ(サンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区に集まった若者たちが共同生活を始め、愛と平和と自由とLSDによる精神の解放を目指したヒッピー文化)になぞらえてセカンド・サマー・オブ・ラブと呼ばれました。
マッシュルームカットにフレアパンツという'60年代ファッションもあの時代の再来を期したものでもあったのでしょう。
くすぶっていたバンド野郎達も、レコード回すだけのDJにおいしい思いをさせておく必要はない、と思ったのでしょう、レイブで踊れるようなギターロックへの流れが加速していき、本格的にダンスビートを採り入れていきました。
その動きが顕著で、もっとも注目されたのが'89年のマンチェスター。
このEPが出てからは「MADCHESTER」という言葉もその代名詞に。

「マンチェスター・ムーブメント」と言ってしまうと地域限定的ですが、そこを起点に英国中に広がって行ったスタイルは当時「インディー・ダンス」とも呼ばれました。
この年に1stアルバムをリリースしたザ・ストーン・ローゼズのブレイクによって「マンチェスターでなにかが起きているらしい」と翌1990年にはマッドチェスターは世界に知られるムーブメントに。
なにか新しい動きが起こる、その胎動を感じさせるようなこのオープニング曲をどうぞ。
アルバムには'60年代アメリカ的なフォーク・ロックっぽい曲も多いんですが、ブレイク以前はジョイ・ディヴィジョンっぽいダークな感じ。
そこから時代の空気を得て大転換を図ったわけです。
THE STONE ROSES - I Wanna Be Adored
アートの香りも感じさせるローゼズに対して、ギャングのニオイを感じさせるのがハッピー・マンデーズ。
一番ちゃんとした曲らしい、'90年のこの曲を。
サビのコーラス部分はLABELLEの"Lady Marmalade"ですね。
HAPPY MONDAYS - Kinky Afro
中心人物ショーン・ライダーの横でゆらゆら踊っているのはバンドのマスコット的存在(=タダのジャンキー)のベズです。
何もしなくても正式メンバーw ちゃんとアルバムにクレジットされています。「ベズ:担当=ベズ」として。
それを真似てか、ダンサーをステージに配置するのが流行って、この年に来日したジョニー・マーを擁するザ・ザまでもが、身体の線を強調したノースリーブのセクシーダンサーを帯同していました。(ジョニーもマンチェ・ダンスをちょっとだけ披露)
インスパイラル・カーぺッツは、今ではオアシスのノエルがローディをやってたという話にしか出てこないバンドですが、最近久々の再結成アルバムが出たもよう。
朴訥としたヴォーカルとアイドル性皆無なたたずまいからして、地味な印象なのは確かですが、よく聴けばけっこう味わいがあるバンド。
マイナー調の歌メロに絡むハモンドオルガンもなかなか哀愁があります。
INSPIRAL CARPETS - Generations
彼らは自主レーベルCowからのリリースで、牛のレーベルマークが印象的でした。
ライブでも会場全体「Moo ム~~~」(日本で言う「モ~」)と重たく鳴くのがお決まりだったらしいw

上記のマンチェ御三家はいずれも'80年代前半からの活動歴があるバンドですが、ザ・シャーラタンズは'88年結成という後発組。
ヴォーカルのティム・バージェスのアイドル顔も、労働者階級には毛嫌いされたのでしょう、よくある話。
当初は「インスパイラル・ローゼズ」とか言われてニセモノ扱いされていましたが、メンバーの死やトラブルをいくつも乗り越えて、現在に至るまで継続的に活動しているのは結局このバンドだけなんですよね。
近年はドラマーの闘病でティムのソロ活動が中心になっていましたが、昨年の死を乗り越えて新年早々アルバムが出る模様。
2001年の7thアルバム「WONDERLAND」ではダニー・セイバーの手を借りた先鋭的な打ち込みサウンドに傾斜したり、果敢にサウンドを変化させて良質な作品を節目節目で発表しています。
なによりいいメロディを書けるのが一番の魅力なわけですが、結果的にもっともプロ意識が高かったということですね。
'92年の2NDアルバムから、攻撃的なオルガンが魅力のこちらをどうぞ。
THE CHARLATANS - Weirdo
選曲にはいつも悩むのですが、どうしても21世紀の今聴いても魅力のあるほうを選んでしまうわけで、その分当時の雰囲気からちょっと外れてしまうのは痛し痒しなんですよねぇ。
今回もそんな感じで、当時のマンチェらしいダンスビートの曲は出てきてないので、
かわりに「これぞマンチェ1990!」という曲を聴いてください。
CANDY FLIP - Strawberry Fields Forever
グラウンド・ビートと呼ばれた、このリズムの曲はこの時期ホントにたくさん作られました。
このドラッギーな永遠の名曲にピッタリきてるのは確かでしょ。
実際、この後ノリビートの起源はリンゴ・スターだとか、いやABBAだ!とかいろいろ言われましたが、多幸感のある横ノリは今聴いても気持ちイイ。
ホントにこいつらが作ってんの?という疑問も湧いてくる、実態がよくわからない2人組ですが、ネーミングの由来はLSDとEの混ぜ物だとか。
'60年代にこの曲を作らせた薬物と、'90年代にカバーしてヒットさせた薬物のミックスということでリンクさせてるのかも。(考えすぎの可能性大)
グラスゴー出身のプライマル・スクリームは、ネオアコ→ガレージパンクと、その時その時で表層的な音楽性をコロコロコロコロコロコロコロと変えてきたバンドで、その後もサザンロックだったりテクノ、ダブと現在に至るまで好き勝手にやってますが、この時期は当然のようにマッドチェスターの影響を受けて、'90年に「Loaded」「Come Together」とアシッドなダンスナンバーをヒットさせ、その集大成として完成させた3RDアルバムが「SCREAMADELICA」
インディーダンスの金字塔と言えるでしょう。
スクリーマデリカ/プライマル・スクリーム

ジャー・ウォブル(現在打ち込みでも使われるウォブルベースという名前の由来になってる元PILのベーシスト)の地を這うベースが、よりアシッ度を倍増させていますが、こんな曲がシングルとなってヒットしたのもこの時代ならでは、というべきか。
PRIMAL SCREAM - Higher Than the Sun
3年後にオアシスと共にブリットポップの2大巨頭となるブラーも'91年春の2NDシングルではこんな感じでした。
BLUR - There's No Other Way
リズムから髪形まで見事におマンチェを気取っていますが、ロンドン周辺のバンドもこの頃までは彼の地の音をなぞっていたという好例。
'91年も後半になるとシューゲイザーのムーブメントが勢いを増してきて、さらにはアメリカ大陸からグランジの大波が加わり、マンチェスター勢は轟音ギターの渦に飲みこまれていくという末路をたどったわけです。
時代を拓いたストーン・ローゼズも有効な二の矢を放てず、94年にロック色を増した2NDアルバムをやっとリリースしたものの、時代に取り残された感じ・・・いい曲はあったんですけどね。
2011年にはまさかの再結成を果たして翌年のフジロックにも来て、新作も作るという話でしたが、予想どおりの集金リユニオンに終わりそう。。。
まぁそんな感じのお祭り騒ぎではありましたが、シーンをギターバンドの手に引き戻して'90年代のUKロック隆盛の扉を開いたとともに、ハウスミュージックのDJがギターバンドの曲をリミックスしたり、テクノユニットとバンドのヴォーカルがコラボしたりと、双方の活動範囲がクロスオーバーしてお互いの音楽性を醸成していって次世代につなげていった意義は大きかったと思います。
当時、ミュージシャン側からも「オーディエンスが主役」といった意味の発言が多くなされていましたが、今考えてみればステージ上のミュージシャンと観客がひとつになる、その媒介として音楽やダンスがあるという思想は、シングアロングやモッシュを前提として曲作りをする、今現在のライブやフェスのあり方に繋がっていくものでしょう。
ミュージシャン→観客という一方的なスターシステムから、双方向のコミュニケーションへ転換する契機となったのがこの地点なのかもしれませんが、必ずしもいいことばかりではなかったというのが現在の洋楽不況という現実が示しているということですかね。