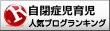私がブログを通して、日本の皆様へ伝えたい!
と思ったきっかけとなった
目からウロコが落ちる
自閉症スペクトラムや発達に凸凹があるお子さんへの接し方について
説明している記事を
「私の体験記」という
3テーマにまとめました。
私の根本はここですので、
ぜひ、このテーマの記事を読んでいただきたいです。
*********************
今日も
ポリヴェーガル理論から読み解くADHDと自閉スペクトラム
のシリーズの続きです。
モナ
教師の心の在り方や考え方が変わると、
とてつもない変化が起こります。
生徒の
「問題行動」を管理することのみに
焦点を当てることから、
生徒の感情に焦点を当て、
生徒の感情を
教師が一緒に整えようとすること
(Co-regulation 共調整)
にシフトするだけでも、
教師の気持ちが穏やかになります。
ご両親にも同じことが言えます。
私自身、
親としてこの考え方へシフト
(パラダイムシフト)する前は、
「子供の問題行動を
減らすようにしなくちゃいけない。
それには私は
どういう戦略を使うのがいいかな?
こんな言動は失礼だし、
するべきではないし、
他の子供が
真似してしまうかもしれない。」
と考えていました。
でも
子供に対する見方や考え方を変えて、
その時その時の
子供を観察するようになると、
誰がそわそわとして
落ち着きがない様子なのか、
誰が隣の席の子供に
ちょっかいをかけようとしているのか、
といったことから
クラスの中で
どの生徒が
脅威のシグナルを感じやすいのか、
特定できるようになります。
もちろん教師は
年度初めには
こういうことを観察していると思います。
ただ、
そういった生徒を
評判の悪い問題児
として見るのではなく、
神経系が
脅威のシグナルを受け取りやすい、
繊細な子供で、
教師のサポートや理解が
必要な生徒として
認識してください。
そうすれば
その生徒が
ソワソワと動き始めたときに、
それが
その生徒の神経系が
安心安全を感じている状態から、
脅威や危険を感じている状態へ
移行しつつある
というサインだということに
気が付きます。
そうしたら、
例えばその生徒に
「ジョニー、
ちょっとお手伝いを頼んでもいい?
この重い本を
○○先生の教室まで
届けて欲しいんだけど。」
(重いものを運んで
大きな筋肉を動かすことは、
神経系を落ち着かせる働きがあります。
それと同時に、
先生がちゃんと
自分の状態を分かってくれていて、
サポートが必要なことを
理解してくれている。
そして
そういう自分を
否定せずに受け入れてくれている
という
子供へのメッセージになります。)
といった助け舟を出して、
生徒がまた
安心安全を感じる状態に
戻してあげることができます。
例えば
子供が落ち着きをなくして
椅子から落ちてしまったような場合でも、
先生が他の生徒に
「ジョニーの体は今
動く必要があっただけです。
時と場合によって、
一人ひとりの体が
違うことを必要としていることがあります。
みなさんも
試しに 今
自分の体が
どんな動きを必要としているか、
ちょっと感じてみてください。
自分の体に
必要な動きをしてあげることで、
落ち着くことができます。」
といった声掛けを
してあげることができます。
続きはこちら。
読んでいただいてありがとうございます。
応援してくれる方はこちらの2つをクリックしていただけると嬉しいです。 ランキングが表示された後に出る一覧からまた私のブログのリンクをクリックしてくれたりしたら ものすごーく喜びます。