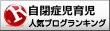こんにちは!
この記事の続きです。
内受容感覚機能が高まってくると、感情のコントロールができるようになってきます。
自分の体が今どういうことを感じているのか、そしてそれがどういう意味を持つのか、ということを認識できるようになるからです。
そうすると、お腹がすきすぎてイライラしたり力が出なくなったりする前に食事を取ることができるようになったり、人の家に遊びに行った時に、周りの雑音や動きからの刺激が大きすぎてパニックになる前に静かな場所に避難したりすることができるようになってきます。
こういったことができるようになると生活がかなり快適になり、自分のやりたいことや目標に力を注ぐことができるようになってきます。
他の7つの感覚統合をすすめることで内受容感覚を高めることができるのかどうかというのは まだ分かっていません。
ただ言えることは、自閉症スペクトラムの人の多くは感覚過敏があり、いつどこから来るかわからない不快な外的刺激に対して常に警戒して暮らさざるを得ません。そういった状況では 自分の体がどう感じているのかといったことに意識を向ける余裕はできません。
なので、他の感覚機能を統合していくことで、外的刺激に対して警戒する必要をなくし、自分の体がどう感じているかに気を配る余裕ができることによって内受容感覚機能を高められる状態にすることができるという意味で、他の感覚機能を統合していくことはとても大切です。
<トイレトレーニングと内受容感覚>
内受容感覚の発達は トイレトレーニングにも影響します。
自分の膀胱がどう感じているのかをわからなければ、自分が今おしっこがしたいんだということに気づけません。また、膀胱がいっぱいになったと感じることができても、それが おしっこがしたいということだと意味づけできなければ タイミングよくトイレに行くことができません。
なので、まずは子供に膀胱がどこにあるのか、そして膀胱におしっこがたまること。そして膀胱がいっぱいになってあふれる前にトイレにいかないとおもらしをしてしまうことを教えます。
(膀胱は目に見えないので、まずは手や足や皮膚など 目に見える体の部分がどう感じているのかに気づく練習をしてからのほうがうまくいきます。心臓や胃や腸なども同じことが言えます。)
そして、おしっこが出る前には体はどう感じたか、おしっこが出ている最中には体はどう感じたか、おしっこが出た後は体はどう感じたかについて話して、教えていくことが大切になります。
このシリーズはこれでおしまいです。
読んでいただいてありがとうございます。