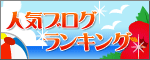「できる」の5レベル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
レベル1:説明されればわかる
レベル2:ヒントをもらえば解ける
(または、途中まで解ける)
レベル3:ヒントなして解ける
レベル4:解き方を説明できる
レベル5:類問や応用問題を作れる
レベル1~2は、本当の意味でわかったとは言いません!
テストでは解けないのですから。
でも塾や学校の先生の説明を聞いて
わかったつもりになっている生徒さんは想像以上に多くいます。
私も授業をしていて
「あーーー!なるほど!!」
と生徒さんの笑顔が咲くときは本当に嬉しいです。
しかーし、
それで「あぁこの問題はもう大丈夫」と思うのは間違い。
そのままでは、たった3日ですっかりキレイに忘れていることも多々あるからです。
最低限、レベル3までもっていかないと
実践では役立ちません。
ですので、本当にその問題が解けるようになったか確認するため、
その日のうちに解き直しをするといいでしょう。
(特に算・理・社)
ベストなタイミングは寝る前です。
その日間違えた問題をザッと見返して解き方を思い出しましょう。
しかし、実際にはレベル3どまりの知識は
あっという間に抜け落ちます。
「あれ?前回のテストではできてたのに
どうしてうちの子今回はこんなに間違うの?」
それはレベル3どまりの知識だったからです。
ではどうすれば長期記憶に入りやすくなるのでしょうか。
そうです。
レベル4まで引き上げればいいんですね。
塾の説明を聞いた。
テスト直しの解説を読んだ。
テキストを読み直した。
うんわかったわかった。
で、おわってはダメ!!!
この問題をどう解くのか、
お母さんやお父さんに説明してみましょう。
(このとき、どんなにもどかしくても
聞く人が先を急がせてはダメです。
まずは「聞く」ことでやる気を育みます。)
おうちの人がどうしても忙しかったら
同じ塾のお友達同士でやるか、
お部屋のぬいぐるみに向かってやりましょう。
私は猫に向かってブツクサ説明しながら
高校&大学受験を乗り切りました![]()
もし途中で説明できなくなったら
まだまだ知識が定着していない証拠です。
もう一度解説を読んで、答えに行きつく道筋を頭に叩き込んでから
再度説明をしてみましょう。
いそがばまわれ。
わんこそば状態で与えられた課題に答えを写しても何の力もつきません。
気力と時間の無駄遣いです。
基本問題こそ丁寧に理解をすすめ、
深く深ーく長期記憶に埋め込みましょう!
(レベル5は御三家レベルを狙う、余裕のある生徒さんが暇つぶしにやればいいです。)