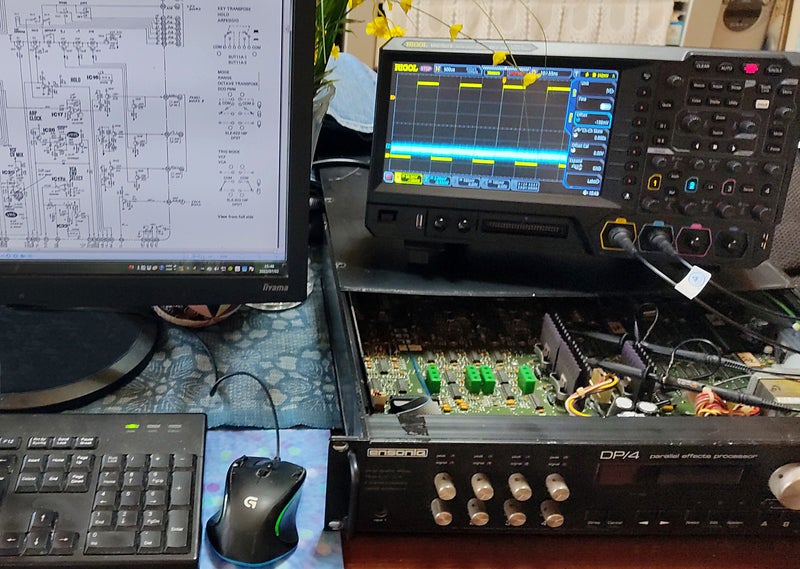イギリスのEMS社のシンセサイザーといえば、SYNTHI-AKS。
アタッシュケースに仕込まれた、モノシンセとシーケンサー付きのキーボードは、3VCO-VCF-TRAPEZOID(VCA/ENV)で256stepという一般的な構成ですが、まさに「電子音」的な音を奏でます。
リングモジュレーターとスプリングリバーブとジョイスティックを駆使すれば、1970年代のSF映画に出てくる「効果音」や「テーマソング」をそのまま作れてしまう、レトロなシンセサイザーです。
SYNTHI-AKSの内部は、3枚の基板があるだけで極めてシンプル。
すべてトランジスタでシンセ回路ができているので、MINIMOOGと同じくらい「音抜け」がいい。
しかし、VCFがMINIMOOGと違うのと、トランジスタがイギリス製なので、いかにも保守的で「古臭い」音になるんですが、それがEMSらしくていい感じです。
キーボードもタッチセンスの、シンプルな30鍵。
256stepのシーケンサーは、TTLロジックIC 20個ほどで回路が組まれていて、これも必要最小限。
当時の「最先端」の技術が使われていますが、CPUを使わないでよく形にしたものです。
EMS VCS3は、SYNTHI-AKSの本体だけをそのまま木製の筐体に入れたもの。
なので、スピーカーの響きが上質になっています。
SYNTHI-Aだとスピーカーの取付けが窮屈で、音量を大きくするとビビリが出るとか、スプリングリバーブがハウリングを起こしてしまうとか「クセ」があるんですけど、VCS3はそこらへんを気にしなくて良くなります。
ブライアン・イーノがVCS3を使用していたのも、「楽器」として優れていたからでしょう。
日本人はSYNTHI-AKSのほうが好きな人が多くて、中には、渋谷の街をAKSのアタッシュケースをぶら下げて歩きたいという人もいるほど。
それは、SYNTHI-AKSが大好きだったからでしょうけど、日本では楽器として使うよりも、「エフェクター」として音の変化を楽しむ人が多いようです。
SYNTHI-AKSもVCS3もMOOG以前のシンセなので、音程CVがV/octじゃないとか、接続するVCOの数が変われば音程CVを調整し直しとか、音程の管理が面倒ということなんでしょうね。
日本での人気は、圧倒的にSYNTHI-AKSのほう。
でも、このシンセは、音楽で「価値」を作り出せる人じゃないと、その「真価」を引き出すのは難しいように思えます。
「クセ」が強すぎて、そのクセを利用して「曲」を作れる人じゃないと、使いこなせないということです。
個人的な見解ですけど。
ヴィンテージシンセの修理と、レストアのお問い合わせはコチラへ
担当の吉田が承ります
ビンテージ・ファイブ・ステート
https://vintagefivestate.shopinfo.jp/
vfstate@gmail.com
業務30年で、細かいものを入れれば、修理実績5000件超!
ふつうの故障からレストアまで、おまかせください