こんばんは。柏原です。
今日は、ちょっとビジネスの話から脱線して、
自分が個人的に興味のある「武道」の話です。
以前にもこのブログで、私は「西野流呼吸法」を
やっていますと申し上げましたが、
創始者である西野皓三先生は、バレエの身体芸術を起点に、
合気道、中国拳法のエッセンスを取り入れ、独自のメソッドとして、
西野流を創始されました。
西野流を学んで以来、生命エネルギーの「氣」に興味を持ち、
中国拳法のひとつである「意拳」の流れを汲む「神意拳」を半年ほど学び、
自己のカラダの変化に、ますます興味が湧いたものです。
年齢を重ね、もう少ししたら合気道を学びたいと思っているのですが、
その合気道の「源流」とも言えるのが、「大東流合気柔術」で、
実はこの大東流が、タイトルの「八重の桜」と関係しているのです。
NHK大河ドラマ 「八重の桜」完全読本 (NIKKO MOOK)/産経新聞出版
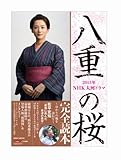
¥1,050
Amazon.co.jp
「八重の桜」の登場人物である、西郷頼母(さいごう たのも)は
会津藩の家老ですが(役:西田敏行さん)、wikipediaなどにも記されているように、
彼の明治以降の経歴はとても複雑です。
いわく、西郷隆盛と交遊があった(縁戚関係にあったそうです)ために、
宮司の職を解かれ、長男の病没後に迎えた養子に柔術を教え、この人が後に
講道館に入門し大成、「姿三四郎」のモデルとなったとされ、
更にはかつての藩主・松平容保が日光東照宮の宮司となった折には、
禰宜となるなど、時代にほんろうされつつも、
最後まで「武人」として振る舞った人でした。
その、頼母が元来習得していたのが、会津藩に古来伝わる「大東流合気柔術」で、
元々は甲斐武田氏につたわる武術だったのです。
それが甲斐から会津武田氏につたわり、武田惣角が広めたとされています。
ここに頼母との接点があり、頼母は家老時代に武田惣角の祖父・惣右衛門から
大東流の秘伝を授けれらています。
ここまで色々読むと、大河ドラマでの西田さんの演技ぶりを、
違う郷愁をもって見てしまい、個人的に応援してしまいそうです(笑)
頼母は惣角に大東流の秘伝を伝え、正式に伝承者となったそうです。
大東流合気柔術 [DVD]/クエスト
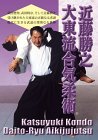
¥5,880
Amazon.co.jp
つまり、頼母が会津戦争で戦死していれば、大東流は存在しなかったのではないか?
大東流が存在しなければ、合気道もなかったのでは?
ちなみに、合気道の創始者・植芝盛平は、武田惣角の弟子です。
ならば、西野流も今のカタチでは存在しなかったのでは・・・とまで思ってしまいます。
いや~ なかなか入り込みましたね。
(ぜんぜん八重の出番がなかった・・・)
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
今日は、ちょっとビジネスの話から脱線して、
自分が個人的に興味のある「武道」の話です。
以前にもこのブログで、私は「西野流呼吸法」を
やっていますと申し上げましたが、
創始者である西野皓三先生は、バレエの身体芸術を起点に、
合気道、中国拳法のエッセンスを取り入れ、独自のメソッドとして、
西野流を創始されました。
西野流を学んで以来、生命エネルギーの「氣」に興味を持ち、
中国拳法のひとつである「意拳」の流れを汲む「神意拳」を半年ほど学び、
自己のカラダの変化に、ますます興味が湧いたものです。
年齢を重ね、もう少ししたら合気道を学びたいと思っているのですが、
その合気道の「源流」とも言えるのが、「大東流合気柔術」で、
実はこの大東流が、タイトルの「八重の桜」と関係しているのです。
NHK大河ドラマ 「八重の桜」完全読本 (NIKKO MOOK)/産経新聞出版
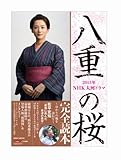
¥1,050
Amazon.co.jp
「八重の桜」の登場人物である、西郷頼母(さいごう たのも)は
会津藩の家老ですが(役:西田敏行さん)、wikipediaなどにも記されているように、
彼の明治以降の経歴はとても複雑です。
いわく、西郷隆盛と交遊があった(縁戚関係にあったそうです)ために、
宮司の職を解かれ、長男の病没後に迎えた養子に柔術を教え、この人が後に
講道館に入門し大成、「姿三四郎」のモデルとなったとされ、
更にはかつての藩主・松平容保が日光東照宮の宮司となった折には、
禰宜となるなど、時代にほんろうされつつも、
最後まで「武人」として振る舞った人でした。
その、頼母が元来習得していたのが、会津藩に古来伝わる「大東流合気柔術」で、
元々は甲斐武田氏につたわる武術だったのです。
それが甲斐から会津武田氏につたわり、武田惣角が広めたとされています。
ここに頼母との接点があり、頼母は家老時代に武田惣角の祖父・惣右衛門から
大東流の秘伝を授けれらています。
ここまで色々読むと、大河ドラマでの西田さんの演技ぶりを、
違う郷愁をもって見てしまい、個人的に応援してしまいそうです(笑)
頼母は惣角に大東流の秘伝を伝え、正式に伝承者となったそうです。
大東流合気柔術 [DVD]/クエスト
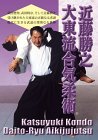
¥5,880
Amazon.co.jp
つまり、頼母が会津戦争で戦死していれば、大東流は存在しなかったのではないか?
大東流が存在しなければ、合気道もなかったのでは?
ちなみに、合気道の創始者・植芝盛平は、武田惣角の弟子です。
ならば、西野流も今のカタチでは存在しなかったのでは・・・とまで思ってしまいます。
いや~ なかなか入り込みましたね。
(ぜんぜん八重の出番がなかった・・・)
最後までお読み頂き、ありがとうございました。