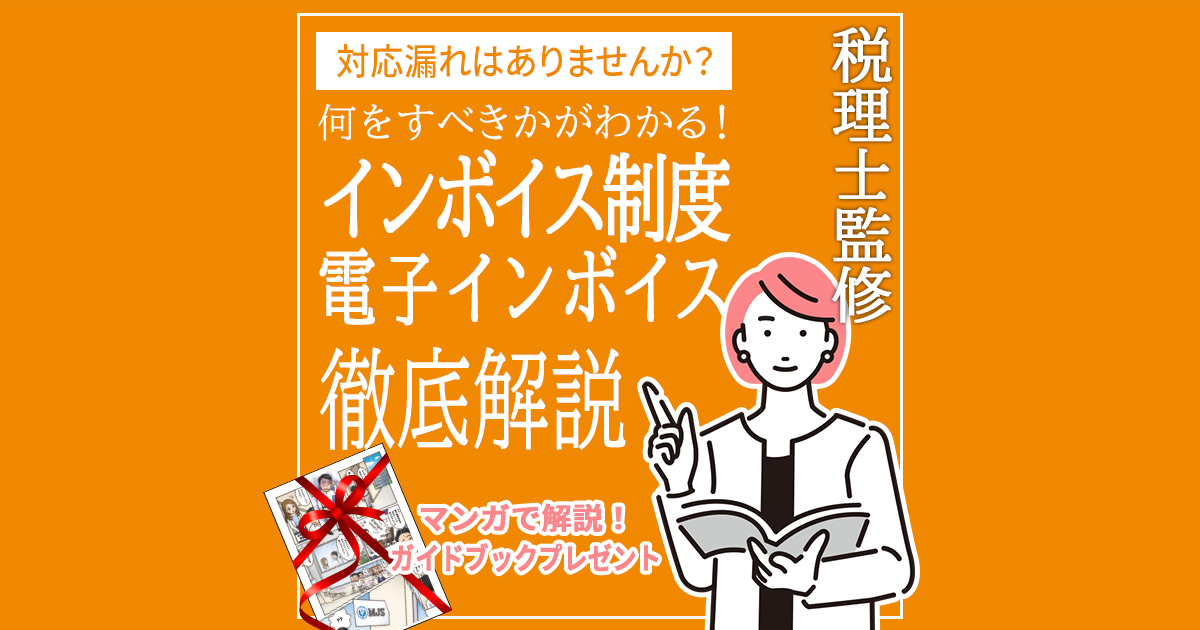10月から始まるインボイス制度の準備はお済ですか?
10月1日からインボイス制度(適格請求書)が始まります。
皆様導入準備はお済でしょうか。
今更ですがインボイス制度ってなに?という事を少し説明させていただこうと思います。
【国税庁の説明】
【分かりやすい民間の説明】
インボイス制度を本当に《超ざっくり》説明すると、売り手側(企業や個人)が発行する請求書(これを適格請求書といいます)を発行するときに、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載して請求します。
こうすることで請求を受けた側は消費税を全額経費として計上出来ます。
今までと何が違うんだと思われるかもしれませんが、ポイントは《登録番号》です。
請求する側が適格領収書を発行するためには申請(これを適格請求書発行事業者登録申請と言います)して【登録番号】を取得する必要があります。
この登録事業者にならないと請求を受ける側(買い手企業や個人)は消費税を全額経費計上できないので、《登録事業者でない企業や個人からの購入を控える》動きが予想されます。
特に今まで非課税事業者であった個人事業主や零細企業などは取引先からの契約打ち切りや負担消費税分の値引きを求められる可能性が高くなります。
大ぴらに値引き要請や契約打ち切りをする企業は無いと思いますが、それとなく圧力をかけられることは可能性として高く、仕事を依頼されている側の個人や零細企業は無言の圧力を受け入れるしかないのが実情です。
インボイス制度の導入で【大きな勘違い】をしている方も多く、驚くべき事ですが政治家の方も間違って認識されている人が多いです。
では【大きな勘違い】とは何か。
それはインボイス導入が、今まで非課税事業者が消費税を支払わず差額を『益税』として懐に入れていて、あるいは『預り金と』して預かっているにも関わらず納税せずに儲けているのを無くすためと思っている事です。
ちなみに消費税は【預り金】でもなく【預かり税】でもありません。
単純に価格の一部です。
これは『1990年3月26日 東京地裁判決』『11月26日大阪地裁判決』の中で触れられています。
この裁判では以下の3つの事が認定されています。
「消費税を支払っているのは事業者である」
「消費税は『預かり金』ではない」
「免税事業者に『益税』は存在しない」
※以下引用先
判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。
※以下引用先
この事は実は昔から議論されていて、今回のインボイス導入の時にも論点となっている事です。
私はインボイス制度自体は税の内容や負担を分かりやすくするので、個人的には良い制度かなとも思っていますが、説明と導入経緯があまりにも『国民に理解されない』状態なので、本格的に導入されるまでにはこの件も含めてちゃんとアナウンスしてほしいです。