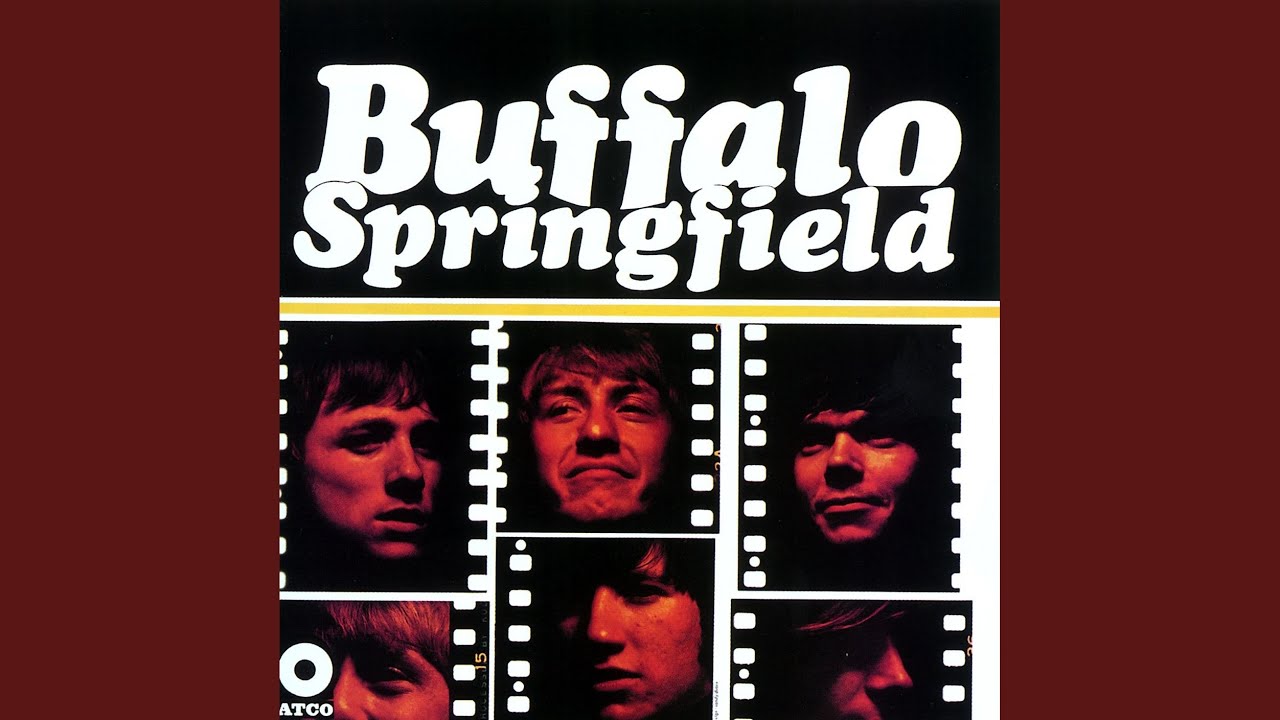1965年にスティーブン・スティルスとリッチー・フューレイがフォ―クグループの一員としてカナダ・オンタリオ州でライブを行った時、前座を務めたバンドに在籍していたのがニール・ヤングであった。その後のウェスト・コースト・ロックの流れを考えるに、この出会いの意味は大きい。66年ヤングは件のバンド解散後別のバンドに在籍しレコーディング寸前だったが、それも諸事情で解散となり、ベース担当だったブルース・パーマーと共にスティルスとのバンド結成を目指しロサンゼルスへと。スティルスの居場所が判らず途方に暮れていた所、偶然スティルス、フューレイらが乗った車とヤングの車が対向車線で擦れ違って再会、ドラマーを加えて『バッファロー・スプリングフィールド』が結成される事となったのだ。
スティルス、ヤング、フューレイという3人のヴォーカル&ギタリストを擁するバッファロー・スプリングフィールドは『ザ・バーズ』の前座などを経て、ロスアンゼルスの有名クラブにレギュラー出演してあっという間にレコーディング契約を交わし『アトランティックレコード』傘下の『アトコ・レコード』からデビューアルバム『バッファロー・スプリングフィールド』を66年12月に発売。だが翌67年2月に発売したシングル『フォー・ホワット・イッツ・ワース』(邦題は『フォー・ホワット』)がビルボードチャート7位まで上るヒットを記録した為、急遽一曲を削って『ソー・ホワット』を収録し、更に曲順を変えた形で1stアルバムを4月に再発。されがさっき聴いた『バッファロー・スプリングフィールド』改訂盤なのだ。
アナログA面1曲目が問題の曲『ソー・ホワット』。バッファロー・スプリングフィールドが出演していたクラブの目の前で起こった、夜間外出禁止令を施行した警察と、それに反対する若者たちのデモ隊(映画『イージー・ライダー』で有名になるピーター・フォンダとジャック・ニコルスンも参加)との衝突を描写した詞と曲をスティルスが作った、タイムリーな曲。一度聴いたら耳に焼き付くイントロ、スティルスのヴォーカルとコーラスの嚙み合わせなど、彼らの代表作にふさわしい曲だ。当然ながらカバーヴァージョンも沢山あるが、有名なのはスティルスの許可を得てイントロをサンプリングで使用したヒップホップグループ『パブリック・エナミ―』であろう。
2曲目『ゴー・アンド・セイ・グッバイ』はスティルス作、スティルスとフューレイのWヴォーカル。カントリーへの傾倒を感じさせる、後にカントリー・ロックバンド『ポコ』を結成するフューレイの色が出た軽快な曲。デビューシングル『クランシーは歌わない』のB面に収録。
3曲目『君を愛していると思う』はスティルス作、スティルスとフューレイのWヴォーカル。初期『バーズ』を彷彿とさせる音色のギターのアルペジオで始まり、間奏ではヤングの重々しいギターとスティルスの軽めのギターがソロを取って好対照。
4曲目『クランシーは歌わない』で初めてヤングの曲が聴ける。曲の前半はフューレイ、途中からスティルス&ヤングのWヴォーカル。切なさが売りになっているメロディーだが、曲構成にはヤングの色が滲み出ている。デビュー曲としてシングルカットされたが、地元でのマイナーヒットに終わって失敗。
5曲目『ホット・ダスティ・ローズ』はスティルス作&ヴォーカル。ミディアム・テンポで淡々と進み唄う。全体的に軽い印象だが、スティルスの硬派ぽいヴォーカルの声質がいいかな…と思う部分はある。
A面最後の曲『みんな悪いのさ』はスティルス作、フロント3人によるコーラスヴォーカル。軽快なドラムスに乗って時流に合わせた「フォ―ク・ロック」ぽい演奏が展開されるのも、やはりバーズの影響があるのかな? ただ爆音ぽく終わるエンディングはインパクトあり。
アナログB面1曲目『僕のそばに居ておくれ』はヤング作、フューレイのヴォーカル、スティルス&ヤングのコーラス。これも節々にヤング色を感じるのだが、フューレイがリード・ヴォーカルなので、その分軽くなってる印象がある。自分が作った曲なのにリードヴォーカルやれないっていうのは…。
2曲目『バーンド』でやっとヤング作&ヴォーカルの曲が登場。更にピアノまで弾いてはりきっちゃてる。独特のやや枯れた様なヴォーカルはやっぱりいいね。曲自体はかなりポップな雰囲気だが、間奏のピアノソロとサイケなギターソロの組み合わせも悪くない。
3曲目『いい娘になって』もヤングの曲だが、ヴォーカルはフューレイ。彼の甘いヴォーカルをフィーチャーした聴き易い曲だが、スティルス&ヤングのコーラスワークには『クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング』に通じる物を感じたりもする。
4曲目『リーヴ』はスティルス作&ヴォーカル。のんびり気味な曲が続いた所で、目の覚める様な激しいロックン・ロール曲を叩き込んでくる。ヤングが歌のバックで荒々しいギターを弾きまくり、スティルスもそれに応えてシャフト気味に唄う。この曲には英国ロック勢からの影響がありそうだ。
5曲目『アウト・オブ・マイ・マインド』はヤング作&リード・ヴォーカル。まるでヤングのソロ曲みたいに彼の世界観が全開になっていて、つい聴き惚れてしまうのだが…。スティルス&フューレイもこの曲ではヤングに付き合って、グッドヘルプなコーラスを担当。
アルバム最後の曲『ペイ・ザ・プライス』はスティルス作&ヴォーカル。まるで「赤盤」の頃のビートルズみたいな曲だが、彼らに負けない演奏力を示したカントリーとロックン・ロールのあいの子みたいな、軽快な曲でアルバムは〆となる。
正規の1stアルバムに『ソー・ホワット』を入れ込んだ為に、バッファロー・スプリングフィールドは単なるヒット曲狙いのバンドじゃ許されない雰囲気になった印象がある。それだけ『ソー・ホワット』が突出した曲だったって事だが、他の収録曲には当時の流行サウンドを取り入れつつ、自分たちの演るべき音楽を模索するスティ-ヴン・スティルスのバンマス的な自負が感じられ、本アルバムの時点では未完成ながらもバッファロー・スプリングフィールドの可能性は大きかったと思う。
だがその一方でニール・ヤングはこのアルバムの時点で既に自分の世界を確立している感があり、それは「バンマス」であるスティルスにとっては、あまり歓迎すべき事ではなかったはず。その二人の間の確執が悪化した事で、バッファロー・スプリングフィールドは短命バンドに終わってしまうのだ…。