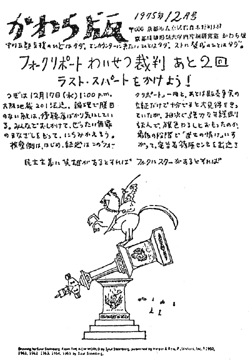絶頂期のよしだたくろう(吉田拓郎)をTVで観ても憧れとか、自分もああなりたいみたいな気持ちには一度もなった事はなかった。でも「関西フォ―ク」の楽曲を聴いた時は自分もギターを弾きたいと思い、拙いながらも自分で曲を作りたいとも考えた。この違いは何だったのだろうか?
俺はリアルタイムで関西フォ―ク運動のムーブメントを知らず、その流れから生み出された楽曲を通しそれを何となく知った。それらが商業的な仕掛けではなく自主的な動きから生じた事にまず興味を持ったし、当時の俺には恋愛ソングなんかよりもリアルで身近な物に感じられたのである。その頃ベトナム戦争は終焉を迎えたばかりで、世の中も音楽界も急速に別方向に展開していった時期であったが、俺は敢えて遅れようとしていたのだ。
『表現の文化研究』は文化社会学研究者である筆者の学術論的本であり、所謂音楽本の類いではないのだが、1968年生まれの筆者は02年にエイベックスから再発された『URCレコード』(関西フォ―ク運動とは密接な関わり合いがあった)の音源を聴いた事で、フィールドワークとして研究しようと考えたという。関西フォ―ク世代とは二回りも歳が違う世代ならではの視点で、客観的な分析を試みている(別稿で政治運動などにも大きな影響を与えた鶴見俊輔の思想、70年大阪万博に協力した当時の前衛芸術家についての考察もある)。
67年の『フォ―ク・クルセダーズ』のブレイクが起爆剤となり、関西の音楽シーンは『べ平連』の市民運動と密接に関わり合い、集会で高石友也が反戦集会などで唄い出した事が評判となり、集会とは別にコンサートの形で外国の曲を和訳で紹介したり、メッセージ性を含んだオリジナル曲を唄う歌手が現れ始めたのだ。
筆者は関西フォ―ク運動の大きな功労者として、片桐ユズルと歌手の中川五郎(表紙の写真も彼)を挙げている。片桐ユズル(1931年生まれ。去年10月に逝去)は都内の高校教員を経て59年に米国留学してビート・ジェネレーションの詩に強い影響を受け、帰国後は神戸の大学で教員として働きながら詩人活動と同時にべ平連やフォ―ク運動もに加わり、67年にミニコミ新聞『かわら版』を創刊。そこで海外の曲や日本の若者が作ったオリジナルソングを楽譜付きで数多く紹介(その中には友部正人の『たむしの歌』なんてのもあって、どんな曲か聴いてみたくなる)。
その『かわら版』で片桐は「替え歌」を奨励的に評価。元歌に捉われず好きな詞を乗っけて唄う事も、歌い手側の自己表現であると定義した訳だ。この流れからボブ・ディランの『ノース・カントリー・ブルース』を真崎義博(現・翻訳家)が『炭鉱町のブルーズ』という自作の詞を乗っけて唄い、それが更に中川五郎によって新たな詞で『受験生ブルース』としても唄い その『受験生ブルース』を高石が改訂した詞とメロディーでヒットさせ、またまた東京のフォ―クゲリラが替え歌『機動隊のブルース』にする…という臨機応変な流れになったりした。
中川五郎は高校生の時(67年)にベトナム反戦集会で高石友也の歌を聴いて衝撃を受け、京都で行われた第一回フォ―クキャンプに出演、同じ年に件の『受験生ブルース』の詞を作り歌唱。俺の同年代の頃と照らし合わせても恐るべき早熟少年と言うしかない。『かわら版』創刊号に片桐の手伝いとして編集に参加。高石や岡林信康は既に青年の年齢に達していた事を考えると、更に凄いなあと思ってしまう。
69年1月にはURC系の音楽出版社から『フォ―ク・リポート』誌が創刊(当初は月刊、後に季刊に。俺は古本屋で73年冬の号を入手した事があるのみ)。創刊号には片桐は勿論錚々たる文化人が投稿している。こちらにも楽譜付きで曲紹介のページがあったらしいが、文章中心の編集で関西情報のみならず、東京フォ―クゲリラ関連の記事も多く載っていたらしい。中川も後に編集に参加する。
と、当時の時代の趨勢と合わせ、URCからは次々と関西フォ―ク系シンガーをデビューさせていたこのムーブメントがどうして下火になったか問わわれば、本書を読むと東京フォ―クゲリラとの軋轢辺りからではないかと推測される。俺は知らなかったがURCレコードから69年8月に『”新宿69年6月” ドキュメント69/70シリーズ№1』という17cmアルバムが発売されていた。日比谷野外音楽堂での、高石とフォ―クゲリラの論争が収められている珍しいレコードである。その中で問題とされていたのは、高石が集会などの活動と同時進行で芸能活動や映画出演(加山雄三主演作『弾痕』に出演し谷川俊太郎作詞、武満徹作曲の『死んだ男の残した物は』を歌唱)。この問題から見えてくるのは、フォ―クゲリラが反戦集会を盛り上げる為のメッセージソングやプロテストソングとして「うた」を捉えているのに比して、片桐ユズルなどはまず「うた」の存在価値を認める事から社会変革などに繋がるのではないかと考えており、そこに大きな隔たりがあった。
そもそも高石はボブ・ディランがそうであった様に、元々がプロ歌手になる事がそもそもの希望であり、反戦運動に加わったからといって活動家になりたい訳ではなかった。この論争は極論的に「歌で金銭を得る事自体がフォ―クとは言えない」という意見になり、それが71年『第三回全日本フォ―ク・ジャンボリー』が中途で粉砕される原因となり、関西フォ―ク運動は終焉を迎える事になってしまった。加えて高石はマネージャーの某氏(URCレコードの社長でもあった)の厳しい搾取にうんざりしていたと証言しており、それが関西フォ―ク運動からの離脱に繋がった。
関西フォ―クブーム退潮後も地道にそれに纏わる活動を継続していた中川五郎にも落とし穴が。変名で『フォ―ク・リポート』70年冬の号に執筆した小説『ふたりのラブジュース』が関西の高校教師のタレコミでわいせつに当たると警察に摘発され、中川は被告としてこの裁判に約10年関わる事になる(80年最高裁で有罪確定)。
検察側の態度は中川を舐め切った物で(摘発されてから2年放置してから、予告なく裁判所からの出廷要請通知が届いた)、定期的に大阪の裁判所へ通わなければならない心理的な苦痛は相当な物だったらしく、彼の音楽活動自体にも大きな影響を及ぼした(シンガーとしての活動より、米国シンガー・ソングライターのアルバムのライナー・ノーツや和訳執筆、評論活動が中心になった)。
前述した様に本書は音楽本ではない為、関西フォ―ク運動で唄われた楽曲の魅力を語るのではなく、それが文化的表現としてどの様な影響を及ぼしたのかに執心して語られており、本書執筆の為に行われた片桐&中川へのインタビューの中身が、本書を読む限りでは一切判らないというのも欠点。ただ文化的な意味で必然的に「企業の論理」以外で起こった音楽ムーブメントの始まりとして、関西フォ―ク運動を記憶に留める事は重要であり、そこで唄われた「うた」も時代を越えた価値を持っているはずで、個人的にはそれを再確認できただけで有効であった。
関西フォ―クブーム終焉後の片桐ユズルは関西フォ―ク第二世代とも言うべきシンガーを伴って『かわら版キャラバン』なるライヴを行い(URCでレコード化。中川も参加)、京都に喫茶店『ほんやら洞』を設立して詩の朗読会を実施、詩人兼外国文学者の中山容と共訳で『ボブ・ディラン全詩集』を74年に出版している。
中川五郎はというと、バブル時代は誰もが知っているメンズ雑誌のライターや編集にも携わったりもしたが、90年代は酔いどれ作家兼詩人のチャールズ・ブコウスキー作品の翻訳者として有名になり、ゼロ年代からはかつての関西フォ―ク時代のスピリッツを継承する様な自作の歌を唄い出した。「これだけ今の社会は問題を抱えているのに、何故日本には『君を信じてる』風な歌しか存在しないのか」という町山智浩の問いかけに、唯一応えてる人と言えるだろうか。