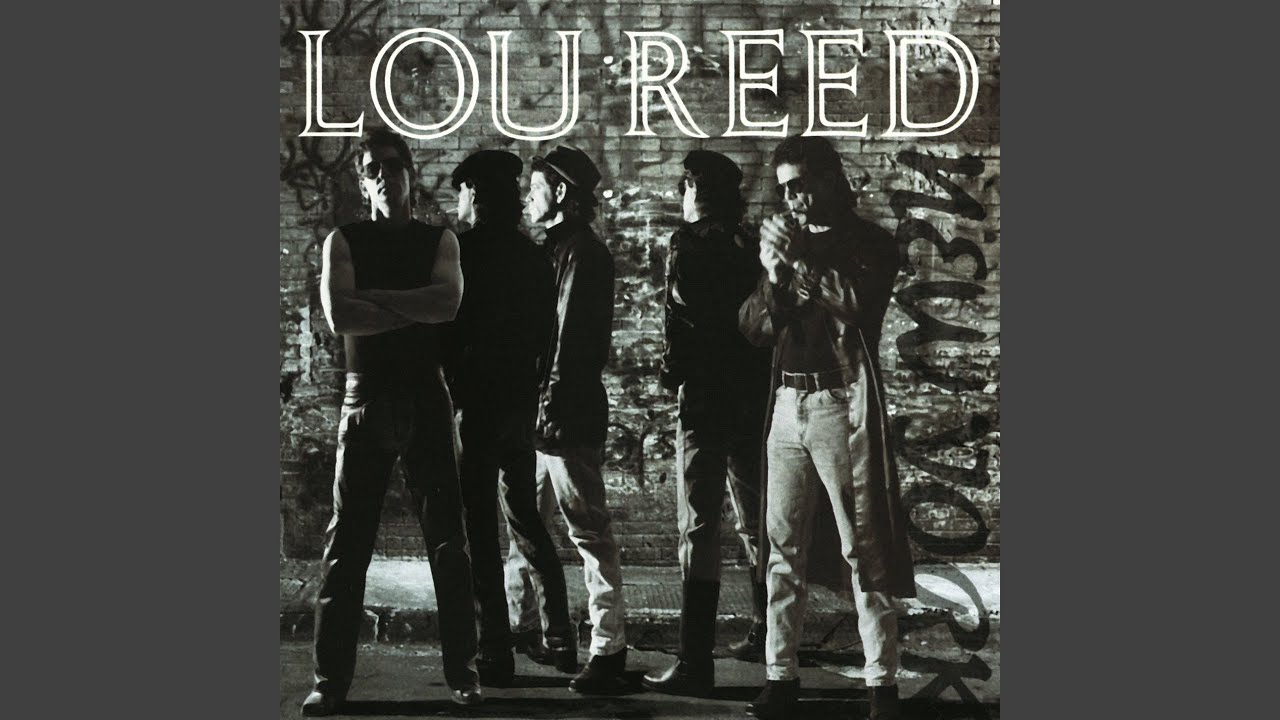俺がルー・リードと『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド』の音楽に初めて接したのは、1984年頃と意外に遅い。勿論ルー・リードとヴェルヴェットの存在は大昔から知ってはいたけど、ラジオとかで良く流れるタイプの音楽ではなく、やはり70年代後半のパンク・ロックブーム辺りから、その「元祖」として名前が上がる様になり、俺も『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ』(67)とルー・リードの『ベルリン』(73)を聴き、遅まきながらルー・リードの存在を強く意識する様になった…という流れだ。
既にルー・リードの伝記はこれまでにも何点か発表されていて、俺もその内の一つを読んだ事がある。あまり細かい事は覚えてないが、ルー・リードがヴェルヴェット・アンダーグラウンドとして音楽シーンに登場するまでの事を中心に綴った物であった様に記憶している。ルー・リードの場合どうしてもヴェルヴェット時代から、ソロアーティストとして『トランスファーマー』(72)収録の『ワイルドサイドを歩け』のヒットが出るまでの頃の逸話に、興味が集中していた部分がありそうだ。
そういう意味では本書は画期的。『ローリング・ストーン』誌に寄稿するライターである著者は、評論家嫌いで知られるルー・リードとは1995年以来深い付き合いがあった。その付き合いあってのルー自に直接訊いたコメントや彼の関係者の証言を基に、ルー・リードの71年の生涯を俯瞰気味に考察、その音楽が生れるに至った経緯を描き出している。
かのボブ・ディランがそうだった様に、ルー・リードもかつてはポップスターに憧れる普通の少年時代を過ごした。だがディランと違っていたのは、彼にはポップスターと共に「文学者」として成功したい強い意志があった事だ。それが当時のロックの概念から逸脱したヴェルヴェット・アンダーグラウンドの結成に至り、ポップ・アートの開拓者であるアンディ―・ウォ―ホルに見い出された事によってごく一部で高い評価を得る様に。
ただルー・リードには「バンドマン」的な発想は無かった。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドはゴタゴタ続きで最終的にはルー・リード自身が脱退。常に自己中心的に音楽を捉え、共動者(『トランスファーマー』をプロデュースしたデヴィッド・ボウイなど)の才能を認めつつも、アルバム制作において彼らの功績を低めに設定したい彼の性質は、94年のヴェルヴェッド・アンダーグラウンド再結成辺りまでまで続いていた事が、本書で確認できる。
これも文学者志向ならではあろうが、そんな裡に籠る彼の性格はオープンとは言えず、その副産物としてルー・リードはロックミュージシャンお決まりのドラッグと酒に溺れる事になり、英国音楽誌の「早死にしそうなミュージシャンランキング」では、キース・リチャーズに次いで第2位にランキング。本人も音楽で生み出されたルー・リード像を演じ続けなければならないというジレンマに陥り、その音楽には更に陰影が付き纏っていく。
著者はルー・リードがそういう人間になった原因として、父が死ぬまで冷却関係だった父子の確執があるのでは…と考察。その一方で母親への関係は良好で、ルー・リードの私生活上のパートナーにも母親的な物を求めていたのでは…と本書を読むと感じた。ルー・リードの最初と2回目の結婚は何れも年下のうら若い娘で、結婚生活は妻が気儘なルー・リードの日常的な世話をする事に終始し、二人の妻との結婚期間の間に同居した「レイチェル」という「女装の男性」もまた同様。パートナーとの間に相互的な愛情関係は育たなかった。
そんな鬱に籠るタイプのルー・リードが、オープンな活動へと変遷していったのは80年代に入ってからだ。南アフリカのアパルトヘイト政策に抗議する曲『サン・シティ』に参加し『ファームエイド』のライヴにも登場。『ヘロイン』みたいな曲を唄っていた者が農民救済を訴えるというのも変な話だが(笑)。そしてアルバム『ニューヨーク』(89)の大ヒット。ノイジーとは無縁な、シンプルなサウンドで歌詞を聴かせる事を一義的にしたこのアルバムのヒットは、文学者志向であるルー・リードを至極満足させたはず。ドラッグや深酒を断ち太極拳を学ぶという健康的な生活の中で、ルー・リードは生涯最後の伴侶となるパフォーマンスアーティスト、ローリー・アンダーソンと出会う。ルー・リードの世話役ではなく、お互い表現者として自立している二人の関係は、いい意味で生活の緊張感をルー・リードにもたらしたと言えるだろう。
ローリー・アンダーソンとの生活は彼の音楽活動にも影響を与え、かつては有り得なかった音楽上のパートナーシップをもたらす事になる。音楽ジャンル的には全く共通項の無いスーパー・メタルバンド『メタリカ』とのコラボレーション(『ルル』)が何のコミニケーション不足も無く無事完了する…なんて事は『メタル・マシン・ミュージック』(75)で評論家の不評を買った時代(日本では湯川れい子が「これは音楽による殺人である」との理由で批評拒否)のルー・リードには考えられなかった。だたその頃には彼の体調は悪化の一歩を辿り、結局2003年11月27日に亡くなっている。
はっきり言って本書の発表は、ルー・リードが存命だったら不可能だったと思う。本書に限らずそう感じられる書籍は米国には多い。真摯にミュージシャンの伝記を書こうとすると、本人にとっては黒歴史となる事実にも目を向けなければならないから。本書も膨大な証言からルー・リードのこれまで表には出てなかった裏の顔みたいな物もくっきりと描き、そういう陰の面もあったからこそ、ルー・リードの素晴らしい音楽が生れたのだと主張して止まないのだ。
個人的にはやはりアンディ・ウォ―ホルとの複雑な確執(ウォーホルは恩人ではあるが音楽方面のプロデュース力に乏しく、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドにニコをヴォーカリストとして加入させるのもアンディの意志で、ルー・リードの本意ではなかった)が興味深いし、パーティーでルー・リードとは水と油な性質の『オールマン・ブラザーズ・バンド』のギタリスト、ディッキー・ベッツと殴り合いになったという記述には、さもありなんと思ったりして。71歳の生涯はリー・リードみたいなタイプのミュージシャンとしては早世なのか長寿なのかは、何とも言えないけど(キーズ・リチャーズは予想に反してまだ生きている)、NYという街が生み出した希有なロック文学者だったとは言える。