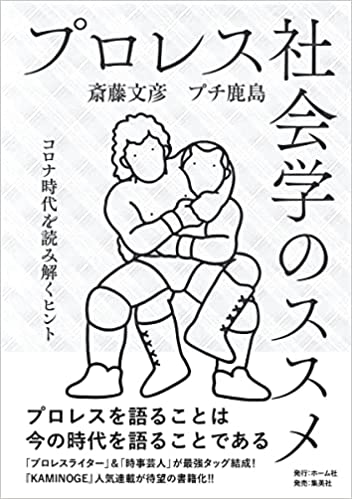「ブック」なるプロレス用語があるのを知ったのは演劇マニアの知人からだ。小劇場の舞台ではプロレスを題材にした物が意外と多かったりするらしく、そこで「ブック」という言葉が使われていたと。要するに試合の勝ち負けを事前に決めた台本みたいな物を顕した用語らしい。
曲がりなりにも半世紀ぐらいプロレスに関する文章を目にしてきた俺だが「ブック」という言葉は初耳だった。でもプロレス関係のウイキとかでは頻繁に使われているし「そういうモンかな」と思って俺も何度か文章で使った事はある。
そんな俺にとって今回読んだ『プロレス社会学のススメ』(斎藤文彦、プチ鹿島著 集英社・刊)は目から鱗が落ちた…とも言うべき本であった。本書の中で斎藤は「『ブック』なんてプロレス用語は存在せず、某プロレスライターが作った造語に過ぎない」と断言している。そうだったのか、道理でアナログ世代の俺には耳慣れなかったはず…。
本書は『KAMINOGE』というプロレス雑誌(前身は『紙のプロレス』。雑誌名は新日本プロレスの道場がある東京都世田谷区の「上野毛」から取っている)に連載された、アメリカンプロレスに造詣が深いプロレスライターの草分け的存在である斎藤文彦と、プロレスマニアで時事ネタ芸人として活動しているプチ鹿島の対談の単行本化だ。対談はわが国で新型コロナウイルス禍が発生した20年3月から始まっており、プロレス団体が新型コロナウイルスの猛威により次々に有観客試合の自粛を強いられた時期に合わせて行われた訳だ。そんな状況下でプロレスの事を語ろうとするとどうしてもマニアックなプロレス談議を交わしつつも現在のプロレスを取り巻く状況、更にはそれに照らし合わせた「社会」について触れざるを得なかった…という事だろう。
斎藤文彦ならではの豊富な知識からもたらされるプロレス裏話や、プロレス界で起きた歴史的な事柄を検証しつつ新たな視点から徹底的に論評するスタイルは、俺の様な昭和のプロレスマニアには格好の餌であり読んで飽きる事など当然なかったのだが、その一方で斎藤は現在のプロレスを取り巻く安直な状況に警句を発し、その在り方が今の社会全体の流れの雛形になっているのではないかと指摘。「ブック」という一ライターが作った造語がネットの世界で定着していくのもその一端ではないかと。
振り返れば90年代までのプロレスは観る側の想像力が加味されて成立する部分が少なからずあったと思う。いくらプロレス好きでも当時行われている試合の全てを観る事は不可能で、俺たちはプロレス雑誌や『東京スポーツ』などの記事を読み、観てもいない試合を想像力を駆使して脳内再現する事でプロレスを愉しんでいたのだ。しかし21世紀になるとネット万能時代へと変化。観ようとすれば往年の名試合を動画などで観る事も容易いかもしれないし、取材記者やプロレスライターでなくとも自分のプロレス観めいた物を発信する事は誰でも可能な時代になった。
しかしその結果「ネットで分かる事が一義的に正しい」という思い込みが生まれ、観る側の想像力が欠如していった部分はあり、事実確認だけで済ましてプロレスを語る輩が多くなっている…という事だろうか。そんな「自由さ故の未熟さ」というのがプロレスの周囲に今溢れており、それがプロレスの歴史に対する誤解や半端な考えを生み出す原因になっている点が指摘されている。
そのプロレスにおける諸問題がそのまま今の社会的状況にもリンクする…と本書は語って止まない。批判的な言葉は「クレーム」として扱われ「誰か」に都合のいい話ばかりが流通し定着化していく流れは、かつての批評精神を失いプロレス団体の広報誌化していったプロレス雑誌と共通している所があるのかもしれない。
そんなネット世代の想像力の欠如がグロテスクな形で表層化してしまったのが「木村花の死」であったと言える。ネットやテレビで映っている物をそのまんま事実と認識する事自体、長年プロレス界の人間臭い出来事や歴史を見てきた俺には考えられない話であったが…。
そんな感じでプロレス界を取りまく現状は良いとはても言い難い訳だけど、本書で話題とされている、かつては米国対イラクの代理戦争をリングでやったりして胡散臭さその物だった『WWE』が率先してリングから差別を撤廃していった流れや、昭和時代まではキワモノとしてしか扱われていなかった女子プロレスが市民権を持つに至った世の趨勢は歓迎すべきであり、斎藤文彦、プチ鹿島の両著者も決して「昔のプロレスは良かった」的モードばかりで語っている訳ではない。プロレスも新型コロナウイルス禍を乗り越えた先に光明が見えてくる可能性が皆無という訳ではないし、ネット時代に合わせいい風に変化していけばそれでいいんだとは思うが…。