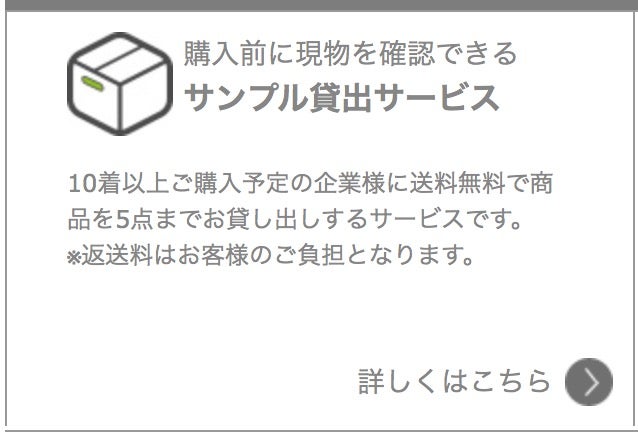昨今、定番となりつつある発熱アンダーウェアですが
そもそも、なぜ発熱するかを皆さんはご存知でしょうか?
メーカーによって違いはあるものの、
「吸湿発熱」と呼ばれるものが大半で、読んで字のごとく
生地が体から出る湿気を吸って発熱する仕組みです。
■「湿気」はどこから来るのか?
実は特に汗をかいていなくても人間は
「不感蒸泄/ふかんじょうせつ」とよばれる
生理現象で常に肌から水蒸気を発しています。
つまり、この「不感蒸泄/ふかんじょうせつ」で発する
水蒸気が発熱のもとになる湿気となるのです。
■なぜ湿気を吸うと発熱するのか?
この吸湿発熱の熱は「凝縮熱(ぎょうしゅくねつ)」と
呼ばれるもので、簡単に言うと「気化熱」の逆バージョン。
気化熱が水が水蒸気になる時に熱を奪うのに対し
凝縮熱は水蒸気が水に変化する時に起こる熱エネルギー。
発熱インナーウェアと呼ばれる物は、この「凝縮熱」を
利用して発熱しているのです。
■どんな繊維でも発熱する?
実はこの「凝縮熱」は湿気を吸うことができる繊維なら
理論上全ての繊維で発生することになります。
ということは、つまり湿気を吸う繊維はみんな
「発熱繊維」と呼べるという訳でどこまでが普通の繊維で
どこからが「発熱繊維」かという明確な基準はありません。
もともと繊維の持つ特性でもある「凝縮熱」を効率的に
引き出してあげられるようにしたものが「発熱素材」と
呼ばれているのが実状です。
■凝縮熱に大きく関わる公定水分率
発熱の元である「凝縮熱」が水蒸気が液体に変化することで
熱を発生させるということは、単純に考えれば湿気を多く
含むことができるほど発熱量が高くなることになります。
そこで気になるのが繊維の公定水分率(水分吸収率)
・ポリエステル 0.4
・アクリル 1.3
・ナイロン 4.5
・コットン 8.0
・レーヨン 13.0
・ウール 16.0
やはり化学繊維のポリエステルやアクリル、ナイロンは
その性質上、水を含むことが苦手なようで水分吸収率も
低めですが、レーヨンやウールは10%を超える高い数値を
示しています。つまりレーヨンやウールは理論上「凝縮熱」を
多く生み出し発熱量が多いということになります。
■発熱量が高いだけでは暖かさは続かない
吸湿量が多ければ凝縮熱が多く発生し、発熱量が高く暖かい。
これ自体は間違いではないのですが、実はこれだけで暖かさは
続きません・・・それどころか寒くなってしまうのです。
というのも湿気を吸い液体に変えるわけですから、吸った水分が
生地にどんどんたまって行くわけで、ためられるうちは発熱しますが
吸収量にも限界があります。ですから、限界値まで達するとそれ以上
湿気を吸うことができなくなり、発熱がストップしてしまいます。
すると逆に今まで吸った湿気が冷えはじめ体の体温を奪う
「ヒートロス」という現象が起こります。
みなさんご存知の靴下が蒸れた時に足先が冷えるアレです。
■夏衣類でおなじみの「吸汗速乾」機能がジレンマを解決
発熱するために湿気はたくさん吸いたいけど蒸れてしまっては逆効果。
でも湿気を吸わないと発熱できない・・・・。そんなジレンマを解決したのは
実は夏の衣料で定番となった「吸汗速乾(きゅうかんそっかん)」機能。
今では「ドライ機能」と言った方が馴染みがあるかもしれません。
体に触れる側ではより多くの湿気を吸い上げ、それを毛細管現象を
利用して素早く生地表面に移動、拡散し効率よく乾かす技術です。
もともと夏衣料のために開発されたこの技術を冬に着用する
防寒インナーに応用し、効率よく吸った湿気を逃がしてやることで
従来より長時間の発熱を可能としたのです。
現在市場には様々なメーカーから数えきれない種類の防寒インナー・
アンダーウェアが発売されていますが、自分の着用環境に合うのは
どのアイテムなのか?また、発熱性の高いものは何を選べば良いのか?
そんな悩みを持っている方がこのブログ記事を参考にしていただければ幸いです。
企業様向けにサンプル商品の貸出も行っております。ぜひご利用下さい。