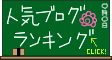とあるお宅の裏庭に、
可愛らしいネコちゃんがいました。
その時の写真をパチリ。
ネコちゃんはどこにいるでしょう?
答えは
一番最後にお伝えします。
ブルーベリー狩りに行って、
採ったブルーベリー1750g。
そのうちの4分の1を、
ジャムにしましたが、あっという間になくなりまして、
また作りました。
今回は、多めに作ったつもりでしたが、
やっぱり2瓶にしかなりませんでした。
ブルーベリー狩り
採ったブルーベリー1750gと入場料で3750円
高いの?安いの?
メルカリで買ったら安いかなと思いましたが、
結構なお値段でした。
600g 1900円とか。
送料も含まれるし、摘むのも重労働ですから
仕方ないと思いますが。
で、目線を変えて
ブルーベリーの若木
2本で555円。
買ってみました。
育てばいいですけれど。
大きくしてしまうと、
2.5mくらいになってしまうのだそうなので、
コンテナで育ててみようと思います。
家の東側で。
あそこなら、
鳥よけのネットが張れるようになっています。
あー苗木が届くのが楽しみです。![]()
しつこく、点字のお話です。
市内に住む視覚障害者の方が、
新潟大学で点字について
研究されている教授と
お知り合いだそうで、
その教授が
これを送ってくれたそうです。
紙でもプラスチックでもない、金属でもない
布?のようなものに打った点字。
触ったときに指にやさしい感触です。
![]()
これは、室内の案内板ですが、
![]()
これは、ウクライナの地図です
これを研究室の大学生が
作ったそうです。
視覚障害者の方が
点字を触る時の手にはどんな感触が残るのか
考えようとも思いませんでした。
理解しようとも思いませんでした。
触感を改善してくれたのですね。
このような配慮ができるって
素晴らしいことだと思いませんか?
障害者のために
「合理的配慮」って言葉があるのを
ご存じですか?
障害者が希望すれば、
その施設の職員は、その希望に合うように
個別に対応しなければならない。
このことを、
内閣府のHPやパンフレットで、
例を1つ1つあげています。
例えば、車いすで移動している人が、
施設の段差が乗り越えられなければ、
その施設の職員は、
車いすを抱え上げて段差を移動する介助を
提供しなくてはならないということです。
でも、そのベーシックには
その施設が負担にならない範囲で
バリアフリー化とか
ユニバーサルデザインの導入することが
必要になります。
つまり、「合理的配慮」には、
バリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入が
基本になるわけです。
この合理的配慮の提供は、以前は民間業者は努力義務で、
公官庁は法的義務でした。
昨年の5月に民間業者も法的義務となりました。
移行には3年あり、2年後には、
民間業者もこの合理的配慮を
しなくてはならないわけです。
店の入り口が階段であれば、
スロープを設置するとか、
車いすを持ち上げられる
人員を確保するとか
ですね。
そのことは、新聞報道でも、ネットでも
しっかり書かれています。
大学で社会福祉学を学んだ私は、
高校の科目福祉の教員免許を取得し、
今年の春まで、
高校の介護福祉科で、
非常勤講師をしておりました。
その学校の福祉科の教科主任の教諭が、
「合理的配慮は障害者から申し出があって行うことだ」
と言ったのですよ。
しかも、私に、
「片道先生は、合理的配慮を
ユニバーサルデザインやバリアフリーと混同している」
「中央法規出版の教科書に、
申し出があったときって書いてある」
「内閣府のパンフレットにもそう書いてある」って
興奮して言い切ったのですよ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
でもね、普通に考えたって
そういう考え方には到達しないでしょう。
あなたは、困っている障害者がいて、
その障害者が何も言わなければ
見て見ぬふりをするのですか?
申し出がなければ、障害者が困っていても
知らんぷりするのですか?
挙句の果てに学校の、
正面玄関にあるスロープは、
障害者のための設置ではなく、
使いたい人のためのもので、
障害者用の多目的トイレには
常時鍵がかかっていて使えないようにしていて
この学校には合理的配慮はないって
その理由はこの学校には、
障害者は入学しないからって
あー言っちゃった。
バリバリ差別してますよ。
私、内閣府に電話で確認しました。
内閣府の応対してくれた方が、
「正しいです。
そこまで教えて下さってありがとうございます。
自信をもって教えて下さい。」って
おっしゃってくださったのです。
余りにも無知なので、
彼女の机の上に、
合理的配慮の資料を置いて
「参考にして下さい」
ってメモ書きまでしたのに、
「ありがとう」も「すみませんでした」も
ありませんでした。
高校の福祉科は、一般教養を学びながら、
介護福祉士国家試験の科目を学ばなければならないので、
速成、知識の詰め込み式になってしまいます。
だから、教科書に書いてあることだけ丸暗記。
できたのは、がちがちの石頭。
同じ時期、非常勤講師をしていた元介護福祉士の方が、
「介護福祉士は、柔軟な頭をもっていないと
だめなんですよ」と言って
定期テストの一番下に、
ちょっとした
頭の体操的な問題を
出題しておりました。
でもね、すっかり、
3年間の高校生活で、
教科書棒読みの教諭に
しっかりインプリンティングされています。
私は高校に福祉科が創設され、
ヘルパー資格を取得し始めた20年くらい前から、
それは、むちゃだと
思っていました。
命や生活の質に携わる介護福祉士は、
もっと、深く、時間をかけて
専門のことを学ぶ必要があると
思っていました。
高校卒業と同時に介護福祉士の資格を取得し、
現場で働くには
未熟すぎるのではないかと。
ずっとずっと思ってました。
教育の現場に実際に就いて
それを確信しました。
「ぼけますからよろしくお願いします」
というドキュメンタリー映画で、
ヘルパーさんが実際に活動しているシーンがでてきます。
興奮する認知症のお母さまに、上手に接して
興奮を収めていらっしゃいました。
作った煮物は、料理上手なおかあさんに、
負けない美味しさだったそうです。
誰でも初めは新人ですが、
やっぱり、家事援助や声かけ等は
熟練の差がでてしまいます。
新潟大学で
視覚障害の手の感触まで配慮した
点字の地図作成は、
障害者の社会進出が遅れている
日本に共生社会へと成長していく
道しるべになるでしょう。
柔らか頭を持ちましょう。
追記:この私が3月まで勤めていた学校、
障害者用のスロープはあっても、
障害者用の駐車場はありませんでした。
事務長が、
「高校に、障害者用駐車場を
設置している学校は少ないです」って
言ったのですよ。
はぁ?![]()
私が知っている高校は、
全て障害者用駐車場がありました。
そんなに設置していない学校が多いなら、
こりゃ問題ですよ。
県知事、県知事。
認知度最下位を気にしている場合じゃ
無いですよ。
共生社会をつくり上げることに対して
県職員の認知度が
低く過ぎますよ。
障害者用駐車場の設置は
一番お金がかからないでできる配慮だと
私は思いますが、、、。
同じように避難所に指定されている
市立の小中学校は、
体育館の入り口の
スロープの設置は当たり前。
今は、改築するときは、
エレベータ―を設置するよう
進めています。
市立と県立に大きな差ができています。
冒頭のクイズの答えは?
まるで保護色みたいでしょ。
よろしければぽちっとお願いしまする。