今日は寒かったですね。
長野県では雪が降ってた所もあるらしく、
冬に逆戻りとか勘弁してほしいなと感じました。
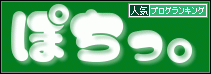
↑↑応援お願いします↑↑

↑↑応援お願いします↑↑
さて、昨日の記事ですが思ったより反応があり嬉しい限りです。
その記事はこちら↓↓
「糖度10%って本当に甘いの?」実は知らない糖度の話。
その反面、読んだ方に誤解を招く様な言い回しがありました。
なので補足と言う形で再度説明をさせていただきます。
ご指摘をくださった方ありがとうございます。
糖度=濃度
と言いました。
糖度=甘さ
でもあります。
例えば糖度8%のトマト。
たぶん甘いんだろうなと言う印象を受けるでしょう。
ただ甘い糖度8%のトマト
少し酸味がある糖度8%のトマト
さてどちらが甘く感じるでしょうか?
同じ糖度8%のトマトなのに、感じる甘さは違います。
もう少し違う観点からお話します。
糖度18%のメロン果汁
糖度18%の砂糖水
さてどちらが甘いでしょうか?
原理的に言うと同じです。
糖度計は液体の中を通る光の屈折率を利用してを計っています。
屈折率が大きくなれば、濃度が上がります。
という事は
どちらも濃度が同じなので一緒ですが
中に溶けている成分は異なりますよね。
なので
「糖度18%のメロン果汁」
と
「糖度18%の砂糖水」
の甘さが同じとは限らない。
という事です。
そしてメロンの事でもう一つ。
発酵したメロンが食味があまりよくないけれど
糖度が高いって事も一例です。
と言う表現を昨日しました。
大分言葉が足りていませんでした。
これは、メロンが追熟する過程で可溶性固形物の量が増えて糖度が上がるって事です。
糖度が上がったから食味まで上がった言い切れない。
基本的には
「糖度」と「美味しさ」は比例します。
糖度が上がれば、おいしくなる。
ただそれが絶対ではないという事が言いたかったんですね。
メロンの例だけでなく
果物や野菜は追熟すると糖度が上がります。
しかしトマト果汁に塩を数グラム入れても糖度は上がる。
果汁の中の可溶性固形物が増えて濃度が上がったから。
糖度=濃度=甘さ
それは絶対的なおいしさではないという事。
目で見て判断出来ない野菜のおいしさ。
それを示す指標として使われているものです。
高いに越したことはありません。
でも糖度と言う概念を知らず
糖度が高い=おいしくて甘い
になっていると、予想していた味と違った場合クレームの原因になりかねない。
だから生産者を責めるのではなく、
消費者も少しは知識を持ちましょうという事が言いたかったんです。
という事で補足をしましたが
いかがでしょうか?
これはどちらか一方の偏った目線から意見をした訳ではありません。
消費者が知らない事が現にあります。
もちろん生産者が知らない消費者の声もあります。
実際、糖度がこういう物だと知らない人は世の中にたくさんいる。
それは糖度の事に限らず、農産物や農業の事に関してもそうです。
「生産者」
と
「消費者」
の間に考えのズレがあるんですね。
このズレが今100あるとしたら
それを今後0に近づくようにしていくのが双方のためになります。
そして丸山のような活動をする人が増えていくことを望みます。
そういう人を知っていたら紹介してください。
私もそういう活動してますと言う人がいたら
ぜひ一緒にそのギャップを埋めていきましょう。
消費者側の人の意見ももちろん欲しいです。
こういう事が浸透していくともっとお互いが納得して
「お金」と「農産物」の交換を出来るのではないでしょうか。
少し専門的な事や、
言い回しが固いところもありましたが
少しでもあなたの知識と今後の参考になると良いです。
では、なんにか意見やメッセージがある方はどうぞ♪
メッセージはこちらから
随時募集中です。
読者登録はこちら