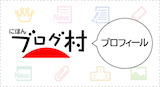宝塚歌劇で山田風太郎著「柳生忍法帖」を上演すると知ったとき、柳生十兵衛は隻眼なので遠近感がつかみにくく殺陣が難しいのでは?と思いました。
こっちゃん(礼真琴さん)の立ち廻りは、それを全く杞憂だと感じさせるぐらい鮮やかでした。
 数ある山風作品の中で、大野拓史先生は「柳生忍法帖」を何故選んだのか
数ある山風作品の中で、大野拓史先生は「柳生忍法帖」を何故選んだのか
まずは、会津七本槍と呼ばれる剣豪、堀一族の娘たちと、男役と娘役に役が多いということでしょうか。
会津七本槍では、瀬央ゆりやさんが演じた漆戸虹七郎と、極美慎くんの香炉銀四郎は、美しい凄腕の剣士です。また、娘たちの窮地を、柳生十兵衛が救うという設定が宝塚にマッチしたのだと思います。
 会津七本槍とは
会津七本槍とは
会津藩初代藩主 加藤嘉明が、賤ケ岳の戦い(羽柴秀吉と柴田勝家が、現滋賀県長浜市賤ケ岳村で戦い、秀吉が勝利して天下人となった)で武勇を馳せた賤ケ岳七本槍の一人であることから、山風先生が命名。
加藤明成は嘉明の子で2代藩主。
 会津七本槍 登場順(敬称略)
会津七本槍 登場順(敬称略)
平賀孫兵衛(天華えま):黒豹のような精悍さを持つ長槍の名手。
大道寺鉄斎(碧海さりお):くさり鎌を投げて相手を倒す白髪の達人。
具足丈之進(漣レイラ): 3匹の猛犬を手足のように操る(原作ではこの猛犬たちがいい仕事してます)。
司馬一眼房(ひろ香祐):右眼だけが開き、変幻自在に皮鞭を操る。
鷲ノ巣廉助(綺城ひか理):大男で怪力、原作では女二人を振り分け荷物のように担いで移動できる。
香炉銀四郎(極美慎):前髪のある美少年で顔の中央に凄惨な傷(原作では女の髪で編んだ鋼のような霞網を投げて相手を捉える)。
漆戸虹七郎(瀬央ゆりあ):会津七本槍の中心的人物で会津藩一の剣の使い手(原作では片腕で過去の戦歴が偲ばれる)。
 原作にはない設定
原作にはない設定
おゆらと漆戸虹七郎の過去の関係が語られることがサイドストーリーとして面白いと思いました。
「柳生忍法帖」、宝塚大劇場公演を経て、どのように深化しているかとても楽しみです。