この人との書く物語は変化球と見せかけて、ストレートだ。それも「ど」のつく、馬鹿正直な。
表題作「ナイフ」を含む5作からなる短中編からなる物語は小学生中学生を題材とし、何にも考えていないようで考えているし、考えているようで考えていない彼らにスポットを当てている。
今となっては記憶を探るしかないあの時代。読んでいると、記憶の中の自分ではなくて、物語の中の自分を見つめている事に気がつく。
その根底にあるものは、恐らく、郷愁に近い感情ではないだろうか。
ある家族のある時を切り取って、円満な解決が訪れる訳でもなく、割り切れず、曖昧なまま物語は終わる。
その曖昧さを許容しなければならない状況こそが家族を作るのかもしれない。
頭の隅にモデルとなる家族像があって、そこからはみ出してしまう現実に当事者たちは戸惑い行動する。
その行動は家族であるからこそ起こる苦悩であり、逃れるという選択肢はない。
その事で誰も成長しないし、分かり合えもしない、けれど、その苦悩を超えていかなければならない。
殆ど一過性であるそれらの事柄は見えていなかった日常であり、妻から子供から妹から直視せざるを得ない状況を強いられるだけだ。
自身の子供時代をそんなに細かい状況を記憶からほじくり返せる訳ではないが、そこにあった、音とか匂いとか感触だとかがよみがえる。
これらの物語が遠慮なしに触れてくる読み手の琴線は歪ながらも音楽になる。
その音色こそがこの本の感想という事になる。
つまり、どの世代が読んでも何らかの反応を起こさせる。
だから、きっとこの作者は多作なのだろう。
誰しもがもつ、日常にある「普通」という感覚から漏れる事柄は「普通」な事よりも絶対的に多いのだから。
iPhoneからの投稿ナイフ (新潮文庫)/重松 清
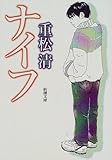
¥620
Amazon.co.jp
表題作「ナイフ」を含む5作からなる短中編からなる物語は小学生中学生を題材とし、何にも考えていないようで考えているし、考えているようで考えていない彼らにスポットを当てている。
今となっては記憶を探るしかないあの時代。読んでいると、記憶の中の自分ではなくて、物語の中の自分を見つめている事に気がつく。
その根底にあるものは、恐らく、郷愁に近い感情ではないだろうか。
ある家族のある時を切り取って、円満な解決が訪れる訳でもなく、割り切れず、曖昧なまま物語は終わる。
その曖昧さを許容しなければならない状況こそが家族を作るのかもしれない。
頭の隅にモデルとなる家族像があって、そこからはみ出してしまう現実に当事者たちは戸惑い行動する。
その行動は家族であるからこそ起こる苦悩であり、逃れるという選択肢はない。
その事で誰も成長しないし、分かり合えもしない、けれど、その苦悩を超えていかなければならない。
殆ど一過性であるそれらの事柄は見えていなかった日常であり、妻から子供から妹から直視せざるを得ない状況を強いられるだけだ。
自身の子供時代をそんなに細かい状況を記憶からほじくり返せる訳ではないが、そこにあった、音とか匂いとか感触だとかがよみがえる。
これらの物語が遠慮なしに触れてくる読み手の琴線は歪ながらも音楽になる。
その音色こそがこの本の感想という事になる。
つまり、どの世代が読んでも何らかの反応を起こさせる。
だから、きっとこの作者は多作なのだろう。
誰しもがもつ、日常にある「普通」という感覚から漏れる事柄は「普通」な事よりも絶対的に多いのだから。
iPhoneからの投稿ナイフ (新潮文庫)/重松 清
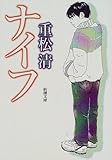
¥620
Amazon.co.jp