読んでいて気持ちの良い小説ではありませんでした。
主人公と主人公に影響を及ぼす人物がいて、
主人公はある意味普通に暮らしていこうとするところに、
その人物が出てきて、
口車に乗せてしまう。
読んでいると、
そろそろ出てきそうだな
出てこないでほしいな、とか。
これは嘘だろうとか、
気付かないなんてバカなんじゃないかとか。
主人公に少しでも肩入れしてしまうと
それをことごとく裏切られてしまう。
だから、段々と主人公が好きになれなくなっていく。
そして、ことごとく出てくる人物も
生理的に受け付けなくなってくる。
けれど、この先『殺意』はどこへ行くのか
が気になった。
『白夜行』『幻夜』に通じるところが
あるけれど、行為の純度を薄めたような
ものとしても捉えられる。
それには主人公のキャラクターが
その門の前で躊躇するからだろう。
その上、積極的にくぐろうとしているわけではない。
それはつまり、
『普通の人』と言う事になりはしないだろうか。
誰もが殺意の一つや二つ抱いた事はあるだろう。
いや、もちろんない人も多いだろうが。
その殺意の継続と言うのは思いのほか
短い。
その瞬間、沸き立っても、
タイミングとかほんのちょっとのズレで
我にかえってしまう。
だから、そうそう殺人は起こらない。
主人公はそういった心の葛藤を
あまり見せない。
同じような事で同じような殺意を抱き、
同じようにその意欲をそがれていく。
都合良く現れるその人物はそれを見越している。
彼は彼なりに命を張っているのだろう。
けれど、主人公は自らの命を張らない。
それはその行為にそれほどの価値を
置いていないからだろう。
だから、彼は『普通の人』であり、
殺人の門に魅力を感じているのだろう。
表からその門をみると内側が気になる。
けれど、その門をたたいても内側は
推し量れない。
人を殺した者だけがその門をくぐる事が出来る。
普通の人はくぐらない。
魅力を感じていても
くぐる為の行為が追い付かない。
愚鈍とも言える主人公の行為に
苛立ちを感じさせる事がこの小説の目的だとしたら
それは大成功といえるだろう。
はじめに他の小説を薄めたような、と書いたが、
それは当然そうあるべき小説だっただろう。
東野圭吾論などと言うものは持ちわせていないけれど、
思い付きを言葉にするなら、
『普通の人』を浮き彫りにしたいのではないだろうか。
誰だって殺意は抱く
けれど、
行う人は一握りにも満たない。
それはどうしてだろうと考え、
今回の主人公が生まれた。
『さまよう刃』ほど動機がはっきりとしているわけでもなく、
可もなく不可もない人生に憤りに近い不満を感じるわけでもない。
そんな人物が殺人に至るまで、
至るかどうかを
書いてみた。
そんな物語なのだろう。
だから、私から見た主人公は
右往左往している。
一応ミステリー形式だったらしく
最後にある事実が開示されるが、
それほどのことでもなかった。
嘘はつかない方が良いとは言うが、
真実だけを目にしなければならない現実
ならばもっと殺人は起きているだろう。
だから、私たちは嘘に守られている。
けれど、そんな一側面だけで、
社会を人生を割り切れる程、
人間と言うのは簡単ではないだろう。
だから、私は殺人の門をくぐらなくて済んだのだ。
殺人の門 (角川文庫)/東野 圭吾
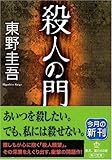
¥780
Amazon.co.jp
主人公と主人公に影響を及ぼす人物がいて、
主人公はある意味普通に暮らしていこうとするところに、
その人物が出てきて、
口車に乗せてしまう。
読んでいると、
そろそろ出てきそうだな
出てこないでほしいな、とか。
これは嘘だろうとか、
気付かないなんてバカなんじゃないかとか。
主人公に少しでも肩入れしてしまうと
それをことごとく裏切られてしまう。
だから、段々と主人公が好きになれなくなっていく。
そして、ことごとく出てくる人物も
生理的に受け付けなくなってくる。
けれど、この先『殺意』はどこへ行くのか
が気になった。
『白夜行』『幻夜』に通じるところが
あるけれど、行為の純度を薄めたような
ものとしても捉えられる。
それには主人公のキャラクターが
その門の前で躊躇するからだろう。
その上、積極的にくぐろうとしているわけではない。
それはつまり、
『普通の人』と言う事になりはしないだろうか。
誰もが殺意の一つや二つ抱いた事はあるだろう。
いや、もちろんない人も多いだろうが。
その殺意の継続と言うのは思いのほか
短い。
その瞬間、沸き立っても、
タイミングとかほんのちょっとのズレで
我にかえってしまう。
だから、そうそう殺人は起こらない。
主人公はそういった心の葛藤を
あまり見せない。
同じような事で同じような殺意を抱き、
同じようにその意欲をそがれていく。
都合良く現れるその人物はそれを見越している。
彼は彼なりに命を張っているのだろう。
けれど、主人公は自らの命を張らない。
それはその行為にそれほどの価値を
置いていないからだろう。
だから、彼は『普通の人』であり、
殺人の門に魅力を感じているのだろう。
表からその門をみると内側が気になる。
けれど、その門をたたいても内側は
推し量れない。
人を殺した者だけがその門をくぐる事が出来る。
普通の人はくぐらない。
魅力を感じていても
くぐる為の行為が追い付かない。
愚鈍とも言える主人公の行為に
苛立ちを感じさせる事がこの小説の目的だとしたら
それは大成功といえるだろう。
はじめに他の小説を薄めたような、と書いたが、
それは当然そうあるべき小説だっただろう。
東野圭吾論などと言うものは持ちわせていないけれど、
思い付きを言葉にするなら、
『普通の人』を浮き彫りにしたいのではないだろうか。
誰だって殺意は抱く
けれど、
行う人は一握りにも満たない。
それはどうしてだろうと考え、
今回の主人公が生まれた。
『さまよう刃』ほど動機がはっきりとしているわけでもなく、
可もなく不可もない人生に憤りに近い不満を感じるわけでもない。
そんな人物が殺人に至るまで、
至るかどうかを
書いてみた。
そんな物語なのだろう。
だから、私から見た主人公は
右往左往している。
一応ミステリー形式だったらしく
最後にある事実が開示されるが、
それほどのことでもなかった。
嘘はつかない方が良いとは言うが、
真実だけを目にしなければならない現実
ならばもっと殺人は起きているだろう。
だから、私たちは嘘に守られている。
けれど、そんな一側面だけで、
社会を人生を割り切れる程、
人間と言うのは簡単ではないだろう。
だから、私は殺人の門をくぐらなくて済んだのだ。
殺人の門 (角川文庫)/東野 圭吾
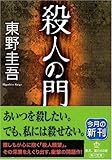
¥780
Amazon.co.jp