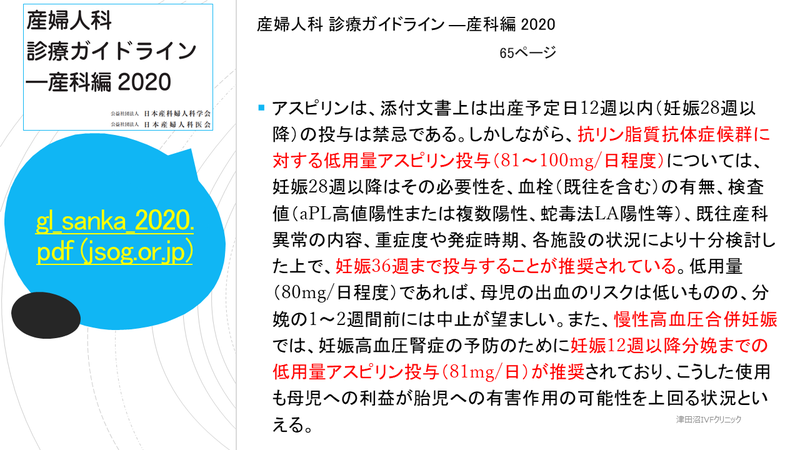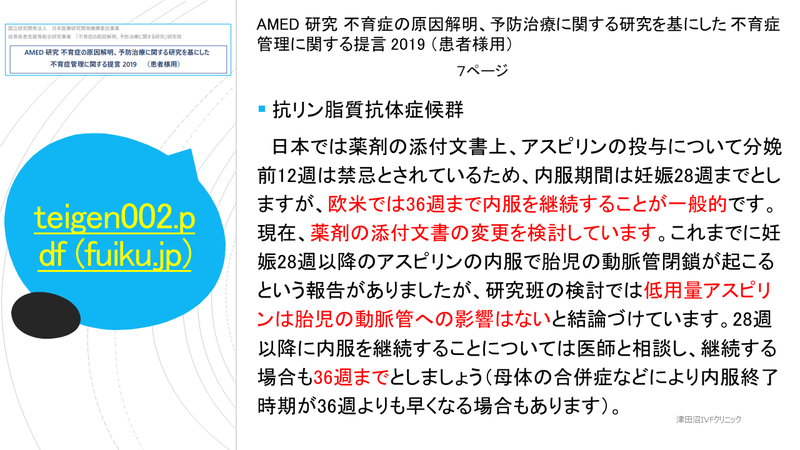妊娠中の低用量アスピリンは、いつまで飲めるの?
アスピリンの添付文書
出産予定日12週以内の妊婦
投与しないこと。妊娠期間の延長、動脈管の早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加につながるおそれがある。海外での大規模な疫学調査では、妊娠中のアスピリン服用と先天異常児出産の因果関係は否定的であるが、長期連用した場合は、母体の貧血、産前産後の出血、分娩時間の延長、難産、死産、新生児の体重減少・死亡などの危険が高くなるおそれを否定できないとの報告がある。また、ヒトで妊娠末期に投与された患者及びその新生児に出血異常があらわれたとの報告がある。さらに、妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い胎児の動脈管収縮が報告されている。
妊婦(ただし、出産予定日12週以内の妊婦は除く)又は妊娠している可能性のある女性
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。動物実験(ラット)で催奇形性作用があらわれたとの報告がある。妊娠期間の延長、過期産につながるおそれがある。
産婦人科 診療ガイドライン ―産科編 2020 65ページ
gl_sanka_2020.pdf (jsog.or.jp)
アスピリンは、添付文書上は出産予定日12週以内(妊娠28週以降)の投与は禁忌である。しかしながら、抗リン脂質抗体症候群に対する低用量アスピリン投与(81~100mg/日程度)については、妊娠28週以降はその必要性を、血栓(既往を含む)の有無、検査値(aPL高値陽性または複数陽性、蛇毒法LA陽性等)、既往産科異常の内容、重症度や発症時期、各施設の状況により十分検討した上で、妊娠36週まで投与することが推奨されている。低用量(80mg/日程度)であれば、母児の出血のリスクは低いものの、分娩の1~2週間前には中止が望ましい。また、慢性高血圧合併妊娠では、妊娠高血圧腎症の予防のために妊娠12週以降分娩までの低用量アスピリン投与(81mg/日)が推奨されており、こうした使用も母児への利益が胎児への有害作用の可能性を上回る状況といえる。
産婦人科 診療ガイドライン ―産科編 2020 174ページ
gl_sanka_2020.pdf (jsog.or.jp)
2013年にACOG(米国産科婦人科学会)は早発型妊娠高血圧腎症で34週以前に早産になった症例あるいは妊娠高血圧腎症既往症例に対して再発予防目的での妊娠初期からの低用量アスピリン服用(妊娠初期から60~80mg/日)を推奨し、2014年にUSPSTF(米国予防医学作業部会)も同目的で低用量アスピリン服用(妊娠12週から81mg/日)を推奨した。産婦人科診療ガイドライン産科編2017でも、妊娠高血圧腎症の再発リスクが高い女性に対して次回妊娠中の低用量アスピリン服用を考慮するとした。海外では低用量アスピリン服用の適応が拡大され、2018年、ACOGは妊娠高血圧症候群発症の高リスク因子(妊娠高血圧腎症既往、多胎、高血圧、糖尿病、腎疾患、自己免疫疾患)をひとつ以上有する患者に対して低用量アスピリン服用(妊娠12~28週から分娩まで81mg/日)を推奨し、中リスク因子(妊娠高血圧腎症家族歴、BMI30以上の肥満、FGR分娩歴、人種と低所得教育層、10年以上空いての妊娠)をひとつ以上有する患者に対して低用量アスピリン服用を考慮するとした。WHO(世界保健機関)(妊娠20週以前から75mg/日)、ISSHP(世界妊娠高血圧学会)(妊娠16週以前から分娩まで75~162mg/日)、NICE(英国保健医療研究所)(妊娠12週から分娩まで75~150mg/日)ともにリスク因子に違いはあるものの同様内容の推奨を行っている。一方、わが国における低用量アスピリンは、出産予定日12週以内(妊娠28週以降)は使用禁忌であり、妊娠高血圧腎症予防としての保険適用もない。したがって、低用量アスピリン使用に際しては、適応外使用であること等を患者に説明し同意を得た上で処方することが重要となる。
抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン 27ページ
20190204143451-4B2EBC6C57C8F0010F436B277CEE05A90F1E4FB27B40462C30694A4C9A9B9D1C.pdf (kenkyuukai.jp)
アスピリンの投与
低用量(81〜100 mg/日)を妊娠前ないし妊娠後可及的早期より投与する。なお、研究班の症例解析で低用量アスピリン(LDA)+未分画ヘパリン(UFH)治療群において、妊娠前からのLDA投与で34週未満早産のリスクが下がった。
解説は次のとおり。海外では妊娠全期間を通して投与が行われていることが多いが、わが国では妊娠28週以降の使用は禁忌となっている。わが国の妊娠と薬データ ベースの情報をまとめると、LDA投与に関してはほぼ安全であると考えられるが、分娩の1〜2週間前には出血傾向の問題を回避するために中止することが望ましいと される。LDA使用妊婦の帝王切開の麻酔方針は医療施設ごとで異なることが予想さ れるため、妊娠後期まで投与を続けた場合の終了時期については各施設の状況によって判断される。LDA投与の終了時期の目安を妊娠28〜36週とするが,28週以降の継続はその必要性を十分に検討したうえで、患者の同意を得て行う。海外では、LDAによる奇形の明らかな増加はないと報告されている。
不育症管理に関する提言2021 20ページ
抗リン脂質抗体症候群
アスピリンは妊娠前からの投与が望ましい。ESHRE(欧州生殖医学会) Early Pregnancy Guideline Development Group (2017)においても、アスピリンの投与は妊娠前からの投与を勧めている。投与期間は添付文書では分娩前12週の投与は禁忌となっているため、妊娠27週末までとするが、欧米では妊娠後期にも継続投与することが一般的である。必要と判断すれば患者の同意を得て継続し、妊娠36週前後を終了の目安とする。産婦人科診療ガイドラインでは、妊娠28週以降はその必要性を血栓の有無、検査値、既往産科異常の内容、重症度や発症時期、各施設の状況により十分検討した上で、妊娠36週まで投与する事が推奨されている。アスピリンの終了時期については産科麻酔に関わる問題(麻酔合併症の問題から腰椎麻酔、硬膜外麻酔がアスピリン内服下ないし終了直後は実施できない施設もある)、分娩時の出血傾向に配慮し、各施設および個々の患者の状況により判断する。
AMED 研究 不育症の原因解明、予防治療に関する研究を基にした 不育症管理に関する提言 2019 (患者様用) 7ページ
抗リン脂質抗体症候群
日本では薬剤の添付文書上、アスピリンの投与について分娩前12週は禁忌とされているため、内服期間は妊娠28週までとしますが、欧米では36週まで内服を継続することが一般的です。現在、薬剤の添付文書の変更を検討しています。これまでに妊娠28週以降のアスピリンの内服で胎児の動脈管閉鎖が起こるという報告がありましたが、研究班の検討では低用量アスピリンは胎児の動脈管への影響はないと結論づけています。28週以降に内服を継続することについては医師と相談し、継続する場合も36週までとしましょう(母体の合併症などにより内服終了時期が36週よりも早くなる場合もあります)。
早発性子癇前症の高リスク妊娠におけるアスピリンとプラセボの比較
Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia | NEJM
背景:子癇前症は、母体および周産期の死亡や合併症の重要な原因となっています。妊娠中に低用量アスピリンを摂取することで、子癇前症のリスクが減少するかどうかは不明です。
研究方法:この多施設共同二重盲検プラセボ対照試験では、妊娠11~14週から妊娠36週まで、子癇前症のリスクが高い単胎妊娠の女性1776例を、1日当たり150 mgのアスピリンまたはプラセボの投与を受けるように無作為に割り付けました.主要な成果は、妊娠37週以前の子癇前症による分娩としました。
結果:合計152名の女性が試験中に同意を撤回し、4名が追跡調査不能となり、アスピリン群に798名、プラセボ群に822名が残りました。早発の子癇前症は、アスピリン群では13名(1.6%)に発生したのに対し、プラセボ群では35名(4.3%)に発生しました(アスピリン群のオッズ比0.38、95%信頼区間0.20~0.74、P=0.004)。結果は、退会者や追跡調査不能者を考慮した感度分析でも重要な変化はありませんでした。服薬遵守は良好で、79.9%の参加者が必要な錠数の85%以上を摂取したと報告されました。新生児期の有害事象およびその他の有害事象の発生率には、グループ間で有意な差は認めませんでした。
結論:早発の子癇前症のリスクが高い女性に低用量アスピリンを投与したところ、この診断の発生率はプラセボよりも低くなりました。
早期発症の子癇前症の予測と予防:妊娠第一期スクリーニング後のアスピリンの影響
目的:スクリーニングと低用量アスピリンによる治療の組み合わせが、早期発症の子癇前症(PE)の有病率に及ぼす影響を検討します。
方法:本研究は、早期子癇前症のスクリーニングを受けた女性の2つの連続したコホートのレトロスペクティブ分析です。最初のコホートは、妊娠11~13+6週目にPEをスクリーニングするために開発されたアルゴリズムが、我々の集団に適用できるかどうかを判断するために観察されました。2番目のコホートの高リスク女性は、自分のリスクについてアドバイスを受け、妊娠34週までアスピリン(夜間150mg)を服用するよう助言し、スクリーニング後すぐに治療を開始しました。早期PEの有病率と、PEの女性が妊娠34~37週で出産する割合を両コホート間で比較しました。
結果:観察コホートと介入コホートでは、それぞれ3066人と2717人の女性がスクリーニングを受けました。観察コホートでは12例(0.4%)、介入コホートでは1例(0.04%)の早期PEが発生しました(P<0.01)。37週以前に出産したPEの全女性のうち、観察コホートでは25例(0.83%)、介入コホートでは10例(0.37%)でした(P = 0.03)。
結論:早期PEの第一期スクリーニングと高リスク群へのアスピリンの処方は、早期PEの有病率を減少させるのに有効であると思われます。
結局、妊娠中の低用量アスピリンは、いつまで飲めるの?
36週までが一般的です。
アスピリンを妊娠36週まで使用することの安全性は、すでに国際的に確立しています。27週で使用を終了する医学的根拠はありません。
妊娠28週以降の使用を禁忌としているのは、日本のみです。胎児動脈管閉鎖、催奇形性、胎盤早期剥離、胎児脳室内出血、腹壁破裂などのリスク増加は否定されています。
アスピリンの薬剤添付文書の改訂が、専門医集団から求められています。