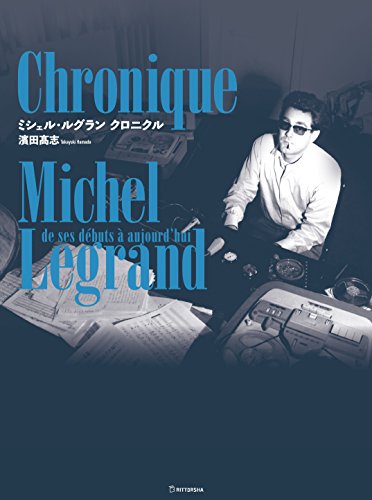『シェルブールの雨傘』、『ロシュフォールの恋人たち』などで知られ、3度のアカデミー賞を受賞し、手掛けた映画音楽は200本以上に及び、ジャック・ドゥミ監督との名作群をはじめ、マイルス・デイヴィスやバーブラ・ストライサンドら伝説的アーティストとの共演を重ね、その創造力で映画音楽の歴史を塗り替えてきたフランスの音楽家:ミシェル・ルグランの創作の舞台裏と人生の軌跡と最後の舞台に迫る圧巻のドキュメンタリー『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』を池袋の新文芸坐で観てきました。
今日は、音楽家:ミシェル・ルグランのことを呟きたいと思います。
今回は、坂本龍一さんの『戦場のメリークリスマス』サウンドトラック(1982年)録音などで知られる、世界的音響レコーディング・エンジニアのオノ セイゲンさんが、新文芸坐の映写担当と「BUNGEI-PHONIC SOUND SYSTEM」でそれぞれの作品に合わせて音を調整し、極上の環境で上映する『オーディオルーム 新文芸坐』という企画上映でした。
だから、音響は極上でした。音楽家のドキュメンタリーですから、ここは肝心ですよねー。
フランスを代表する音楽家ミシェル・ルグランは、2019年に亡くなりましたが、75年間の音楽人生の中で、特にジャック・ドゥミ監督とのコンビで名作映画を数多く生み出し、マイルス・デイヴィス、シャルル・アズナヴール、バーブラ・ストライサンドなど伝説的なアーティストとも共演を重ねてきました。
ジャン=リュック・ゴダールなどヌーヴェルヴァーグの監督たちから評価され、以後多くのフランス映画音楽を手掛けています。『シェルブールの雨傘』(1964年)はセリフの代わりに全て音楽で物語を展開させるという画期的な手法で、第17回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。
『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』ではルグラン本人と関係者がルグランの軌跡を振り返る形で、貴重な作曲の舞台裏が明かされていました。
練習において自他共に一切の妥協を許さない厳格な姿勢、ルグランにとって人生最後の公演となった2018年12月のフィルハーモニー・ド・パリでのコンサートの舞台裏に密着。数々の栄光に隠された挫折と苦悩など、これまで知ることのなかったルグランの姿も余すところなく描かれていました。
さらに、ルグランが携わった30作以上の映画の名場面や、16ミリカメラで撮影された若き日のルグランの映像など個人的アーカイブも多数スクリーンに映し出されました。
『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』を観て、私は一人の音楽家の人生に圧倒されました。
彼は成功した作曲家でした。名声も、賞も、名曲も残しました。けれど何より心を打ったのは、人生の終わりの瞬間まで、音楽に身を捧げていたという事実です。音楽を仕事にした人ではなく、音楽を生き方にした人だったと思います。
人は歳を重ねると、少しつづ何かを手放してゆきます。手放さざるを得ないのでしょう。情熱も、体力も、時間も…。
それでもルグランは手放さなかった…。最後までピアノに向かい、旋律を探し続けていた…。それは執念ではなく、命尽きるまで音楽のそばにいたいんだという祈りように私には見えました。
私はその姿を観て、大きく胸を打たれ、堪えきれずボロボロと泣いてしまいました。
私は子供の頃から、映画を好きになった時から、ミシェル・ルグランが音楽を手掛けた映画をたくさん観てきました。そしてたくさんの感動をもらってきた一人です。
ルグランの音楽は、映画をただ彩る装飾ではなく、主人公の人生や心の揺れを映す鏡のようだと思っていました。恋の幸福、別れの痛み、戻らない時間の気配…。ルグランは主人公の人生を旋律で語れる素晴らしい音楽家だと思います。
ミシェル・ルグランの音楽を語る時、ジャック・ドゥミ監督との関係は避けて通れません。
『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』では、音楽が背景ではなく語り手になっています。登場人物が歌い、街が歌い、人生が歌う…。それは現実よりも少しだけ夢に近い世界です。
全編が歌で構成される『シェルブールの雨傘』でのルグランの旋律は、恋の輝きと同時に、別れのinevitability(避けられなさ)を同時に抱えているように感じます。あのテーマ曲は甘いのにどこか痛い…。若さの恋が持つ残酷さを、音楽だけで語ってしまうところがルグランの凄さです。
ルグランの音楽の根底にはジャズがあり、クラシックがあり、異なる文化の要素を組み合わせた豊かで華麗な旋律は、ジャンルの垣根をなくしたといえるでしょうね。
そして何より映画の中で描かれるキャラクターへの共感性があります。
喜びは単純に明るくならず、哀しみも暗闇に沈みきらない…。絶妙な光と影の間で揺れているような旋律がルグランの特徴であり美学のような気がします。
『シェルブールの雨傘』のラストに流れるフィナーレ。あの旋律を聴くたびに、私は震えるほど感動してしまうのです。この作品を初めて観た時から、幾度となく観ていますが必ず涙してしまいます。
雪が降るクリスマスの夜に、ガソリンスタンドでギイとジュヌヴィエーヴが偶然再会します。再会は奇跡のようで、同時に遅すぎました。ルグランの音楽は、そこで観客に優しい慰めを与えません。むしろ静かに突きつけてくるようです。愛は甘いだけではない。残酷なものだということを…。
愛し合った時間が本物だったからこそ、戦争に翻弄され、別々の人生を生きることになってしまったことがあまりにも哀しい…。その痛みをルグランは涙ではなく旋律で描いたんですね。ルグランは、恋を飾る音楽を描いたのではない。人生の真実を旋律にしたのだと思います。幸福と喪失が同じメロディの中にある…。それがルグランの音楽の残酷なまでの美しさだと思います。
ドキュメンタリーの中では紹介されていませんでしたが僕の好きなミシェル・ルグランが音楽を手掛けた2本の作品を紹介しておきます。どちらも日本映画です。
『ベルサイユのばら Lady Oscar』(1979年)池田理代子さんの同名漫画を原作とする日仏合作映画です。
ジャック・ドゥミが脚本と監督を務め、音楽はミシェル・ルグランが担当。キティ・フィルム、日本テレビ、東宝のもとで山本又一朗さんがプロデューサーに就任し、フランス政府の協力によりヴェルサイユ宮殿での撮影が特別に許可された大作です。
革命前夜のフランス宮廷。華やかさと崩壊の予感が同居する世界で、運命に翻弄される人間の心模様を、ルグランの旋律は華やかに美しく、同時に胸の奥を締め付けるように奏でています。
もう一本は、手塚治虫さんの漫画作品を、市川崑監督が実写映画家した『火の鳥』(1978年)です。プロデューサーの市川喜一さんの要望で、テーマ音楽のみですが、ミシェル・ルグランとロンドン交響楽団が起用され、フランスで作曲と録音が行われたのです。
日本の輪廻と神話の物語に寄り添った壮大なメロディーで、 谷川俊太郎さんの詩がついていて、松崎しげるさん、ハイ・ファイ・セット、サーカスが歌っています。ルグランは親日家だったそうなので、この2本だけでも、日本映画のために素晴らしい曲を残してくれたことに感謝です。音楽は国境を越えるのです。
ルグランはアカデミー賞を3度受賞しています。
◎第56回(1984年)歌曲賞・編曲賞『愛のイエントル』
◎第44回(1972年)作曲賞『おもいでの夏』
◎第41回(1969年)歌曲賞『華麗なる賭け』(風のささやき)
『華麗なる掛け 'The Thomas Crown Affair'』の作詞はマリリン&アラン・バーグマン、歌唱はノエル・ハリソン。
スティーブ・マックィーン演じる、トーマス・クラウンという男は、虚無を抱えているように感じます。金も自由もある。それでも心は満たされない…。だから彼は盗みをするのだと思います。スリルのためではなく、心の空白を埋めるために…。ルグランが「風のささやき」で表現しているのは、トーマスの満たされない心と意識の中で、逃げても逃げても吹き続ける風の音を旋律にしたんだと思うのです。この曲は甘いだけじゃない。どこまでも不穏で、だからこそどこまでも魅惑的なのだと思います。
『おもいでの夏(Summer of '42)』は、思春期の少年が、一夏の間に経験する、淡くて痛い、初めての恋を描いた作品です。
青春の記憶そのものが旋律になったような曲ですね。恋は終わるのではなく記憶に変わって残っていく…。終わった時から思い出に変わるものです。その残像をルグランは旋律で描いているように思います。恋の喜びではなく、過ぎ去った時間の匂いを…。
『愛のイエントル』は、監督・製作・脚本・主演:バーブラ・ストライサンド、アイザック・バシェヴィス・シンガーの短編小説を原作としたミュージカル映画です。
東欧ユダヤ社会を舞台に、女性が学びを求めて男装し、自分の道を生きようとする魂の希求の物語です。世界に許されなくても、自分とは何者か、知りたい、学びたい、生きたい!そういう心の叫びが全て歌になっているんです。バーブラ・ストライサンドが渾身の力を込めた作品です。
ルグランは、主人公の心の叫び、痛み、希望、祈りを、飾り立てることなく旋律に変えて私たちの胸に深く届けてくれています。傑作です。
ルグランにとって人生最後の公演となった2018年12月のフィルハーモニー・ド・パリでのコンサートの舞台裏での姿にとても感銘を受けました。誰かに支えてもらえなければ足元もおぼつかない状態でも、呼吸が乱れて立つことさえままならなくても、最後の力を振り絞って指揮棒を振り、ピアノを弾くルグランの姿は、彼の音楽と共に生きた美しい生涯の集大成として僕の胸を深く打ちました。生きる証を見せてもらったようでした。
ミシェル・ルグランはその翌月、2019年1月26日に86歳で亡くなりました。
ルグランの音楽って華やかですよね。メロディは流れるように美しい。それなのに、なぜか不思議と涙が出る…。
『シェルブールの雨傘』『風のささやき』を聴くだけで、胸の奥が静かに揺さぶられ崩れていく…。ルグランはいつも、幸福と喪失、人生の甘さと痛みを、同じ和音で鳴らしてしまうからなのか知れません。ルグランの音楽って、映画が終わっても、心のどこかで鳴り続けるんですよね。
このドキュメンタリーを手がけたデヴィッド・ヘルツォーク・デシテス監督は、市の清掃員からドキュメンタリー監督へと転身したという異色の経歴を持つ人です。
デシテス監督の凄いのは、ドキュメンタリー映画制作の依頼をされたわけではなく、自分から作りたいとルグラン本人の面接を受けたことです。やはり、やりたいこと、作りたい物を形にするためには、現状を突き動かす情熱が大切なんだとあらためて感じました。
このドキュメンタリーの面白いところは、ミシェル・ルグランの天才的な面ばかり持ち上げるのではなく、感じの悪い側面も見せたところです。それも天才ゆえなんでしょうけど、ルグランの気性の荒さ、時には他人に強く当たるところも描き出されます。ルグランと働いた人たちには知られていたけれど、一般的には知られていなかった側面です。
驚きも多少ありますが、偉大な何かを作る人たちは、規格外の人物ですから、複雑さと矛盾を抱えているのは当たり前ですけどね。
『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』は、映画音楽の金字塔を築いた偉大な作曲家の生涯と、その人間的な素顔を描き出した傑作でした。
ミシェル・ルグランは、音楽に人生を捧げるとはこういうことなのかも知れないと教えてくれました。
『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』
◎監督・脚本:デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス
◎脚本:ウィリー・デュハフオーグ
◎製作:マルティーヌ・ド・クレルモン・トネール、ティエリー・ド・クレルモン・トネール、デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス
◎撮影:ニコラス・ボーシャン、リヤド・カイラット、スタン・オリンガー
◎音響:テオドール・セラルド
◎出演:ミシェル・ルグラン、アニエス・ヴァルダ、ジャック・ドゥミ、カトリーヌ・ドヌーヴ、バンジャマン・ルグラン、クロード・ルルーシュ、バーブラ・ストライサンド、クインシー・ジョーンズ、ナナ・ムスクーリ
◎音楽:デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス、ミシェル・ルグラン
◎2024年/フランス
原題:Il était une fois Michel Legrand
◎配給:アンプラグド