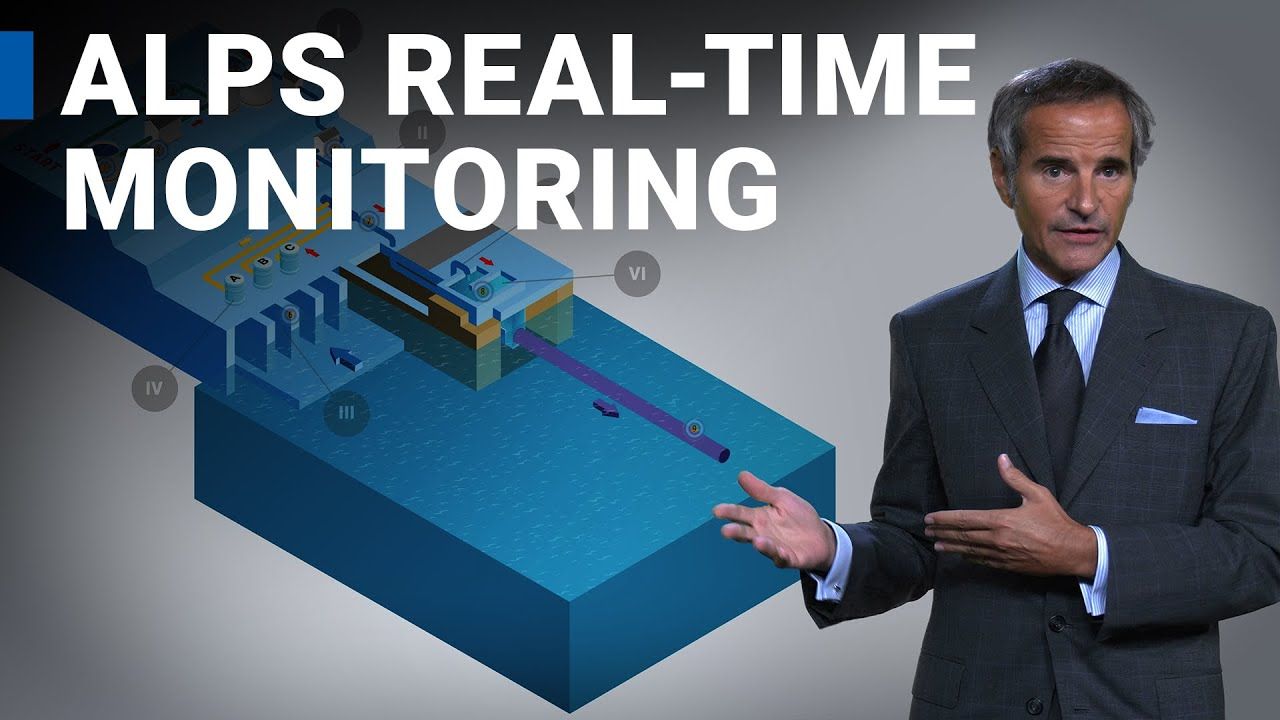エネルギー危機にもかかわらず、世界最大の原子力発電所は依然として停止したまま
2024年6月5日
Natural News

世界最大の原子力発電所である柏崎刈羽原子力発電所は、世界中でエネルギー需要が高まり、日本も高価な輸入燃料に頼らない方針を打ち出しているにもかかわらず、いまだに稼働していません。
2030年までにエネルギーの50%を原子力発電で賄うという日本の目標にもかかわらず、同発電所は2011年の福島原発事故以来、稼働していません。
ブルームバーグの最近の報道によると、2030年までにエネルギーの50%を原子力発電で賄うという日本の目標には、柏崎刈羽原子力発電所は含まれていない。同発電所は、現在稼働中の原子力発電所の中で最も高い8.2ギガワットの潜在発電能力を持つにもかかわらず、稼働していない。
福島の事故をきっかけに、日本全国で原子力エネルギーの見直しが行われ、柏崎刈羽原発の7基の原子炉が停止されました。
柏崎刈羽原発の所有者である東京電力に再挑戦の機会を与えるべきかどうかについての議論は、現在の経済政策や世界的な原子力エネルギーへの関心の高まりを受けて、ますます激しさを増しています。
国際原子力機関(IAEA)の予測によると、原子力発電容量は2022年の水準から2050年までに140%増加する可能性がある。
中国やインドが原子力開発を進めていることや、サウジアラビアが米国と原子力オプションを検討していることからも、重要な資源として原子力エネルギーへの再コミットメントが広がっていることがうかがえます。
「柏崎刈羽原発が再び稼働できることは、日本にとって非常に重要です。休止中の発電設備を保有している国はどのくらいあるでしょうか。多くの国が、それを保有していればよかったのにと思っています」と、IAEA事務局長のラファエル・マリアーノ・グロスィ氏は3月に述べています。
日本では、新しい原子炉を稼働させたり、既存の原子炉を再稼働させたりすることは政治的に難しい状況です。
風力や太陽光は発電量が変動するのに対し、原子力発電は安定した無炭素電力を生み出します。しかし、原子力発電所の建設には10年以上かかり、また、有害廃棄物を永久的に生み出します。
柏崎刈羽の再稼働は、地元自治体の同意が得られない限り実現しない見通し
日本の原子力規制委員会は2017年に柏崎刈羽原発の2基の再稼働を承認したが、地元自治体の同意が得られていないため、正式な再稼働日は設定されていない。
ブルームバーグは、柏崎刈羽原発のある新潟県で次回開催される地方議会で、この問題が審議される可能性があると報じた。
繰り返しますが、福島の惨事を上回る明確な利点がない限り、再稼働は実現しないでしょう。(関連記事:日本、福島の放射性汚染水の太平洋放出を承認)
これは、岸田文雄首相の政権が日本のエネルギー戦略を見直す中で起こっている。
これは、複数の利害関係者を交えた日々の評価であり、クリーンエネルギーへの取り組み不足に対する批判にもかかわらず、日本の原子力エネルギー目標を変更する可能性もある。
岸田政権が注目している要因のひとつは、日本のエネルギー需要の70%を輸入エネルギーに依存していることであり、安定したエネルギー供給と価格が保証されていないという事実です。
現在、国内で 21 基の原子炉が停止していることを考えると、これは特に顕著です。
「私たちは、顧客のために安定した電力源を確保する必要があります。海外からの燃料輸入に頼らない何らかの供給源を確保することが重要です」と、東京電力の小早川智明社長は4月のメディア向け声明で発表しました。
一方、日本の電力会社は、まったく新しい原子炉が必要だという点で一致しています。この分野の主要業界団体である電気事業連合会は、4月に、今後のエネルギー投資の指針となる明確な政策提案を岸田内閣に要求しました。
東北電力は、女川原発2号機の再稼働の可能性が浮上し、2013年以来最も高い水準まで急上昇するなど、投資家はすでに原子力発電の復活に殺到している。一方、九州電力は、原子力発電プロジェクトへの資金調達に関連した国内初の環境債に対する強い需要を受け、300億円(191億ドル)を調達した。