リーダーの意思決定スピードは速いに越したことはありません。
それは確かにそうですが、経験以上の意思決定や、扱ったことのない金額を
投資するような案件に対しては、意思決定を迷うのは当然で、すなわち意思決定とは、
立場ではなく、それまでの経験によるものに大きく影響されるということだ
と思っています。
リーダーという立場があっても、起こりうる全ての意思決定に関わる経験者
か?というと誰もがそうではないわけで、大事なのは、自分よりも、任意の
項目については経験している実力者から力を貸してもらえて、かつ、認めら
れるだけの「何か」があるかないかによるのでしょうね。
(ちなみに私は今まで立場だけは頂けたものの、その「何か」が全くなかった
ことだけは気がついた(苦笑)。)
痛いリーダーは、リーダーであるがゆえに、自分が知らないことや、未経験で
自信がないということを開示したくない意識やプライドが邪魔して、なんとか
取り繕おうとするものの、周りからは、無理や不自然さが透けて観えてし
まうことです。
それだけならまだしも、経営判断において、取り返しのつかない意思決定を
してしまうこともあるわけで、それは避けたいところですね。
私は、知らないことは知らないと言っていいと思うし、未経験のことは未経
験だと認識してしまうことが大切だと思います。
言うか言わないかは別として、自分で認識するかしないかです。
自分が何を知っていて何を知らないのか、自分は何ができて何ができないのか、
それを知っていることが大事です。
その認識がないと、足らない部分をどう埋めたり解決しようとすることもで
きません。
さらに、この認識があったところで、誰がそれを埋めるに相応しいかどうかを
知らないと、具体的に他人に依頼やお願いもできないわけで、それらを考えると、
まずは、自分の人生や経験を客観視する、あるいは自分自身を客観視してお
くというのは、最も重要な認知なのだと思うし、自分とは違った人と関われる
ような環境に属するというのも、とても大事なのだと思います。
リーダー批判だけが生き甲斐のような人はどこにでもいて、ただ、それは
無能なだけで、変わってリーダーをやって圧倒的成果を出すという覚悟が
あるとか、深く考えて喋っているわけでもなく、ただなんとなく無造作に
喋っているだけなので、放っておけばいいでしょう。
本当にリーダーを見限った人は静かに、カドをたてずに去っていくだけです。
去ろうとする人が、本当にまだ側にいて欲しい人であれば、そちらの本音の
声に耳を傾けた方が気づきの可能性はまだあるでしょうね。
ビジネスの場面において「責任」という言葉は様々な局面で、曖昧で不明確に
出てきますが、現実的には、お金を投資する人物が、投資した結果、
投資した分のお金がなくなったり、借金を背負うというリスクに集約されます。
(まぁ、うまいこと回避するようなのもいるでしょうが、ここでは論外。)
そういう意味では、ゼロから、あるいはマイナスの窮地から立ち上がった
経験者というのは、その経験者であるわけですから、一般には尻込みするよ
うな意思決定も、一般の人に比べれば速いということになりますね。
そういう意味では、「責任」をとるだとらないだ、本当の意味で言えるのは
オーナーか、オーナー経営者か、あるいは、決済金額の上限内の立場の人と
なるでしょう。
では万人に与えられた「責任」、例えば、全く決済金額のない人にとっても
与えられる「責任」とは何かと言えば、結果に対する責任よりも自らが
発言したことや意思決定したことに対して、結果がどうあれ、結果が出るま
で、持てる全力を尽くすということ以外にないと思っています。
会議やミーティングの場で、意見を譲らない人や、自分の意見が通らないと
不機嫌になったり、やり気を失ったり、本気で憂ている人に、時として
私がやるのは、
「分かった、では君の意見に100%譲ろう。君の施策で、君の言う通りに
しよう。ただし成果に対するその全責任は君だという腹は持てるんだな。」
と試す時があります。
「望むところです。ありがとうございます。」
と言ってくれればいいのですが、受けて立つ人は、実際にはほとんどいません。
言いたいことは言いたい、自分の意見は通したい、立場は守りたい、
でも責任やリスクは取りたくない、というタイプの方が圧倒的に多いのが現実で、
このタイプを組織階層の上にのさばらせておくことは、それこそ大きなリスク
となります。
このタイプは成果は自分のものにしますが、ミスは他人や環境のせいにします。
上司に自分の意見が取り入れられたかどうかに大きな価値をみるタイプですから、
要するに、リアルな実力がありません。言うだけでやらない人です。
話を戻すと、言った以上は、最後は誰もやらなくても自分一人でもやってみ
せる、という前提に基づいた譲れない発言かどうか、腹を確認しにいってい
るだけということです。
評価というのは、ある一方ではドライに結果・成果に対して出るのが現実です。
しかし、信頼とか求心力というものは結果が出ても出なくても、自らの発信
に向かうその姿勢や行動・生き方から周りの人達から得られるものだとしたら、
自らのリーダーシップは、自らで創り出せるに相応しいと思うのです。
そう考えると、リスクの小さな若いうちの方が、実はリーダーたる要素を
培いやすいということができるとも言えますね。
正解が誰にも分からない今の時代、職位や立場だけでリーダーとはいえない
状況だからこそ、若い方がリーダースキルを身につける最大のチャンスとも
言えますね。
かく言う私が、結果に対しても、全力の姿勢に対しても、リーダーであるか
どうかは別問題ではあります(苦笑)。
まぁ、だから、今までイロイロやってきた結果、一人の選択をし、一人の
リスクを今のところ取っているわけですからね(苦笑)。
ともあれ、大きな時代のウネリの中、リーダーの定義すら変わってきている
ような気がして、私は私で考えていくことにします。
リスクの小さいうちから鍛えておこう。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
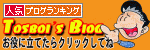
iPhoneからの投稿
