組織やチームで動いている会社や店舗で、業績が落ちたり鈍化しているとし
ます。
対策を練る為のミーティングや会議を行うことは決まっているものの、日時
と場所、メンバーだけが決まっていて、肝心の「その会議を、どう進めて
何を決めていくのか?」が、決まっておらず、リーダーに相談されることが
あります。
会議のシナリオと出口が見えないということですね。
業種や業態を短期で一気に変えるのは現実的に難しい場合、まずは、今ある
環境で何をしていくのかを一緒に考えます。
こういう場合、抱えている問題を認識するところから入った方がいいので、
ある程度の仮説に基づいて問題を抽出することにします。
大抵は、下記の大きく二つのうち、どちらで止まっていることになります。
①何をやっていくのかが決められていない。
②何をやるかは明確だが、実際に稼動していない。
①は、どちらかというと「企画面」での案だしに閉塞感を持っていて、
②は、どちらかというと「運営面」で上手く行っていないパターンです。
業績を上げる、というような名目で集まったもしても、その内容や進め方は
全く違ってきます。
逆にここが明確になるだけで、自分が何をせねばならないか、一気に見えて
きたりします。
とても不思議なのですが、ほとんどの会議名や研修名は、職位や立場に準じ
た名称です。
例えば、営業会議とか幹部会議とか、店長研修とか、その類いです。
本来は「○○を決める会議」とか、「○○の案だしをするミーティング」
とか、「その時間を使って、何をするのか」という名称に変えていくと、
当日に何をするのかが分かりやすくなるし、それにより招集メンバーそのも
のから変わってきたりもします。
余談ですが、それを事前に考える招集リーダーが少ないのも現実だったりし
ます。
なぜ少ないかとなると、招集者が、「自分の考えていることや、言いたい
ことを誰かに聞いて欲しい会議」になっている場合は往々にしてあります。
日頃、「皆で考えよう。」と口では言っている場合はなおさら自覚するのは
イヤでしょう。
ただ、それならそれで、そう言ってしまった方がいいのです。
参加者は何も考えずに当日を迎えるだけで良く、いらぬ思考や資料作りに
時間を使わなくて済む分、助かります。
考える時間というのが、最もエネルギーを使うのです。
話を戻します。
企画そのものの案が欲しい場合、
どうすれば企画案が適正に運営されるかにヒントが欲しい場合、
既存メンバーで行う場合、
外部の者に参加してもらう場合・・、
それぞれの場合のバリエーションによって、招集リーダーは事前に思考して
おく時間を取ることが大切でしょう。
会議も編集力が問われる。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
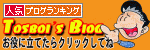
iPhoneからの投稿
