「挑戦」とか「チャレンジ」というのは、聞こえはいいけど、
成果に対しては無責任なのと同じです。
チャレンジなのだから、成功確率が低くてもやってみるということです。
昨今のビジネスの現場で、これは行けるかもしれないと
チャレンジしてみたことで、ヒットを飛ばすことは1割あるかどうかが
私の体感値です。
目論んだことに対して、目論んだ通りの成果が出たことは、1割あれば
ホントにいい方だと思うのです。
ただ、残りの9割が無駄かというとそうではなく、
別の場面で活かされたりすることは多々あって、
結局、スキルが上がっていく人というのは行動している人、という論法に
なっているのだと思っています。
上司が部下に何かを依頼したとして、部下が難色を示したとします。
やらせたい時に、
「チャレンジをしてみよう。」
と説得を持ち掛けて、やる気にさせたとします。
チャレンジさせた以上、その行為に対して、やったか・やらなかったかは
問うべきでしょうが、成果を問うのは間違っていると私は思っています。
その成果責任は、チャレンジを意図した本人・・・、
自分であれば自分だし、チャレンジの言葉を持ち掛けてやらせたのが
上司であれば、その上司です。
にも関わらず、時間の経過と共にいつの間にか部下の成果に対して
部下に問い続け、責任を押し付けるような行為をすれば、
部下のモティベーションは下がるに決まっているし、精神的にも追い詰め
られておかしくなるに決まっています。
「チャレンジ」という、本来尊い未来に向かう行為を、
取り敢えず「やらせる」為の無責任な使い方は私は好みません。
逆に、部下が「チャレンジさせて下さい。」と体良く言葉を使って、
やりたいことだけ言ってきて、成果責任は問われたくない意図を
感じた時、私は案件によっては絶対にやらせませんでした。
業績を落とし続けている緊急時は、部下育成より、直接業績を上げる為の
行動行為にシフトせねばならないのは私は当然だと思っているし、
それができないのなら、リーダーは変わるべきです。
成果を出さねばならない時と、その経験をすることによって育てようと
する時とでは、判断基準は変わります。
できるかどうか分からないけど、チャレンジしてみて、かつ成果が出た時の
インパクトは大きく、貴重で感動的な体験となるけど、
それは滅多にないことだから、という前提があるからでしょう。
チャレンジはせねば、成果は何も得られません。
ただし、チャレンジをすれば成果が必ず手に入るというものでもないことは
分かっておく必要があると思うのです。
そういう意味で、イルカが口から飛び出るこの画像は、
尊いチャレンジですので、成果状態はまだ問わないで下さいね(笑。
外人に笑われてもやるのです(笑。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
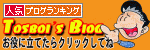
iPhoneからの投稿
