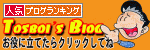一つ前の記事に、「置き換えの法則」の①「直接置き換え」について書きました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://ameblo.jp/tosboistudio/entry-11766601879.html
その続きです。
講義やセミナーで聴く時の成功事例等を「置き換え」する時には、この3段階を
適用すると自社に落とし込みやすくなるという話です。
①直接置き換え
②中間置き換え
③本質置き換え
こ3つを私も定番で使っています。
今回は
②中間置き換え
です。
これはどらかと言うと、異業態同業種の場合に有効です。
例えば、アパレル業界での交流会やセミナーで、同じ業種なんだけど、
集まっている人達は、メーカー・卸・小売といった様々な業態の場合ですね。
自社の業態そのものが衰退していっている時に置き換えてアイデアを出してみます。
自分の業態が厳しくなった時の、定石パターンとして「一歩川上・一歩川下」と
いうのがあります。
「卸」の業態から見た時に、「メーカー」「小売」で当たり前で普通のこととされている
ことが、「卸」業態の中ではでは、とても斬新で革新的なことがあったりします。
これを、そのまま自社に組み入れると「卸」業態の中では突き抜ける可能性がある、
という論法です。
例えば・・・・・・・・、
私の家業であった傘屋さんの基本機能は「傘メーカー」でした。
海外で大量に低価格の傘を生産して「問屋」さんに売っていました。
売り方は、全12色の傘の色があったとして、「一色」60本入りのケースが一単位です。
ケースを一単位として売るという方法です。ロットというやつですね。
売られた方は、あまり売れないけれど、店頭の差し色としては欲しい「白」や「パープル」と
いった色も60本仕入れることとなり、全色揃えると720本となり、見せ筋の色は在庫リスク
となります。
箱をバラして、それぞれの色を小分けにして小売店に売るのは「問屋」さんの仕事だった
んですね。
私は、その「問屋」機能を「メーカー」であるこちらでやって、「問屋」さんに売る、
という方法を試みました。
だから、「欲しいけどリスクの高い色」というのは買うことができない小さな問屋は、黒や紺の
傘ばかりで楽しくない品揃えになっていました。
私は、そういう売り先に対して、欲しい色を欲しい数だけ売るということをやってみました。
一色60本入りの箱を開けて、問屋さんから発注がきた、問屋さんが欲しい色を一本から
こちらで揃えて、60本入りのケースに各色で詰め直すという方法です。
問屋さんとしては、欲しい色の全色を、小さい在庫リスクで揃えられるということで、
発注が相次ぎました。
条件はほとんど変えませんでしたから、相手にとっては喜ばれるけど、
自社にとっては、余計な手間が増えるという、一見無駄な行為とも思えましたが、
結果としては、取引額が一気に増えた結果となりました。
私の手間が増えるだけなら、私が余分に働けばいいだけのことなので、
コストもかからずに利益だけが上がるだろうと、まぁ後先考えない方法でしたが(笑)。
「問屋」では当たり前にやっている普通のことを、「メーカー」でやってみたということです。
当時の傘メーカーさんの多くは、そんな面倒なことはしていませんでした。
業界常識的には、考えもしない面倒なことでしたが、私はただ手間をちょっとかけただけ、
そう、本来「問屋」さんがやるべきと思われていた機能を「メーカー」てやっただけです。
その経験は、いずれ直接「小売り」へ売りに行くということに発展していきました。
これにより、一時的な挽回ができたことがありました。
そういうことです。
今では、アパレルでは、ユニクロを筆頭に「製造小売り」というのは当たり前になっていますし、
例えば、牛とか米とかの農業が中心だった方が、そのまま焼肉屋さんも展開したりとか、
6次産業と言われるのが普通になってきていますが、
この「中間置き換え」の発展型といえるでしょう。
「一歩川上・一歩川下」というのは、特に流通の世界では、モノが出来上がって流通していく中で、
生産している方に近いほど「川上」で、消費者に近いほど「川下」と言われていることから
の名称です。
セミナーや勉強会では、「B to C」のビジネスを展開している方の話を聞くこともあるし、
「B to B」の業態の方の話を聞くこともあります。
私の前職のリサイクルショップは、言ってれば「C to C」の世界でした。
「〇〇業界専門セミナー」というのは、そのまますぐ置き換えられる事例は満載でが、
すぐマネができるということは、誰でもすぐマネできることであり、よって標準化は
時間の問題です。
無論、大事ではあるでしょうが、すぐ儲かることだけを考えて「同業界のセミナー」だけ
行っては儲かるネタだけ探すと言うのは考えものです。
②の「中間置き換え」は、ヒットすれば、他社がなかなか追いつけない自社の価値に
繋がるのが大きなメリットでしょう。
デメリットもあって、やはり少々時間がかかることと、私の事例のように最初は手間が
かかることになるでしょうか。
セミナーや講義というのは、発信している側というのは自分では普通だと思っていることは
当然ながら喋りません。
よって、この「中間置き換え」のヒントは、案外、バカっ話や世間話の中にヒントが隠されています。
違う業種や業態の相手の、日常の仕事のことを積極的に聞きまくったり(笑)、
どんどんバカっ話をしてみることが大事となります(笑)。
自分とは違う人とほど、積極的にバカっ話をしまくりましょう(笑)。
バカっ話の中に大きなヒントがある。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓