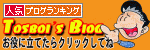私がセミナーや講演をする時に、よく最初お伝えすることに「置き換えの法則」と
いうのがあります。
もちろん、これは私が聴く側になった時にもよく意識するやり方です。
以前は、よく講師や先生から、「今日の話は、是非ご自身のビジネスに置き換えて
考えてみて下さい。」とは言われましたが、私にはさっぱり分かりませんでした。
言葉は何となく分かるものの、何をどうすることが「置き換え」とするのかは、
人によって様々です。
ある異業種の集まりの経営者勉強会で聞いた話がとても分かりやすくて、以後
私はこれを使っています。
置き換えには3段階あります。
①直接置き換え
②中間置き換え
③本質置き換え
です。
①直接置き換え
これは、とちらかと言えば同業の集まりの時に有効です。
同業他社の成功事例や販促事例など、具体的な内容を、つべこべ言わずに
そのままパクってしまう、そのままマネしてしまう、という方法です。
「こういうやり方はウチにはちょっと・・・・」とか思ってもやってしまうことです。
同業でなくとも、販促物などはそのまま置き換えられることは多く、
私の経験上では、最大のメリットは、学んだことを行動に移すスピードが速く、
即効性が最もあります。
実際に行動するので、そこから気づくことや学ぶこともあって、徐々に自分の
モノになってきます。
なんだかんだ言って、まずやってみる、ダメなら変えればいい、というサイクルを体現できる
やり方で、伸びる人はこのパターンが多い。
最初は、とりあえず量から入っていく中で、次第に質がついてきて本物になっていきます。
ただし、デメリットとしては、よほと意識しないと続かないことにあります。
そのままマネをするということは、自分が「好き」「嫌い」関係なしにやるということ
です。人間は「好き」なことしか続けられません。成果を出すには一定の継続が
必要で、成果が出るまでやり続けられるかどうかのハードルはあります。
例えばですが、私は以前、「東スポ風」チラシという「東京スポーツ新聞」の見出しや
レイアウトをパロディにしたチラシを連続したことがあります。
(前職のチラシなので画像が出せません(苦笑)。過去のブログから見つけてみてください(笑)。)
私は、子供の頃からプロレスが好きで、このスポーツ紙はプロレスネタが毎日出ていたので、
よく見ていた関係から、見出しのネタには困りませんでした(笑)。
「ネッシー発見!?」「UFO飛来!?」「ツチノコ捕獲!?」などアホアホなゴシップネタが
満載の新聞だったので、さらにそれをパロディにし続けることができ、成果を実感するに
至りました。
ところがある日、地元新聞社から「紛らわしいから止めてくれ。」とクレームが入って、
それならと思って、今度は「中吊り広告風」で行こうとなって、
雑誌「週刊女性の地下鉄中吊り広告」風のチラシをやりました。
これはこれで面白かったですし、良かったのですが、これは続かなかった。
いろんな理由はありましたが、最も大きかったのは、「好き」ではなかったからネタも含めて
続かなかったんですね(笑)。
そういうことです。
よく経営者勉強会で、方法としての成功事例を見つけてきて、すぐに「他社で成功してい
のだからこれをやろう。」と自分では何もせずに部下に指示だけ出して、
進んでいないと「どうしてウチの社員は・・・・・・・。」と嘆く人を見ますが、
それは指示を出した側が、あまりに人の動機に対してトロイと思った方がいいてしょう。
部下がそれをやるに当たってのモティベーションがどうなのか?
これをよく見ておく必要はあるということですね。
最初から「これなら面白そうだからやりたい!」となっているのか?
モティベーションが上がっていないなら、どう上げるのか?
最初は徹底的に強制をかけて一緒にチェックしていかないといけないのか?
誰もやらないなら、いざとなったら自分でやるくらいの腹があるのか?
新しいことは、色んな意味で誰でも恐いのです。
「最後の責任は自分が持つから思い切ってやれ。」と言ってあげられるのかどうか?
部下が「やってみました!」と持ってきたときに、いいか悪いかの判断はどうするのか?
の基準もなく、ただ「やれ」と言っているアホは結構多いのです。
このあたりが「直接置き換え」する時のポイントになると思います。
「直接置き換え」は、まずは自分がやってみることを認識してみることでしょう。
自分ではできないこと、足らない能力を誰に補ってもらうのか?という思考で進むことです。
じゃないと、実際にやっている人の気持ちなど分かりません。
部下が乗ってきて、自発的にやりはじめたら、そこからは部下のお手柄でいいのです。
②と③は次に続きます。
「直接置き換え」は、まず自分がやりたいかどうか。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓