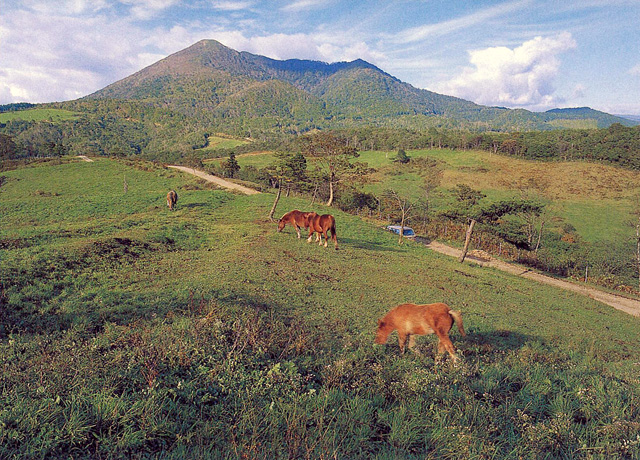そろそろ終わりにしたいのですが、
塩釜は深すぎて歴史妄想は、むずかしいが、
ドーパミンが放出します。
でも早く手放したい~
じゃないと終われない。
ちょっと長くなります。
さて、何から書いたらよいのか。
多賀城から終点は、本塩釜駅でした。
塩釜で行っておきたい所がありまして、
「白坂観音堂」です。
由来>あんまりわからない。
法蓮寺には12院の脇院がありました。
『奥州名所図絵』には、 裏坂(東参道) 周辺に脇院が立ち並んでいた様子が描かれています。
脇院の1つである普門 院は白坂にあり、
普門院内にあった観音堂は今も「白坂観音堂」として残って います。
※塩竈の文化財より
雄石という謎の石があります。

実は、この観音堂を知ったのは岩手県八幡平の方の
白坂観音堂でした。
なので、塩釜に同じ名前の観音堂があることが気になり、
岩手と関係しているのか不明ですが、
行ってみることにしました。
ある資料に、
「白坂観音フォーラム(平成24年)」という1枚の紙が家にあり(もらったものですが)
岩手県にも白坂観音堂という同じ名前があることを知った事です。
奥州札所三十三観音霊場は、天台宗の円仁開祖と、
名取老女が後に改めたとして伝わります。
岩手県の白坂観音堂の縁起は、
724年、多賀城に朝廷軍駐屯。
728年、聖武天皇の勅命として建立。
802年、胆沢城築城
857年、極楽寺を北上市国見山に建立。
上記のように大和朝廷は、
「仏の力を借りて蝦夷の民の心を和らげていただきたい」
との陳情に応じて国府の所在地以外に、天皇の発願により
国家鎮護のために仏堂を建立。
岩手県の白坂観音堂は、行基により728年に建立。
同じ年に天台寺も建立し、
730年に黒石寺を建立。
岩手県の白坂観音堂は、エミシ征伐に深く関係する
お堂だったのです。
行基は藤原不比等についていた人なので、
北方の民族が多かったことを考えれば、
続縄文文化やアイヌ文化、キリスト教・ユダヤ教なども含め、
藤原政権に組みこませるために仏教を推進させる意図が
あったと思います。
現在建てられているお堂は、
きれいな山名の「七時雨山(ななしぐれやま)」から、
流れる川と田代から流れる染田川の合流地点にあるそうです。
すてきなお山ですよ~。
何度か遷座し、1875年6月に聖福寺(奥州札所観音31番)
にうつされ、現在に至るとの事。
さて、この白坂の意味はなんだろう?
塩釜の白坂観音堂も征伐の地であったのだろうか?
追記しますと、
1763年、中興七開基といわれる宮城県の僧七人が
奉納した木の額に刻まれ、白坂観音堂に納められている
「御詠歌」があるそうです。
「紫の雲を染田の観世音
ただ十念のおこたらぬ身を」
(※十念:10個の念仏)
だからね、
「紫色たなびく雲~」なんですよ。
ところで、中興(ちゅうこう)とは、
「一度衰えていたり途絶えた物を復興させる」
という意味なんだそうです。
王朝や寺院を復興させた人物につけるそうです。
それで、「奥州鎮護」という言葉なのですが、
誤解していたのですけど、
塩釜神社がなぜ「鎮護」なのかは、
塩釜大所明神というのですが、
大明神とは、神號(しんごう)として用いていると。
神號とは、
神の格式や性質を示すものとして、神名に付加する呼び名。
皇大神・大神・明神・天神・権現・新宮・今宮など。
東北の「艮(うしとら)」を守って創建された意図があり、
鎮守とは、「肩書き」のことで、
奥州を鎮護する官職のことを指すのだそうです。
その多賀城の下は塩釜の津で食塩の生産地となる。
清めの地にふさわしい場所でもあるのです・・・
そんなことで、
もう少しほりさげてみると、意外なことがわかりました。
■国府津の地名--------------------
真面目に塩釜の歴史について、さらっと調べてみました。
『塩釜市史』より、
塩釜は元は「国府津(こうつ)」と呼ばれていました。
いづれも大和言葉で、多賀城が置かれる以前の
先住の地なので、大和言葉をつけられる。
大和文化が最初に成立していたとは思われないため、
国府津とは港津のことなので、
多賀城を築くために、荷物や物資を船で輸送した港のことを意味する。
その後、製塩が伝わり塩釜になったと考えられる。
海の記憶・・・
なんと~
その国府津の地名がついた場所の発端が、
白坂だったのです!

白坂が塩釜のルーツだったなんて。
行かなきゃ、わからなかったよ。
そこが「舟戸(ふなと)」だったんですよ。
立地条件からみて、港地に適しているのが「白坂一帯」であると。
本町から仲宿に曲がる町角に、
白坂の丘陵地からのびた陸地が岬端になって
東北に約50メートルほど海中に突出。
仲宿の海岸の風波を遮ぎついていたから、
船着場→白坂→岬の跡が残ったという。
そして、ここにも「鳥居原」の地名があったんですね。
磐の鳥居があったという話しも。
なので、このあたりは、船着き場だったのです。
■多賀と名取の藤原実方---------------
で、これは、名取の閖上と同じでは?
藤原実方は、名取の道祖神の前で落馬して
亡くなった伝説があります。
お墓も名取にあります。
古代、塩の道沿いです。
(名取(39号線)にある塩薬師如来)
多賀城へ行っていたのですが、
なぜか、名取に来ている。
それで亡くなっているという謎の行動。
名取老女が勧請したという名取熊野那智神社がある
高舘山も閖上が港だったので、物資を運んでいました。
その平野部に属する下余田に名取老女伝承が誕生し、
わらじを編んでいたのですが、船着場があったから、と。
旅人にわらじを編んで渡していた。
そのわらじがをはくと、足腰が良くなると評判になる。
太白区には多賀神社が2社あり、
多賀城以前に陸奥国府(郡山遺跡)があり、
地震と津波で国府が壊れたため、多賀城へうつしたと。
そんな実方さんの共通は、
藤原実方ー名取ー道祖神(ふなと神)
藤原実方ー塩釜ー舟戸(ふなと神)
多賀城の前身が、名取一帯。
塩釜明神は不明ですが、道祖神のフナト神に
関係する塞神かもしれない説がある。
他、猿田彦命説も多いですが、詳細はわかりません。
塩土翁との会話は、あこやの松を探しに、
実方が道をたずねた人が「塩釜明神」です。(源平盛衰記)
塩土爺のことですが、藤原実方もまた塩釜明神と
接触していることを残している。
また、多賀城を焼き打ちしたアザマロは、
泉の方へも遠征にいってます。
「泉誌」によれば、
志波彦命は、岩切村にある岐神(ふなとのかみ)を祀つると。
それを石止(留)神社という。
七北田川の堤防上にあり。
その昔、志波彦神が白馬に乗り七北田川を渡ったところ、
馬が川底の石につまずき落馬したため、
冠を川に流してしまいました。
(七北田川の別名「冠川」はここから来ている説)。
多賀城に関係していた留守氏は、諏訪の方でしたよね?
似てると思ったのは、
愛子にある諏訪神社。
白幡大神、黒鳩大神、彌渡大神、住吉大神。
黒い鳩って・・・
ここに白と黒。
そしてニワタリ権現。
それに、大和町の方に黒川郡の黒がありますが、
蝦夷の境界にあたりますね。
そこから北上した色麻町の地名由来は、四釜でした。
塩釜→赤瀬(加瀬)→丸子→黒川のルーツがあったという。
だから、四釜のひとつが、岐神。
陸奥国に百座、黒川郡には四座が 祀られているが、
行神社はその内の一社である。
(猿田彦命です)
ここも道祖神、岐神
塩釜神社の7つの釜のうち、 3つの釜が行方不明になったとの伝承があり、
そのひとつの釜が、この沼に沈んでいると伝わります。
そんなことで、塩釜神社の歴史は、いろいろあるのですが、
とてもじゃないが、書ききれません。

白坂が国府津のルーツにあったことが驚きでしたが、
そんな塩釜のルーツに巡り合えたことが、喜びでもある。
何かが伝えているのですね。
きっかけは、青木神社でした。