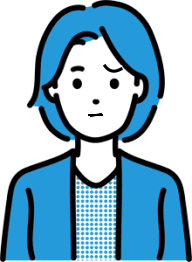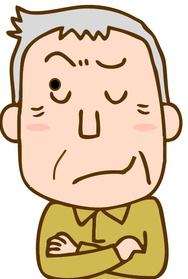第1章 ガッデム流 最終仕上げ
1986年(昭和61年)1月、2月
3年も終わりになるころ、ガッデムは媚びたような声で自宅に電話をかけてくるようになった。
教室ではそれまでの悪行非業は全部水に流してやる、といったふうな猫なで声で、僕を激励した。
「北原先生は厳しいかもしれないけど、それは生徒の将来をおもってのことだよ」
と、あるとき困った顔で、母がお説教した。
あれが厳しいなんてーー。
と僕は思った。
母はガッデムの伝書鳩として利用されているようだ。自分を圧迫することをやられているとも知らずに。
あれは、厳しさなんてものではない。逆だ。自堕落の強制。それに他ならない。やつはだらしないのだ。不適切なことを無理強いして押しつけるのは厳しさとは言わない。傲慢さだ。厳しさとだらしなさの区別のつかない母。
大学出の高校教師というだけで舞い上がり、おずおすと従う。やつの実体がまったく分かっていないのだろう。やつのこれまでの数々の悪辣非道の行ないについて何も話したことがないし、口に出すのも嫌だった。口に出して言えないほど僕は鬱屈していた。母に話したところで何も解らないだろうし、困ったことはなんでも夫に下請けさせようとするだけだ。そしてその夫がーー
これだ。
彼女ら夫婦に学校のことを言っても埒があくとは思えなかったので、極力、話さないようにしていたのだが、先手必勝とでも思ったのだろう、ガッデムは煩雑に家に電話をかけてきて母を説得していたようだ。自分の悪口を言ってやしないかとーー。いや、作戦の最後の仕上げだとしか思っていなかったことだろう。
そういうわけで、僕は黙っていた。黙って結果を出す以外に僕の状況を打開し道を開くものはなかった。担任がどうであろうが、両親がこうであろうが、僕は合格点を取るような勉強をしてさっさとこの家から出て、自分の人生を歩み始めるしかなかった。
この人たちのことを考える暇はなかったし、考えるのは時間の無駄。この人たちの人生の選択を僕はどうしようもないし、この人たちのところに降りてチャンちゃんバラばらやれば、この人たちと同じになるだけのことだ。
ともかく、こうなった以上、不本意であったけれど全力を尽くすしかないのだ。僕はなにも言わず部屋に入り、勉強を続けた。
僕が公立高校に落ちた春、毎日1時間以上かかる学校に自転車の往復をしていた頃、父は戦い疲れ打ちひしがれた戦後の復員兵のようにぐでっと溶けたようになって、
「早よ働いて親をラクさせろ」
と僕の顔を見るたびに言った。そして、情けないことを並べ立てた。「退職したら、収入がなくなるぞ」「腰が動かんごとなる」「どんどん弱っていく」
まだ、45歳だった。
母も母で、何かと言えば、
「もー、早く働いてー」
と苦情を言う。上の歯と下の歯がカネカネカネと音を立てているようだった。
連日連夜の夫婦喧嘩はひとまず止まったが、入学時の出費と毎月の授業料が家計を圧迫しているのを悔やんでのことだろう。その点で彼らは意気投合していた。
父は、船に引き上げられて腸を抜かれたアンコウのようにブヨブヨにふやけていた。
あまりに老後の心配をするものだから、西鉄駅の界隈立花通りで見かけた数件の自転車一時預かり所のことを話した。


「あそこで働いたらいいよ、そしたら椅子に腰掛けているだけでいいからーー」
すると話の意味がわかった父は、
「そんなこと考えんでいい」
と怒ったように言った。
要するに、自分たちの不埒は棚に上げ責任を僕にすべておっかぶせようとしていたのだったが、まさか僕を愛する両親がそんなことをするはずがないと思っていた16歳の僕は、心底心配して父に職業の斡旋をしたのだった。
僕の知能が発達した背景には、この両親の多大な貢献があった。たとえば僕が5歳頃のことだ。そろそろ相手の人となりが知れてきて、互いに嫌悪し夫婦間に不穏な空気が流れていた。昼間に母と二人で家にいると、なにやら一人でヒートアップしてプンプン怒り始めた母が台所からぬっと顔を出し、座敷にいた僕のところにやってきた。そして妄想の途中から訳のわからないことを愚図愚図言い始めた。あんたが、悪い、あんたのせいで私たちがこんな関係になった、といった旨のことをぶちまけたあと、母は僕にこう言った。
「子は( A )なんだから、あんたが私たちを仲良くしなくちゃいけないの!」
( A )に入る言葉を下の4つから選びなさい。(5点)
① かけ橋
② かすがい
③ カラス貝
④ 宝
「( A )ってなーに?」
と質ねる僕に言い淀んだ母はアレ! と天井を指差す。そこには屋根の骨組みが見えており、金具が打ち付けてあった。
「あれが、どうしたの?」
「あーもう、あんたダメ」
呆れた顔で母は何か説明したが、僕にはさっぱり解らなかった。答えは①のかけ橋だ。②のかすがいと答えた人は0点。母の錯綜まで読み解かなければ正解には至れない。
そしてまた、こんなことを子供に言うのが流行っていたようで、流行に過敏な母の口から同じ言葉が出るのを幼児期や少年時代になんども聞いた。
そしてまた、両親は互いを罵りあった後ときどき意気投合してこんなことも言った。
「親がダメでも、子供がしっかりしておけば、しっかり育つの! 世の中にはそういうちゃんとした子もいるのよ」
それはそうだろうが、自分や自分たちの矛盾を幼児に押し付けるとは、なかなか根性がある。
「子をかすがいにして夫婦仲良くしていなくちゃ、子供の教育にも悪影響だよ」
とでも誰かに諭されたのだろう。それが思い出されてムカムカしてきたのだろう。
こうしなければいけない、ああしなければいけないと我慢して爆発する母の憤懣は、僕の生まれる前実家に嫁いできたおない歳の伯母さんにも及んでいたようで、伯母さんは母を心底嫌っていた模様だ。爆発していない時の母はそれはそれはおしとやかで優しく思いやりがあって気品がありカワイイ女性なのだが、一度、限界に達するとゴジラのように荒れ狂った。
母は結婚して外に出てからも、伯母さんになにかと注文をつけていたようで、それは、早くに亡くなった父親や祖父(僕にとってはそう祖父・ひい爺ちゃん)から教えられた家のシキタリや物の考え方を伝承してやろうといった親切心だったと思うが、伯母さんにしてみるといじめられているように感じていたらしい。
「克也によくしてやれ」
と、苦情を呈する伯母さんをひいばあちゃんはたしなめていた。
母と伯母さんは同い年で、しかも伯母さんは当時はめずらしかった新制の高校を出ていたのだった。自分が『保証人倒れ』で困窮していたせいでいけなかった憧れの女学校を出ているのもどこかで癪に障っていたのかもしれない。
悔しさをこらえながら、伯母さんは僕にニコニコして接し、いつもなにかと親切にしてくれた。
正しいだけの母がそんな自分を反省し、改善することはなかった。
なんでもかんでも、ぎゃあぎゃあと禁止したり強制したりするので、母の妹すなわち叔母に
「どうしてあんななの?」
と尋ねたら、
「おばあちゃんに聞きなさい。製造元なんだから」
と、どちらかと言えば尖った物言いをするので、おばあちゃんに尋ねると、玄関先の上がり框に片足をかけたポーズで停止して片側の眉をしかめ、
「あげんあっと」
とだけ答えた。どうも僕の知らない母の幼少期から青年時代にかけても、母が御門違いによく僕を非難していたように
ぎゅうらしか
ったようだ。元々は筑後弁で「おおげさだ」とか「たくさん」という意味らしいが、めんどくさい・鬱陶しい・わずらわしい・うんざりなどのニュアンスで使っていた。幼少期の僕に無理難題をつきつけてはいじりまわし、いろいろ難癖をつける。僕が困ったり泣いたりすると、そう言って呆れたのだ。
自分が言われたことをお門違いの時になすりつけるパターン。「育てにくい」だの「一番手がかかる」だの「すぐ泣く」だの。暇を持て余してやっとお座りをした僕の頬をつねっては苦情を言った。
伯父さんや叔母さんや叔父さんや祖母や曽祖母を見ていると、決して母が僕に強いているようなことを教えてはいない。どこで仕入れてきたのか、母には勝手な正しさが蔓延していた。それで自分の首を絞めていたのだろうと思う。善い人になろうとすればするだけ自分から遠ざかる。そして、そんな自分を解って欲しかったのだ、母は。
こうやって誰にも指南されることのない最も身近にいる不可解な存在について、そのもつれた感情によって破綻した支離滅裂な理屈を紐解き相手が何を考えているか正確に理解する訓練を僕は幼少期から余儀なくされていたのだった。まさに他者理解の英才教育を受けていたのだった。
つまり、中学3年の僕が夜に勉強している隣の部屋でゴンゴン、ゴンゴン険悪なムードで夜中まで言い争っていたあれはきっと彼らなりのエールだったのに違いない。

それが、高1の夏と秋の間くらいからの僕の受験に邁進する姿を見て、とりあえず進学には反対しなくなり、むしろ彼らなりのサポートをするようになった。ーーつまり、無関心だ。特に父は。
父は亡くなるまで優柔不断とだらしなさが優しさとは次元のちがうことだと分からなかったようで、何年もの間、地獄でもがき苦しんでいる相手の鬩ぎを黙って我慢して耐えることが優しさだと思っていたようだ。
僕が受験勉強に取り組んでいるこの1年半の間、彼はぬぼぉーっと暮らしていた。そういう態度を僕の地域の方言でこう表す。
のんべんだらりのずんだらべったり
のんべんだらりのずんだらべったり
これはもう、24時間稼働の低波動発生装置といっても過言ではない。年中無休で働き続けている。
通常は、両親が揃っていて明るい笑顔に包まれ何不自由なく衣食足りて家族は互いに理解し合っているなどの理想の家庭像があり、それに比して家庭内暴力やネグレクト、あるいは多額の借金とか離婚とかそういう大々的な分裂や陰湿な虐待が取り沙汰され、大問題としてスムーズな受験を妨げる最大のファクターのように見なされる。その通りだ。
だがしかし、例えば水滴刑。
かえってこれが精神崩壊を引き起こし死に至らしめる最も苛虐な鬩ぎなのではないか。身体損傷よりはむしろ、終わることのない低刺激を繰り返すことにより精神苦痛と最終的な精神崩壊を誘発させ遂には死に至らしめる。実のところ、両親の体たらくと中途半端な和解と腐れ縁、真綿で首を絞めるような毎日毎秒の慢性的な低次元習慣の伝播、これこそが最悪の負の影響なのではないか思える。いないなら、いないがマシ。片親の方が幸いとさえ思える関係性がある。一人一人が低次元で互いに依存しあい、互いに互いの責任をあげつらう。
僕が受験勉強に取り組んでいるこの1年半の間、彼はぬぼぉーっと暮らしていた。中学3年から高校1年にかけて僕にとっては革命の嵐だったが、彼には嵐のやんだあとの倦怠だったのかもしれない。

そこに舞い込んで来た東京の私大への進学話。わけのわからないところにわけのわからないことが重なってパニックになったのだろう。俺に任せておけと胸を叩いた矢先、授業料が年間100万円と聞くや、
たぶんもう、自分が何を言っているのか解っていない。
「僕もそう思う」
と僕は答えたけれど、耳の遠い父に聞こえたかどうかはわからなかった。それをぜひ、北原捻也に言ってくれ。
ーーそんなん言うんだったら、お前には受験票、書いてやらねえ!
ーー自分で書きます。
「自分では、」
「書けねえんだよ!」
でも、その勇気はない。本人を前にすると、あれこれ自分のダメさ加減を引き合いに出してヘコヘコするだけだ。いやそれどころか、本人を前にすることさえできない。
「私の夫なのに、なんであんなにダメなのよ!」
「こんなに良い私が」
「なんで、こんな男と!」
「人生を台無しにされた!」
母も母で、自分が「こんな男」としか結婚が成立しなかったわけをしっかりと分析しなければ、同じ失敗を何度も繰り返す羽目になる。
いつしか僕は、この人たちに会わせるにはよほど真のしっかりした、聡明で慈悲心のある女性でなければならないと、そんな目線で結婚相手を探していたと思う。そんじょそこらの女性ではダメだ。金の草鞋を履いて三顧の礼をもって迎える最高の女性だ。第一、「親見て婿取れ」だの信じているレベルの近所の女性など、僕のことなど敬遠してしかるべきだ。あれだけ長期間にわたって連日連夜騒ぎ立てていて、噂どころか怒声が聴こえていないはずがないではないか。自分の中で渦巻く醜い感情を他人になんとかしてもらおうとして、地獄が増長していったのだろう、母は。
この時期にはすでに両親は炊飯ジャーを分かつていたはずで、
ゴチゴチに固いご飯派の母とやわやわのご飯派に分かれてしばらくは争い合い、覇権をめぐっていたのだが、母が、自分の単なる好みでなく、
正しい
と主張し始め、押し切ったのだった。それで、諍いを避けるために各々が炊飯ジャーを持ち合い、好みの固さで炊くようになったのだった。
この頃には、オルソン夫人からロッテンマイヤーを通り越し、オバタリアンと化した母が牛耳を執っていた。
僕と妹は母の炊くご飯を食べていたのだが、
父と張り合い戦っていた時期のご飯は、日に日に硬度を増し、
勝利を得た母がどう思ったのかは知らないが、停戦後のご飯はちょっと固めではあったけれど、それなりにちょうど良かったと思う。
諍いの元は、正しいに堕落させることにあるのではないかと思う。いや、諍いを起こして相手を負かそうとするのが目的なのかもしれないとさえ。
そんな母にもリベラル性はあった。オルソン夫人がロッテンマイヤーにかわった頃だったか。父と同様、母のネガティブな思い込みと押し付けも激しかった。たとえば1970年代には、日本人は塩食い人種などと揶揄され(あとの時代のエコノミックアニマルのようなものだ)塩を減らせ、1日5g以上の摂取は高血圧の元と言って、減塩減塩が叫ばれていた。たとえば袋ラーメンに入っている塩の量は1日に摂っていい塩分と同量かそれ以上が入っていると宣伝されていた。
正しいこと、より新しいこと、科学的なことを信じる母の司どる我が家の食卓もご多分にもれず、薄味と化していった。塩分の摂りすぎは病気の元と思い込むとどんどん減らしていって、少なければ少ないほど良いと考えるのだ。
肉体労働で毎日大量の汗をかく父には不満だったらしく、苦情を呈していたが、母は家族の健康のためと頑として聞き入れなかった。父が料理に醤油をかける度に悪態をついて制した。
塩の摂りすぎは高血圧になる、という不安によって従順に聞き入れたのだ。
同時期、逆に胡椒がかだらに良いと聞けば、どんどん増えていって、白米以外のなんの料理にでもかけられるようになった。香辛料の嫌いな父は顔をしかめて苦情を言ったが、体に良いから食べなさい、と一喝された。
父はおそらくこっそり外で塩分を補っていたと思うが、僕と妹は学校の給食で補給する以外に手立てがなかった。だが、マスコミの喧伝することを信じて最も被害を受けるのは、他ならぬ母だった。
どうにも調子がおかしかったのだろう、ある日、小学校の4年だったと思うけれど、帰宅すると母は僕をつかまえ開口一番言った。
ーー今日、ラジオでね、と母は話し始めた。
「看護婦さんが塩分の摂りすぎはいけないと、自分の子供たちの塩の量をだんだん減らしていって、塩をまったく与えなくなったら、耳が聞こえなくなり、視力が薄くなって盲目になんたんだって」
としおらしく言うのだった。それ以来、肉体労働者は背広着て仕事している人よりたくさん汗をかくから塩分は必要と主張し始めた。
『不安』×『不安』であったけれど、母はついに適度な塩分という概念に行き着いた。それで僕たち家族は難聴と視力低下から免れたわけだが、このなにやら科学的なことを権威のありそうな人たちがマスコミを通して伝えられることを無批判に信じ込んでしまうという浅はかさを利用して、僕らはさまざまな情報操作と思い込みを形成されていることに留意しておかなければならないなと思わせた一連の出来事だった。
ところがその数年後には、前に話した通り今度は父が会社で塩分について講義を受けたらしく、わけのわからない減塩に励んだのだったが、ともかく、こうした修正が時々なされたのは幸いだった。
父はまごうことなき、田舎者であった。が、さらに度がすさむと謙遜しようが、相手を立てようが、ちょっとでも自分をさげるようなことを言おうものなら、それ来たとばかりに
「自分で、言いよっとぢゃけん、そげんぢゃろ」
と決めつけ、バカに見下し観る目のないことを盛大に暴露すると同時に、そう信じているからこそ、自分のことを口でカッコつけ、言葉で知ったかぶるようになる。
行き着く先は群畜
訳も分からず、被害を受けたやられたに違いないと決めつけそれをやり返す。自分に甘さがあると、論理が狂う。破綻する
こうした田舎者の性質は全て持ち合わせ、不安、エゴ、自意識肥大、妄想、曲解、歪曲、拘泥 撞着 固執 妄執、他人のせい、責任転嫁、言い訳、非難、依存。
矛盾を指摘して怒り優位に立とうとする(非難するために)真理を非難に使う(自業自得など)比較して劣等を裁断する(威張るために)(進化するためではなく)間違いを認めない
怠慢・依存心・他責思考・劣等感・被害者意識・優越感・自信喪失・自暴自棄・嫉妬・罪悪感・悲観・慰め・同情・自己憐憫・卑下・欺瞞・不平不満・混乱・不安・慢心・渇愛・・・・
それらの造り出す理屈は、事実の認定の仕様は、おかしい、狂っている。捻じ曲がっている。(となれば、論理が正しい時、僕たちは愛に在ることになる。が、たいていこのことは誤解されている)
平等主義 威張り散らし(権威主義) 説教 自慢 昔語り 下の世代批判・・・・全て固陋な精神。
耳学問 知ったかぶり 調べない 早とちり 速合点 早飲み込み 一回おぼえた嘘を何でも繰り返す ゴリ押し・・・。そういうのを持ったまま、ぼおっとしていく。曖昧、朦朧となっていく。どうでもよくなる。投げやり、・・・・。自己否定・依存・被害者意識・劣等感・無価値観・不安・意気消沈・陰鬱・淋しさ・嘆き・後悔・・・そんなものがこの人の中で渦巻きさいなんでいる。それを誤魔化すためにテレビ・野球・ビールに逃げる。偽りの喜びで代用する。
いちいち指摘するまでもなく、一事が万事。愚か者の性質をほとんど全てを有帯している。こうした低レベルの信念や認識がズカズカと僕を通り抜け、いつしか共振してしまっているのだ。つまり低周波発生装置なのだ。これは24時間、年中無休で働き続けている。気づかなければ容赦なくそれらに蝕まれていく。けれども自分は周囲になんの悪影響も出していないと、それだけは自信をもって主張する。
そして、年収は200万〜250万、母はそれでいながら専業主婦といった、なんとも恵まれた状況に不平不満を呈し続けている。諍いが常態化し、家の中の空気が悪く、それを互いに互いのせいにしているといった環境。
両親も担任教師ガッデムも、決して自分の非を認めない者たちだった。
非とは、マイナスを発していること。これを認めてマイナスを出さないようにするのは、先ずもって自分に不利益をもたらさないのだから、気づいたらすぐに改めるのが賢明だ。だが、そうしない。愚図愚図のままに他人のせいにし始めたり、親や教師や社会や時代のせいにし始めたり、いまさら変えて仕方ないと言い訳する。
相手がマイナスを出しているのに自分を責めたり、妙に改める必要はない。ガッデムのように自分のエゴや我欲に都合が悪いからと非難してくるのに、合わせることはない。他人の出しているマイナスを観て、自分がマイナスを出してやしないか振り返り、要とあらば他人に気づくよう促すことだ。だが、いつまでも非を認めず権力づくで非を垂れ流して責め立ててくる大人たち。彼らは僕が悪いと非難するが、自分に都合が悪いのにすぎない。
それにシールドを作る方法を僕は高校時代を通して会得したが、それを知らない者は社会人になり上司や社長の悪習慣の餌食になって精神と肉体を病んでいる者もそれなりにいるかと思う。親の七光どころか親の七毒。だがそれを光に変えるのがフリーエネルギーだ。それらをアップコンバートして叡智をみるのが意志というものだ。受験をゲームと捉え、人生を学歴によってだけで決定するなら、完全に不利だ。ディスアドバンテージだ。だが、こういう中でこそ、真理は観えてくるものだ。ソクラテスが悪妻によって開眼したように。
しかしこの父は、次の年、僕が大学に受かったことも知らなかったのではないか? 日頃からぼけっとして受験には興味も関心もなかったし、伝えたところでまたつまらぬ反応しかしてこないと思ったのだろう、僕もあえて言わなかった。母さえもオメデトウのひとこともなかった。自分が心配していたことを解ってもらいたいが先に立っていたのではなかったか。僕もありがとうの一つも口にしなかったと思う。もう、来たるべき輝かしい未来に想いを馳せていたし、高校のことやこの家のことなど、羽化した蝶の抜け殻のように感じていたし、感謝の意を表明した途端、心配ばかりしていた母がどっと崩れ落ちそうな気がしたから。
3月15日に合格発表、27日までに入学手続き、そして4月の7日に僕はカバンひとつ持って実家をあとにした。
それから10日が経ち、20日が経ち、父は異変に気づき始める。家中を探し回り、ちょうど買い物から戻ってきた母にたずねる。
父「さいきん、おらんごたるが、克也はどこに行った?」
母「熊本」
父「はぁ?」耳が遠いので聞き取れない。
母「くまもと」
父「くまもと? なにしにやぁ〜」
ふぬけた顔で聞く。
母「大学」
父「だいがく? なんしに」
母「もう、よか」
父「なんや」
と怒り出す。それから父は実家のパーマ屋に軽自動車を走らせる。実家にすでに祖父母はおらず叔母さんが跡をとっている。道の途中で、そういえばそんな大学を受けるち言いよったな、と思い出す。叔母さんにボケたことを訴える。克也はあれは、
「大学に行きよるゲナ」
叔母さんは、受験前に髪を切りに行ったので、僕がどこを受けたか知っていた。
「ほぉ!」
とそこで初めてその価値に気づく。
そうなると今度は、合格者の父として控えめに宣伝し始める。要するに自慢だ。知り合いという知り合いに、ーー大学ゲナという話にもっていき、相手が感心する度に自慰していたのに違いない。
「いやぁーあれが受かるちは思うとらんじゃった」
とかなんとか、鼻毛でもむしりながらヘラヘラと謙遜をひけらかしていたのだろう。そして、合格者を出した父として親戚中に偉そうにアドバイスなどし始める。こうしたらうまくいったの、ああしたらうまくいったの。ねんがらねんじゅう、ずんだらボケぇーっとしていただけなのに。大学の間、僕が地元に帰る度に、父の知り合いからそんな話を聞かされる度に、すみませんと謝った。あの父ならそんなものなんだろう、仕方ない、やらせておこう、と黙って諦めていた。
だが自慢は、要するに他人を見下す行為だ。相手は口では「自慢の息子さんだから」などと阿諛するかもしれないが、反感を得るのに作用する。そうして息子の成果を貶めていることに気がついていない。受験の前も後も、不合格の時も合格の時も、この父はマイナスのことばかりやっていく。自分が何をしているのか、全く観えていない。
本来なら要らぬ自慢なんかより、自分の働きがわるいのと担任に何も言えなかったために、前年(今年の東京受験)に資金を出してもらっていたお礼を述べるべきなのに、息子の成功で自分まで偉くなったような錯覚をおぼえていたのにちがいない。しかしそれで会社の仕事に多少身が入った模様で、ちょっと彼の背骨を立たせた光明と言えなくもない。また、夫婦協力して僕たち兄弟の教育費を喜んで稼ぎ出してくれるようになった。
さすがに60を過ぎる頃には、僕ら兄弟の進学や就職、結婚、孫の誕生などで、両親ともにずいぶん落ち着いたが、やはり本質的なところは依存心の強さが邪魔をして、飛躍的に成長しているわけでないことが今際の際に出てしまった。子供の内に子供を産んで子供のままに子供を育て、子供のまま死んでいく典型の人たちだ。この人たちに、これが仲睦まじい夫婦だと見せる意味でも、僕はとびっきり明るい太陽みたいな女の人と結婚しようと思っていた。(奈緒子は好きだし憧れだったけど、月だ)
過干渉を通り越した我関せずの放置だったゆえに、GodDamn汚腹に押し切られた受験となった尽無しの我が家。なにもかもがチグハグでてんでんバラバラの受験も、終わりよければ全てヨシとなるのかーー。救いは僕のA判定、合格可能性80%だけだった。
つづきはseesaaブログにて