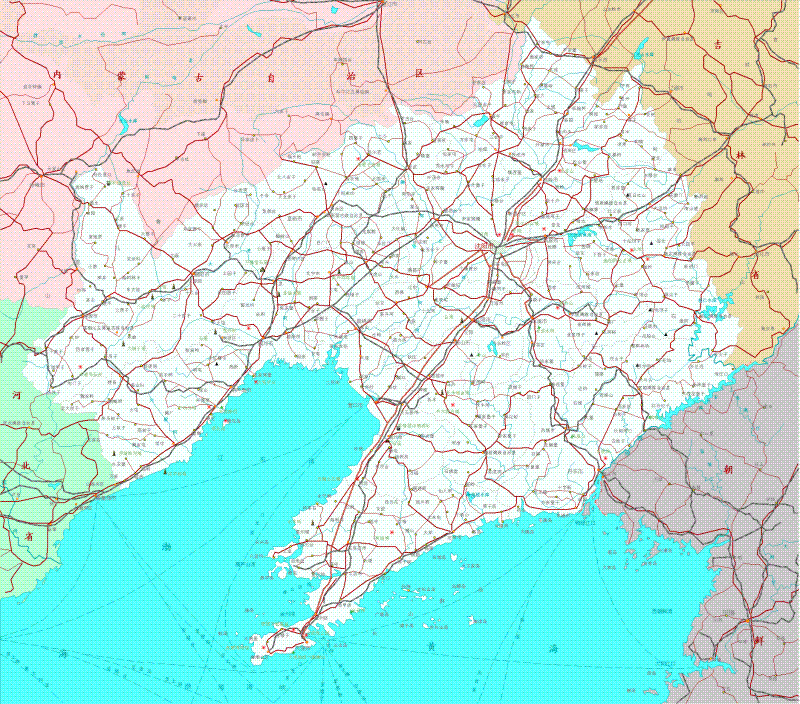太平洋戦争中、爆弾の雨が降る日本列島に比べて、満州の大連は不思議な存在だった。成都から飛来する爆撃機が爆弾を大連に落としたことはたしか一度か二度しかなかったし、死傷者が少し出ただけで被害は殆どなかった。主食品その他の配給制度はあったにしろ、僕たち市民が飢えていたわけでもなかった。
僕たち一家は、大連西部区域にあった聖徳街という完全に日本人家庭だけから構成されていた中級居住地帯に住んでいた。母は大連でも珍しい女医で、産科婦人科医院を開業していたし、彼女の配下には十数名の産婆と言われた助産婦が出産を取り扱い、母の仕事は概ね婦人科診療と難産の処置だった。
今から考えると僕の幼年期から真珠湾攻撃直後(中学二年ごろ)までの大連は、僕(だけ)にとっては一種の桃源郷であったと言ってよいだろう。大連は住みやすい、極度にモダンな都市だったし、生活必需物資は豊富だった。
大連市と旅順市は満洲本土から渤海に向って突出した三角形半島の頂点の左右に、西は旅順、東は大連と位し、ほぼ100キロメートル離れた両市を「旅大道路」という完全にアスファルトで舗装された南側直線高速道路が(註、赤線道路)結んでいた。南満鉄道本線の鉄道支線が北側を半円形に結び、汽車(黒線)で大連と旅順の間は僅かに二時間しかかからなかった。渤海湾を望み見て南へ半円状に迂回する旅大鉄道支線には夏家河子(カカカシ)という遠浅浜辺の避暑地があって、ユダヤ族親友の父が豪勢な避暑地ホテルを経営していた。
上掲、現在地図の三正方形区域(大連駅、中山広場、大連港)が占める大連東部区域はもともと20世紀初期にこの町を建設した露西亜政府がフランスの巴里を真似して計画した区域だった。円形の広場がこの区域に散らばり、それらの広場を高速道路が下掲空中写真のように放射状に連結していた。
下掲写真は大連市東南部にある僕の世代では「星が浦」と呼ばれていた「星海公園」の写真。母が医院を市内現人民広場区域の西側隣接区域に1937年ごろに開業する少し前に、僕たち一家はこの公園写真に見える左から二番目半島の背後に住んでいた。この公園の北部には別荘やヤマト・ホテルが散在し、南部にはゴルフ・コースが広がっていた。そして電車線がここいらと都心を繋いだ。
そして、下掲写真が僕の母校大連中学。写真左端が武道館と体育館。時計塔右側に繋がる白柱窓が講堂。押し開け自由な最新式の窓だったし、最新式のプールまだ備え付けられてあった。官立でなく、大連市立のいわば民立で、広い運動場が備えられた建物でもあった。
この中学で僕は太平洋戦争全期間の4年を過ごした。僕が朝鮮出身であったことは太平洋戦争までは問題にもならなかった。だが、真珠湾事件が勃発し、太平洋に戦雲がたなびき、戦況が悪化しだすと僕の環境は完全に変化してしまった。
あの4年間、僕は複雑な少年期を過ごした。
楽しい4年間ではなかった。だが、詳述しないが、この期間に僕を庇ってくださり、良心をもって教えてくださった恩師4名のことを僕は一生忘れまいと思う。
アメリカに渡ってからこの土地で60年の星霜を生き延びることができたのは、ひとえにこの恩師たちのお陰だった。
1945年8月15日に終戦勅語が放送されたとき、僕は上掲旧制旅順高校の寄宿舎に居た。
そして、その日から僕にとっては新しい人生次元が始った。
僕たち一家は、大連西部区域にあった聖徳街という完全に日本人家庭だけから構成されていた中級居住地帯に住んでいた。母は大連でも珍しい女医で、産科婦人科医院を開業していたし、彼女の配下には十数名の産婆と言われた助産婦が出産を取り扱い、母の仕事は概ね婦人科診療と難産の処置だった。
今から考えると僕の幼年期から真珠湾攻撃直後(中学二年ごろ)までの大連は、僕(だけ)にとっては一種の桃源郷であったと言ってよいだろう。大連は住みやすい、極度にモダンな都市だったし、生活必需物資は豊富だった。
大連市と旅順市は満洲本土から渤海に向って突出した三角形半島の頂点の左右に、西は旅順、東は大連と位し、ほぼ100キロメートル離れた両市を「旅大道路」という完全にアスファルトで舗装された南側直線高速道路が(註、赤線道路)結んでいた。南満鉄道本線の鉄道支線が北側を半円形に結び、汽車(黒線)で大連と旅順の間は僅かに二時間しかかからなかった。渤海湾を望み見て南へ半円状に迂回する旅大鉄道支線には夏家河子(カカカシ)という遠浅浜辺の避暑地があって、ユダヤ族親友の父が豪勢な避暑地ホテルを経営していた。
上掲、現在地図の三正方形区域(大連駅、中山広場、大連港)が占める大連東部区域はもともと20世紀初期にこの町を建設した露西亜政府がフランスの巴里を真似して計画した区域だった。円形の広場がこの区域に散らばり、それらの広場を高速道路が下掲空中写真のように放射状に連結していた。
下掲写真は大連市東南部にある僕の世代では「星が浦」と呼ばれていた「星海公園」の写真。母が医院を市内現人民広場区域の西側隣接区域に1937年ごろに開業する少し前に、僕たち一家はこの公園写真に見える左から二番目半島の背後に住んでいた。この公園の北部には別荘やヤマト・ホテルが散在し、南部にはゴルフ・コースが広がっていた。そして電車線がここいらと都心を繋いだ。
そして、下掲写真が僕の母校大連中学。写真左端が武道館と体育館。時計塔右側に繋がる白柱窓が講堂。押し開け自由な最新式の窓だったし、最新式のプールまだ備え付けられてあった。官立でなく、大連市立のいわば民立で、広い運動場が備えられた建物でもあった。
この中学で僕は太平洋戦争全期間の4年を過ごした。僕が朝鮮出身であったことは太平洋戦争までは問題にもならなかった。だが、真珠湾事件が勃発し、太平洋に戦雲がたなびき、戦況が悪化しだすと僕の環境は完全に変化してしまった。
あの4年間、僕は複雑な少年期を過ごした。
楽しい4年間ではなかった。だが、詳述しないが、この期間に僕を庇ってくださり、良心をもって教えてくださった恩師4名のことを僕は一生忘れまいと思う。
アメリカに渡ってからこの土地で60年の星霜を生き延びることができたのは、ひとえにこの恩師たちのお陰だった。
1945年8月15日に終戦勅語が放送されたとき、僕は上掲旧制旅順高校の寄宿舎に居た。
そして、その日から僕にとっては新しい人生次元が始った。