神功皇后と鞆の浦

神功皇后上陸画 素描 posted by (C)鳶眼
【神功皇后(じんぐうこうごう)】
成務四十(170)年ー神功六十九年四月十七日(269年6月3日)
仲哀天皇の皇后。彦坐王の4世孫、応神天皇の母であり、この事から聖母(しょうも)とも呼ばれる。
◎異称:聖母(しょうも)、気長足姫尊、息長帯比売命、大帯比売命、大足姫命皇后
◎父 :開化天皇玄孫・息長宿禰王(おきながのすくねのみこ)
◎母 :天日矛裔・葛城高顙媛(かずらきのたかぬかひめ)
◎皇配:仲哀天皇
◎子女:応神天皇
『日本書紀』では、気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)
『古事記』では、息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)・大帯比売命(おおたらしひめのみこと)・大足姫命皇后。
【気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)】
『日本書紀』によれば、201年から269年まで政事を執り行なった。夫の仲哀天皇の急死(200年)後、住吉大神の神託により、お腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま海を渡って朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻めた。新羅は戦わずして降服して朝貢を誓い、高句麗・百済も朝貢を約したという(三韓征伐)。
渡海の際は、お腹に月延石や鎮懐石と呼ばれる石を当ててさらしを巻き、冷やすことによって出産を遅らせたとされる。月延石は3つあったとされ、それぞれ・・・
◎長崎県壱岐市
◎京都市の月読神社
◎福岡県糸島市の鎮懐石八幡宮
に奉納されたと言われている。その帰路、筑紫の宇美で応神天皇を出産し、志免でお紙目を代えたと伝えられ、他にも壱岐市の湯ノ本温泉で産湯をつかわせたなど、九州北部に数々の伝承が残っており、九州北部に縁の深い人物であったと推測される。
神功皇后が三韓征伐の後に畿内に帰るとき、自分の皇子(応神天皇)には異母兄にあたる香坂皇子、忍熊皇子が畿内にて反乱を起こして戦いを挑んだが、神功皇后軍は武内宿禰や武振熊命の働きによりこれを平定したという。
この時代は、長期間にわたって天皇が空位のままだったため、明治時代以前は神功皇后を天皇(皇后の臨朝)とみなして15代の帝と数えられていたが、大正十五(1926)年十月の詔書により、歴代天皇から外された。江戸時代から実在の人物かどうか様々な論考があったが、明治から太平洋戦争敗戦までは学校教育の場では実在の人物として教えていた。現在では実在説と非実在説が並存している。
『日本書紀』において、巻九に神功皇后摂政「66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」として、中国晋の文献における倭の女王についての記述が引用されている。このため江戸時代までは、卑弥呼が神功皇后であると考えられていた。しかしながらこの年は266年で卑弥呼はすでに死去しており、この倭の女王は台与の可能性が高いとされている(ヤマト王権の項など参照)。また、これとは別に、直木孝次郎は、斉明天皇と持統天皇がモデルではないかとの説を唱えている。
神功皇后を卑弥呼や台与と同じような巫女王であったとする見方もある。住吉三神とともに住吉大神の一柱として、また応神天皇とともに八幡三神の一柱として信仰されるようになる。大分県の宇佐神宮、大阪府大阪市の住吉大社をはじめ、福岡県福津市の宮地嶽神社、福岡県大川市の風浪宮など、いくつかの神社の祭神となっている。所縁ある福岡市の香椎宮や筥崎宮、福岡県宇美町の宇美八幡宮、壱岐市の聖母宮でも祀られている。
【三韓征伐(さんかんせいばつ)】
『日本書紀』に記載されている、仲哀天皇の后で応神天皇の母・神功皇后が行ったとされる新羅出兵を指す。新羅が降伏した後、三韓の残り二国(百済、高句麗)も相次いで日本の支配下に入ったとされるためこの名で呼ばれるが、新羅征伐と言う場合もある。
南北朝末期の『太平記』巻三十九「神功皇后攻新羅給事(しらぎをせめたまうこと)」では、話の筋は『愚童訓』と変わりないが「三韓の夷(えびす)」という語が新たに登場し、その三韓は同時代の高麗と理解されている。
関連ログ/Discovery! 鞆の浦:神功皇后(じんぐうこうごう)
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10857044808.html
神功皇后伝説の誕生/前田 晴人

¥2,940
Amazon.co.jp
神功皇后を読み解く/山田 昌生
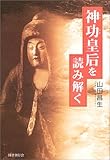
¥2,625
Amazon.co.jp
神功皇后は実在した―その根拠と証明/後藤 幸彦

¥2,100
Amazon.co.jp
女龍王神功皇后〈上〉 (新潮文庫)/黒岩 重吾

¥740
Amazon.co.jp
女龍王神功皇后〈下〉 (新潮文庫)/黒岩 重吾

¥740
Amazon.co.jp
倭の正体―見える謎と、見えない事実/姜 吉云

¥1,575
Amazon.co.jp