【考察】魚島/浮鯛現象
鞆の浦の東に広がる広大な燧灘(ひうちなだ)は、瀬戸内海で最も広い海域で、深度も深く、海底には岩礁が広がり全国有数の真鯛(桜鯛)の産卵地だ。毎年春には真鯛が産卵のため集まり、五月の最盛期には群れ集まった真鯛が島のように見えることから「魚島」と呼ばれる浮鯛現象が起こった。
【真鯛(まだい)/Red seabream】
◎全長:大型のもので120cmに達する。食用として流通する個体は30-70cm程度。
◎生息:北海道以南から南シナ海北部までの北西太平洋に分布するが、奄美群島・沖縄諸島沿岸には分布せず。漁獲量は東シナ海・瀬戸内海・日本海の順に多く、太平洋側では南ほど多い。
◎産卵期:2-8月で、温暖な地域ほど早く、成魚はこの時期になると沖合いの深みから浅い沿岸域に移動する。
卵は直径0.8-1.2mmの分離浮性卵で、海中を漂いながら発生する。マダイは卵や稚魚を保護しないため、卵や稚魚のほとんどが他の動物に捕食される。
稚魚は浅い海の砂礫底、岩場、藻場などで生活し、小動物を捕食しながら成長する。生後1年で全長約15cmに成長、2-3年で浅場を離れて深みに移る。
◎寿命:20-40年程
◎特徴:肉食性。小魚、甲殻類、頭足類、貝類など小動物を幅広く捕食。頑丈な顎と歯で、エビやカニの硬い殻も噛み砕いて食べてしまう。紫褐色を帯びた光沢のある淡紅色は、エビを捕食するためと考えられている。口の中には上顎に2対、下顎に3対の鋭い犬歯があり、その奥に2列の臼歯があり、青い小斑点が散在する。若魚では体側に5本の不明瞭な横縞が出るが、成魚ではこの横縞がなくなる。成魚は水深30-200mの岩礁や砂礫底の底付近に生息し、群れを作らず単独で行動する。
◎こぼれ話:徳川家康が死去した原因は、鯛の天ぷらにあたったためという説もある。
鯛は脂肪分も少なく、組織が緻密で「イノシン酸」を含んでいるため、腐敗の進行が遅く、味が劣化しにくい魚です。 そこで「腐っても鯛」ということわざが生まれました。新鮮なうちに、頭の後ろに包丁をいれて瞬時に命を絶つ「活け締め」、尻尾に深く包丁をいれる「血抜き」、折り曲げて脊髄の神経を断絶するなどの処理で、身の活きを長く保つことができます。
その他。「海老で鯛を釣る」「鯛の尾より鰯の頭」などの諺や、「鯛やヒラメの舞い踊り」というように、しばしばおめでたい言葉に使われる縁起の良い魚。
また、落語「鯛」では、料理屋の生簀に捕まった鯛の物語。主人公の鯛が生簀の中で20年も無事だった鯛「ぎんぎろ」から生簀の中でなんとか長生きする方法を学ぶ。という演目や、それに似た歌謡曲「泳げ鯛焼きくん」などがある。
【魚島/浮き鯛現象】
一説には、神功皇后が旅をした時、船の周りに集まってきた鯛に酒を注ぐと、酒に酔って浮かんできました。そのため、春になると、鯛が酔ったように浮かんでくるという伝承があります。これは、海底が崖になっている地形で、速い潮の流れがあるところでみられるといいます。鯛が集まりすぎて酸欠になるため起こるといいます。近年まで、瀬戸内海のあちこちでみられました。
私の見解では・・・
海中に生息するすべての魚は流れに逆らって泳ぎます。鯛は産卵時期以外は単独で行動しますが、産卵時には群れ(集まり)ます。酸欠状態も一理ありますが、海中ではダウン・カレント(上から下へ流れる海流)、アップ・カレント(下から上へ流れる海流)という現象が起きます。温かい海水は冷たい海水のほうに向かって流れるため、深度が深い海域ではこの現象がよく起こります。ダウン・カレントでは、ダイバーの吐いた空気(泡)が海底に向かっていき、しばらくして泡は上昇します。
このダウン・カレントにて、群れた鯛が(海流に逆らって泳ぐため)一斉に急上昇し、群れ固まっているからそのまま海面まで直行、肺が破れてしまう現象と考えています。
__________
【観光鯛網】
◎開催期間:2011年5月1日(日)~5月22日(日)
5月28日(土)・29日(日)雨天決行(荒天時中止あり)
◎開催場所:福山市鞆町仙酔島田の浦(仮設桟橋より出港)
◎開催時間:平日(月~土)13:30~
日・祝10:30~/13:30~
◎所要時間:約1時間30分
◎料金:大人(高校生以上)3,000円
小・中学生1,500円
◎お問合せ:福山市観光協会/TEL(084)926-2649
◎関連ログ(2011年5月は“鯛網特集”)
観光鯛網の起源
http://ameblo.jp/tomonoura/entry-10865850260.html
鯛網の起源/村上太郎兵衛義光と当納屋忠兵衛
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867892235.html
大漁節/観光鯛網
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867890576.html
大正/鞆町長・横山運治と森下仁丹
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867889856.html
森下仁丹創業者/森下 博
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10161693060.html
森下仁丹創業者/森下 博
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10161693060.html
大正十(1921)年、出郷以来39年ぶりに郷土・鞆の浦に錦を飾る。鞆町では一般町民一人も漏れなく、森下博の施された恩恵に対し、歓迎した。
大正十三(1924)年五月、観光鯛網はじまる。同年、憧れの福沢諭吉に次いで、第二回「日本広告大賞」を受賞した。
観光鯛網のすべて
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867887025.html
【考察】魚島/浮鯛現象
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867889056.html
※大人気!鞆の浦検定の【考察】シリーズ!
第四回 全国一斉 鞆の浦検定/開催延期のお知らせ
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10843510752.html
第四回 全国一斉 鞆の浦検定
『日東第一形勝』呼称300年の歴史~山紫水明處~
300年前、朝鮮通信使が鞆の浦に訪れた重陽の節句(菊の日)に・・・
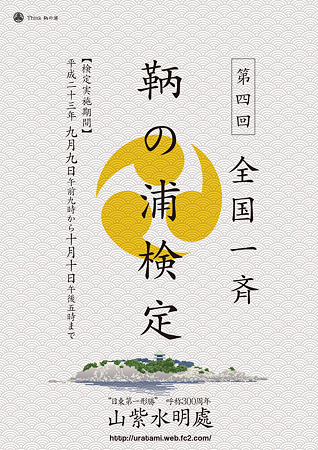
第四回 全国一斉 鞆の浦検定POSTER posted by (C)鳶眼
◎受検期間:平成23年9月9日(金)9時~10月10日(月・祝)17時まで
◎開催場所:鞆の浦及びインターネット(PDF)で問題用紙配布
※鞆の浦での配布は9月10日(土)予定
http://uratami.web.fc2.com/
__________
鞆の浦を旅する旅人に贈る、
旅好きな制作者が作る鞆の浦年代記。
鞆の浦二千年の歴史を紐解く・・・・

“tomonoura”というURLのアメブロです
※注:これから鞆の浦を旅する方々に向けたブログですので、写真は極力少なめに製作しております。
これは、実際に鞆の浦に旅行していただいてから、五感で感じていただいたほうが良いのではないか?という制作者の配慮です。
どうしても、先に写真が見たい!という方のために
写真書庫は『鞆の浦写真館』
http://photozou.jp/community/show/1926
__________
『鞆の浦いいもの再発見!/Discovery! 鞆の浦』
◎みんなで考えよう「まちづくり」
一人百歩の前進よりも、百人一歩の前進を!*
【鞆のための「まちづくり書籍」一覧】
※画家/(故)藤井軍三郎さんが、遺してくれた言葉です
<ソース先:2008.10.29/鞆検日記 総括>
自然と利便性への追求よりも
「そこに住む人々の未来」だけを優先した鞆(とも)の浦検定
架橋埋立計画に賛成している人も、反対している人に対しても
勝者・敗者を出さない方法論
見出すべき答えが同じであるのならば、
余計な妄想を捨てれば解決の道は見えてくる
そこに住むすべての人々がファクターなのだから
多くの良い出会いがあり、
また少しの誹謗中傷を受けた
それにより、本物と偽物の区別ができるようになった
という見解に基づき、余分な物(偽物)は排除した
◎鞆検日記/第1話
◎鞆検日記/第2話
◎鞆検日記/第3話
◎鞆検日記/第4話
◎鞆検日記/第5話
◎鞆検日記/第6話
◎鞆検日記/第7話
◎鞆検日記/第8話
◎鞆検日記/第9話
◎鞆検日記/第10話
◎鞆検日記/第11話
◎鞆検日記/第12話
◎鞆検日記/総括
【番外編】
◎鞆検/主催者からのお願い
◎鞆検総括
◎鞆検<今後の運営予定>
郷土へのPay It Forward<恩送り>の全容がここに・・・
◎鞆の浦検定が協賛金品を募集しない理由
【真鯛(まだい)/Red seabream】
◎全長:大型のもので120cmに達する。食用として流通する個体は30-70cm程度。
◎生息:北海道以南から南シナ海北部までの北西太平洋に分布するが、奄美群島・沖縄諸島沿岸には分布せず。漁獲量は東シナ海・瀬戸内海・日本海の順に多く、太平洋側では南ほど多い。
◎産卵期:2-8月で、温暖な地域ほど早く、成魚はこの時期になると沖合いの深みから浅い沿岸域に移動する。
卵は直径0.8-1.2mmの分離浮性卵で、海中を漂いながら発生する。マダイは卵や稚魚を保護しないため、卵や稚魚のほとんどが他の動物に捕食される。
稚魚は浅い海の砂礫底、岩場、藻場などで生活し、小動物を捕食しながら成長する。生後1年で全長約15cmに成長、2-3年で浅場を離れて深みに移る。
◎寿命:20-40年程
◎特徴:肉食性。小魚、甲殻類、頭足類、貝類など小動物を幅広く捕食。頑丈な顎と歯で、エビやカニの硬い殻も噛み砕いて食べてしまう。紫褐色を帯びた光沢のある淡紅色は、エビを捕食するためと考えられている。口の中には上顎に2対、下顎に3対の鋭い犬歯があり、その奥に2列の臼歯があり、青い小斑点が散在する。若魚では体側に5本の不明瞭な横縞が出るが、成魚ではこの横縞がなくなる。成魚は水深30-200mの岩礁や砂礫底の底付近に生息し、群れを作らず単独で行動する。
◎こぼれ話:徳川家康が死去した原因は、鯛の天ぷらにあたったためという説もある。
鯛は脂肪分も少なく、組織が緻密で「イノシン酸」を含んでいるため、腐敗の進行が遅く、味が劣化しにくい魚です。 そこで「腐っても鯛」ということわざが生まれました。新鮮なうちに、頭の後ろに包丁をいれて瞬時に命を絶つ「活け締め」、尻尾に深く包丁をいれる「血抜き」、折り曲げて脊髄の神経を断絶するなどの処理で、身の活きを長く保つことができます。
その他。「海老で鯛を釣る」「鯛の尾より鰯の頭」などの諺や、「鯛やヒラメの舞い踊り」というように、しばしばおめでたい言葉に使われる縁起の良い魚。
また、落語「鯛」では、料理屋の生簀に捕まった鯛の物語。主人公の鯛が生簀の中で20年も無事だった鯛「ぎんぎろ」から生簀の中でなんとか長生きする方法を学ぶ。という演目や、それに似た歌謡曲「泳げ鯛焼きくん」などがある。
【魚島/浮き鯛現象】
一説には、神功皇后が旅をした時、船の周りに集まってきた鯛に酒を注ぐと、酒に酔って浮かんできました。そのため、春になると、鯛が酔ったように浮かんでくるという伝承があります。これは、海底が崖になっている地形で、速い潮の流れがあるところでみられるといいます。鯛が集まりすぎて酸欠になるため起こるといいます。近年まで、瀬戸内海のあちこちでみられました。
私の見解では・・・
海中に生息するすべての魚は流れに逆らって泳ぎます。鯛は産卵時期以外は単独で行動しますが、産卵時には群れ(集まり)ます。酸欠状態も一理ありますが、海中ではダウン・カレント(上から下へ流れる海流)、アップ・カレント(下から上へ流れる海流)という現象が起きます。温かい海水は冷たい海水のほうに向かって流れるため、深度が深い海域ではこの現象がよく起こります。ダウン・カレントでは、ダイバーの吐いた空気(泡)が海底に向かっていき、しばらくして泡は上昇します。
このダウン・カレントにて、群れた鯛が(海流に逆らって泳ぐため)一斉に急上昇し、群れ固まっているからそのまま海面まで直行、肺が破れてしまう現象と考えています。
__________
【観光鯛網】
◎開催期間:2011年5月1日(日)~5月22日(日)
5月28日(土)・29日(日)雨天決行(荒天時中止あり)
◎開催場所:福山市鞆町仙酔島田の浦(仮設桟橋より出港)
◎開催時間:平日(月~土)13:30~
日・祝10:30~/13:30~
◎所要時間:約1時間30分
◎料金:大人(高校生以上)3,000円
小・中学生1,500円
◎お問合せ:福山市観光協会/TEL(084)926-2649
◎関連ログ(2011年5月は“鯛網特集”)
観光鯛網の起源
http://ameblo.jp/tomonoura/entry-10865850260.html
鯛網の起源/村上太郎兵衛義光と当納屋忠兵衛
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867892235.html
大漁節/観光鯛網
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867890576.html
大正/鞆町長・横山運治と森下仁丹
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867889856.html
森下仁丹創業者/森下 博
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10161693060.html
森下仁丹創業者/森下 博
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10161693060.html
大正十(1921)年、出郷以来39年ぶりに郷土・鞆の浦に錦を飾る。鞆町では一般町民一人も漏れなく、森下博の施された恩恵に対し、歓迎した。
大正十三(1924)年五月、観光鯛網はじまる。同年、憧れの福沢諭吉に次いで、第二回「日本広告大賞」を受賞した。
観光鯛網のすべて
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867887025.html
【考察】魚島/浮鯛現象
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10867889056.html
※大人気!鞆の浦検定の【考察】シリーズ!
第四回 全国一斉 鞆の浦検定/開催延期のお知らせ
http://ameblo.jp/thinktomo/entry-10843510752.html
第四回 全国一斉 鞆の浦検定
『日東第一形勝』呼称300年の歴史~山紫水明處~
300年前、朝鮮通信使が鞆の浦に訪れた重陽の節句(菊の日)に・・・
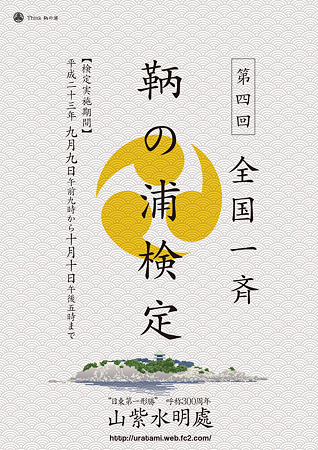
第四回 全国一斉 鞆の浦検定POSTER posted by (C)鳶眼
◎受検期間:平成23年9月9日(金)9時~10月10日(月・祝)17時まで
◎開催場所:鞆の浦及びインターネット(PDF)で問題用紙配布
※鞆の浦での配布は9月10日(土)予定
http://uratami.web.fc2.com/
__________
鞆の浦を旅する旅人に贈る、
旅好きな制作者が作る鞆の浦年代記。
鞆の浦二千年の歴史を紐解く・・・・

“tomonoura”というURLのアメブロです

※注:これから鞆の浦を旅する方々に向けたブログですので、写真は極力少なめに製作しております。
これは、実際に鞆の浦に旅行していただいてから、五感で感じていただいたほうが良いのではないか?という制作者の配慮です。
どうしても、先に写真が見たい!という方のために
写真書庫は『鞆の浦写真館』
http://photozou.jp/community/show/1926
__________
『鞆の浦いいもの再発見!/Discovery! 鞆の浦』
◎みんなで考えよう「まちづくり」
一人百歩の前進よりも、百人一歩の前進を!*
【鞆のための「まちづくり書籍」一覧】
※画家/(故)藤井軍三郎さんが、遺してくれた言葉です
<ソース先:2008.10.29/鞆検日記 総括>
自然と利便性への追求よりも
「そこに住む人々の未来」だけを優先した鞆(とも)の浦検定
架橋埋立計画に賛成している人も、反対している人に対しても
勝者・敗者を出さない方法論
見出すべき答えが同じであるのならば、
余計な妄想を捨てれば解決の道は見えてくる
そこに住むすべての人々がファクターなのだから
多くの良い出会いがあり、
また少しの誹謗中傷を受けた
それにより、本物と偽物の区別ができるようになった
という見解に基づき、余分な物(偽物)は排除した
◎鞆検日記/第1話
◎鞆検日記/第2話
◎鞆検日記/第3話
◎鞆検日記/第4話
◎鞆検日記/第5話
◎鞆検日記/第6話
◎鞆検日記/第7話
◎鞆検日記/第8話
◎鞆検日記/第9話
◎鞆検日記/第10話
◎鞆検日記/第11話
◎鞆検日記/第12話
◎鞆検日記/総括
【番外編】
◎鞆検/主催者からのお願い
◎鞆検総括
◎鞆検<今後の運営予定>
郷土へのPay It Forward<恩送り>の全容がここに・・・
◎鞆の浦検定が協賛金品を募集しない理由

