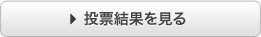ブログネタ:喉あめはスーッと系?フルーティー系?甘い系?
参加中
ブログネタ:喉あめはスーッと系?フルーティー系?甘い系?
参加中私はスーッと系 派!
それでは写真です^^)
11月1日ですけど、マリーゴールドかな^^)
みんなのクチコミが26000000を越えましたけど、大関は遠いです^^)
それでは次回11月18日にお会いしましょう^^)
それではタイトルに戻ります^^)
報道によると、日本が高度成長の転機を迎えたのは、1971年の米ドル防衛策やそれに続く石油危機のころ。それまでは財政は豊かで、政府は全国で公共事業を行い、手厚い社会保障制度を提供してきたとあります^^)
1971年といえば僕が7歳の頃ですけど、我が家の前の国道が4車線になる工事をしていましたから、まだまだ景気が悪いというような状況ではなかったですね^^)
第一次石油危機(オイルショック)は1973年とありますから、僕は9歳です^^)
トイレットペーパーを母親が世間の母親と同じように買いだめをしていたのを記憶しています^^)
その次が第2次石油危機(オイルショック)で1979年ですけど、僕は15歳です^^)
株価を見ると日経平均株価が約7000円から8000円で、長い目で見るとその後の1万円台に乗る中休みみたいな時期ですね^^)
しかし、高度成長が終わり、70年代後半以降に日本の経済や財政が構造的に変化したことを多くの国民は意識しなかった。この時点で政府が無策であったわけではない。80年代初頭には、経団連名誉会長(当時)の土光敏夫氏を会長に第2次臨時行政調査会が設置され、国鉄や電電公社の民営化など一応の改革は行われた。しかし、土光臨調は「増税なき財政再建」を旗印に掲げながら、肝心な大前提である行政合理化を放置したため、その後の日本に財政赤字体質が定着してしまったとあります^^)
国鉄がJRになり、電電公社がNTTとなって国有が民営化になったのだから、行政の合理化を放置したとまでは言えないのではないかと思います^^)
でも多分筆者はもう一声行政合理化をしなければならなかったという点では同感ですね^^)
それが多分郵政民営化でもあったのだろうと思います^^)
さらにその上で合理化をと考えれば、最近行政も派遣社員を使っていますから、人件費の抑制も行われています^^)
だから最終的には公務員の賃下げというところになるのではと考えますが、限度はありますね^^)
その結果が今日の日本の姿だ。先進国で突出した財政赤字累積国になってしまった。政府は今後、社会保障と税の一体改革に取り込もうとしているが、同時に大きな課題はかつてのように中央から資金を回せなくなった地方を、いかに活性化するかであるとあります^^)
地方活性化のために道州制を導入しなければという思いがありましたけど、線引きだけでもなかなか難しいと先輩と話していて思いました^^)
山口県は九州に近い長門側は北九州というか福岡県とくっ付いた方が良いんですけど、広島県に近い周防と言うか岩国あたりは広島県とくっ付いた方が便利だし良いと言った具合です^^)
外にも活性化策はあると思いますけどね^^)
結論を先に述べれば、今後はそれぞれの地域社会が自立して生きていくよりほかはないのだ。しかし、地方の主な産業は農林漁業であることが多く、都市部に先がけて過疎化が進む。地方は果たしてこれから生きていけるのかとあります^^)
TPPで例外のない無関税になれば、地方の主な産業の農林漁業は壊滅しますから、地方には未来は無いように思えますね^^)
世界中から引っ張りだこの美味しい果物を作る農家があっても一つの都道府県の農家を食べさせることは不可能ですね^^)
筆者は条件さえ整えば可能と考える。その条件とは地域主権という表現で議論されているが、中央の権限を地方に大胆に委譲することである。すなわち地方行政に最大限の自由を与えるのだとあります^^)
道州制にしなくても、今の形態で地方に権限と財源を委譲することは賛成です^^)
ただし、中央が心配なら国が何らかの関与をして地方自治体の破綻をしないようにチェックを入れることは必要ではないかと思います^^)
環境は整っている。日本は世界の成長地帯である東アジアの中心的存在。先進国としての社会基盤も整備されている。これからは新興国も成長し産業技術力を競う時代だが、日本はこの面で一日の長がある。農業でも全地球測位機能付きの人工衛星を活用して、無人農機で田畑を耕す時代を迎えようとしていることを強調しておきたいとあります^^)
筆者が言っていることは分かりますけど、家から田畑まで移動しないといけないし、田畑でも曲がりくねった場所もあって、耕運機がひっくり返ることもあるのに、人工衛星の耕運機が活躍するにはまだまだ越えなければならない問題がたくさんありますね^^)
それに無人作業する機械が何千万円もしたら、農業を辞めたほうが儲けですね^^)
無人の漁船が漁をして魚を釣って帰ってくるのも今は夢物語だと思います![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()