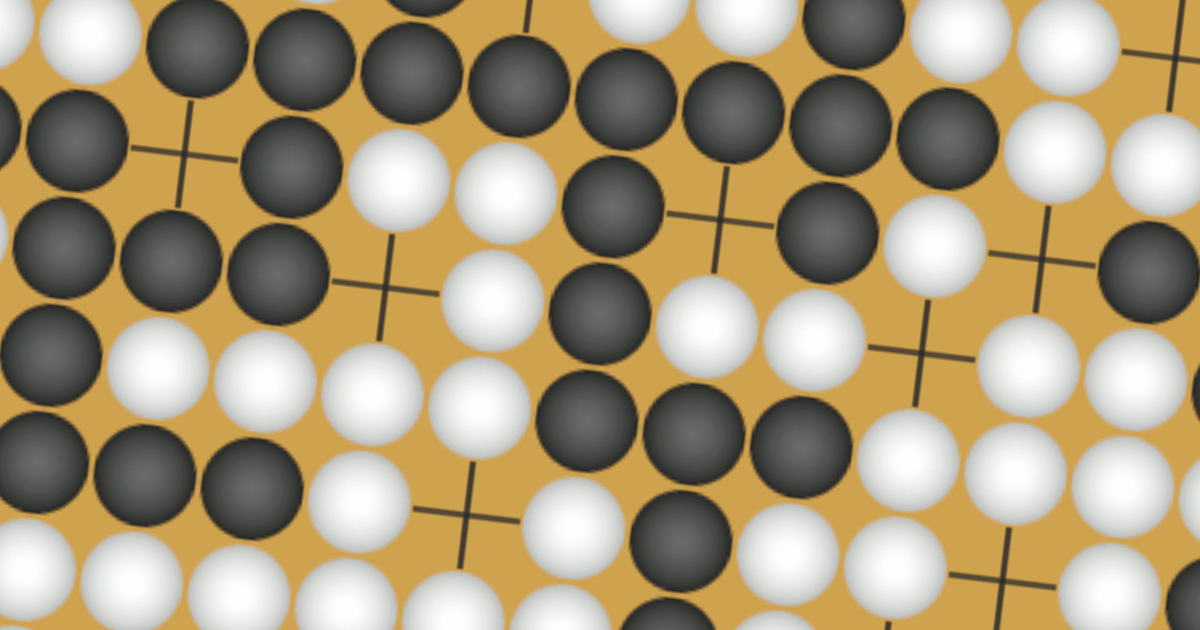「ここに打つのが最善かは、場合によります」
という解説を聞く度に、
曖昧すぎる!
はっきりした正解を聞いて私は安心したいのよ〜
と思ったものでしたが
そもそも場合の数が天文学的に多いから、実戦では
その1つ石の位置が1目ズレているだけ、
そこに1つ石があるかないかだけで、
無数の違いが生じてくる。
だから曖昧にならざるを得ない、
とある時、ふと気付きました。(急にシナプスが繋がった)
初期条件のほんのわずかのズレが、
かけ離れた違いを生んでいく、カオス理論みたいな感じ?
「将棋は人が作った最高のゲーム。碁は神様が作った最高のゲーム」
といった囲碁好きの将棋棋士もいます。
プロでもわかりません。
わからないから面白いのです。
そんなわからない、広い盤面の中から打つ手を探すのはたいへんです。
いい手を浮かびやすくするためにも、筋をよくしておくのが重要です。
高尾紳路 ー手筋の基本ー あとがきより
ーーーーーーーー
息子訓(指導碁)
・石が繋がっているかどうかを見て
・上手は返す必要がない手と判断すると、別のところへ打つ(上手の考えは僕にもわからない)
・囲碁は会話、相手を無視しちゃいけないよ
(上手は外交のように愛想よく相槌を打ちながら、狙いは全く別にあったりするんだ←こわい)
棋譜並べ(50手覚える)
大会名: 木谷・呉打込み十番碁第4局
対戦日: 1940/06/12-14
黒番: 木谷実 (七段)
白番: 呉清源 (七段)
結果: B+1
10手くらいずつ、5日かけて50手覚えました。
「絶対無理」と思いましたが、覚えたら
息子に手の意味(こう考えて打っている)を教わることにして、
ストーリーが頭に入るといけそう。
リストの曲を暗譜するような感じ?(弾けるかどうかは別)
<徒然>
ネガティブ・ケイパビリティという言葉を最近知りました。