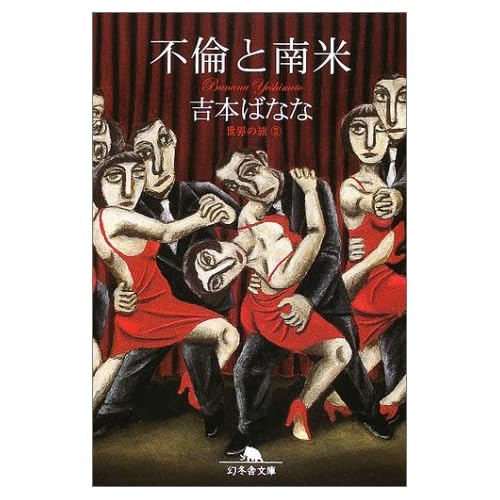
南米も計画しょぅカナ
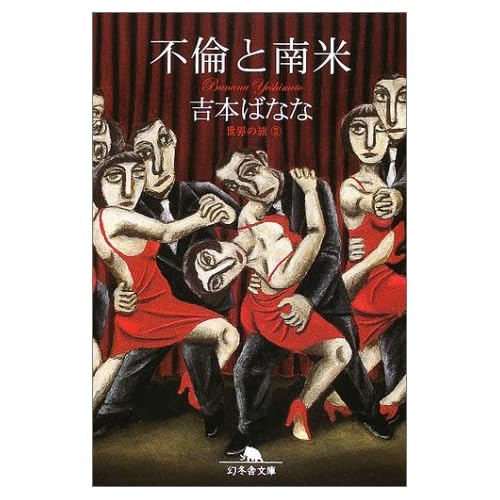

長い人生のなかで意義深い日々がほんの一瞬だったことを知るたびに驚きを覚える。
未来にとって重要な意味を持つ日々でありながら、それと知らぬうちに過ぎ去ってしまうのだ。
しかしそうした日々をもたらした人を忘れることはない。
エジプトからギリシャへ向かう飛行機の中で、ものすごい睡魔に襲われながらも読破してしまいました。
この物語は背景がすごく素敵。19世紀中葉、まだタイがシャム王国だった頃のお話。
周りのアジア諸国の植民地化が進む中で、それを拒み続けた王国。
オリエンタルでミステリアスな文化の背景には、古い伝統やしきたりなど進歩を妨げる根強い頑固さがある。
そんな王国に乗り込んだ一人のイギリス人女性アンナと王様の物語。
人種も文化も習慣も、何もかも違うのに惹かれあう二人。
いくら文化の壁を乗り越え現地の人々と打ち解けたとしても、当時の王国に大英帝国民であるアンナの居場所はない。
いくら惹かれても、イギリス人であるアンナと神の化身と崇められる王様は結ばれることはできない。
人間ておかしな生き物だと思う。
ただの生き物なのだから、好きな場所へ行き、好きな物を食べ、好きな人と好きなことだけして過ごせば人生は勝手に終わっていくはずなのに。
自分達が勝手に作ったルールがそれを邪魔をする。
お金。国境。人種。法律。宗教。
例えば動物だったら、そんなものナシに生きていけるのに。
法や宗教に逆らって、自分の意思と愛を貫いたタプティムは拷問されて処刑されてしまう。
「恐れるな、タプティム・・・・しょせんこの世は苦界だ・・・・。」
彼女に苦しみを与えるのも、彼女を救うのも、彼女が信じていた仏教だった。
皮肉。なんて皮肉。
でもきっと彼女たちのような強い人が国を少しずつ変えていったんだろう。
王国に大きな影響を及ぼし、国民達に受け入れられたにもかかわらずイギリスへ帰ることしか選択肢がなかったアンナ。
結局イギリスに訪問できずに亡くなってしまった王様。
このストーリーは実話だし、これだけ本になって映画化されて後の人々に感銘を与え記憶に刻まれていくなら美しい物語なんだと思う。
自分を犠牲にしても、祖国を守り家族を守り伝統と愛国心と宗教に従い、それを生涯貫いた登場人物たちはとても強い。
感動して本を閉じたらアテネ到着の10分前だった。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
アテネに着いたら留守番電話の通知が来た。
でもナゼか海外から留守電は聞けず。
電話も知らない番号。しかも家電。
![]() (誰だろう??内定先???かけてみょー。)
(誰だろう??内定先???かけてみょー。)
![]() プルルル・・・ 「あっもしもし?」
プルルル・・・ 「あっもしもし?」
![]() 「hello?]
「hello?]
![]() (?!英語??誰!!) 「hello?? I got messsage from this number...??」
(?!英語??誰!!) 「hello?? I got messsage from this number...??」
![]() 「yeah yeah I know, how are you??」
「yeah yeah I know, how are you??」
![]() 「sorry?? Whos speaking???」
「sorry?? Whos speaking???」
・・・・・・・・
![]() 「Teddy is speaking~♪♪」
「Teddy is speaking~♪♪」
・・・・・・・・なんだょ・・・・本気で誰だか分かんなかった。。。![]()
![]()
その後彼はやたらご機嫌で、私の旅の話を興味深そうに聞いてくれて、
もぅそのセクシーでキュートな声を聞くだけで私はもう彼に会いたくて仕方がなくなっちゃぅ。
![]() 「トルコは海に囲まれてて、オリエンタルでヨーロピアンで素敵すぎたの。
「トルコは海に囲まれてて、オリエンタルでヨーロピアンで素敵すぎたの。
Teddyと一緒に行ったらすごく素敵だと思う!」
![]() 「へぇー。すごぃねー。リカちゃんとそんなとこ行ったら盛り上がってエッチなことばっかりしちゃいそぅだけどね。」
「へぇー。すごぃねー。リカちゃんとそんなとこ行ったら盛り上がってエッチなことばっかりしちゃいそぅだけどね。」
![]() 「・・・・・・・ぅん
「・・・・・・・ぅん![]() 」
」
国際電話でも青汁鍋屋でもノーティでラブラブな会話。
親友はバカップルと呆れてるし、でも聖母は 「二人を見てるとハッピーになれる」 って言ってくれる。
私はあの旅の中、Teddyからメールや電話をもらう度に二人一緒にいることを想像してた。
とても近ぃ価値感とノリと、Teddyの方がうんと上手な英語と、何よりも二人っきりで一緒に過ごせる幸せ。
新しいものを見て、感じて、微笑み合える嬉しさ。
私は何百枚も写真を撮ったけど、Teddyは一枚一枚見ながら
![]() 「すごぃねー。 いーなー。 リカちゃん、一緒に行こうよ!!」
「すごぃねー。 いーなー。 リカちゃん、一緒に行こうよ!!」
とかいちいち反応してくれて、ワイン飲みながらムール貝はとても美味しくて、
Teddyが待っていてくれた青ぃイルミネーションもとてもキレイで、
それもすべて彼と一つになりたいって欲望を高める媒体になっているようなもので、
私はほとんど彼とこの時間を共有するためだけに旅行に行ってきたような感覚になってしまう。
本当に、どこか行っちゃえたらいいのにね。
毎日海と本と音楽を楽しんで、盛り上がったら一つになって
疲れたら一緒に眠ればいい。
エラそぅなおっさん![]() 「へぇー、4年生かー。キミの将来の夢は?」
「へぇー、4年生かー。キミの将来の夢は?」
![]() 「ぅぅん・・・・・
「ぅぅん・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・好きな人と世界一周して、
いろいろなことに感動して、ずっと笑ってることです。」
おっさん![]() 「いい夢じゃなぃか!そういう好きな人はいるの?
「いい夢じゃなぃか!そういう好きな人はいるの?
うん、そう強く思っていれば人間そうなって実現していくものだから
大事に思っているといいよ!」
・・・・・・・・・・おっさん・・・・・・・・・(ノДT)![]()
![]()
ありがとう。
障害は多いし、叶うことはないかもしれないけど、私大事に思い続けるょ。
トルコのカッパドキアの写真。
キノコの形をした岩が世界遺産で有名なのです。
英語ではpe○is valleyとぃぅらしく、それを説明したらTeddyはお気に召したみたぃ![]()
ぷ(´∀`)![]()
"You are all a lost generation."
あなたたちはみんな、自堕落な世代なのよね。
-ガートルード・スタイン
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
小説にはいろんな種類があると思う。
人を楽しませるもの。
人に学ばせるもの。
人を考えさせるもの。
これは完全に人に考えさせて悩ませるものだと思う。
この文学的歴史に大きな業績を残すヘミングウェイの作品は、決して愉快なものではない。
特に盛り上がりというものもないし、結末といった結末もない。
私の好きなタイプの小説ではない。
登場人物たちは何の目的もなしに現実から目を背け、酒に溺れる日々。
問題は解決されずに放置されたまま、酔っ払い笑っていればその日は終わる。
時代背景は第一次世界大戦後のパリ。
禁酒法を免れてヨーロッパに渡ったアメリカ人の若者がたくさんいた。
戦争でアメリカは勝利を収め自らも生還したにもかかわらず、彼らは多くの傷を負い祖国にはいれなくなった。
肉体的な傷だけでなく精神面のダメージは彼らの人生の根本的な何かを奪ってしまった。
ハッキリ言ってこの小説を読んでいても全く面白くない。
登場人物たちはいつも酔っ払い、とるにたらないことを話しているだけだし
いつも酔ってるから具体的な感情の起伏も伺えないし、
すべてを中途半端に投げ出すのでイライラさえ覚える。
「とりあえずウイスキーを飲めばいいじゃないか。」
こんな台詞が何度出てくるだろう。
もう少しで本題に近づきそうなところで、彼らは必ず逃げる。
こんな風にこの小説は全然面白くなくて、大きな盛り上がりもない。
何かが変わることもない。
進歩することもない。
良くも悪くも、全く変化しない。
登場人物たちも同じで、感情に起伏がないというかいつも酔っ払っている快楽主義の集まりだし
嫌なこと嫌いな人がいてもそこから目を背けて生活する。
それなのに、
言ってしまえば不愉快にすら感じるこのパリの若者たちの生活が、何となく理解できてしまう。
むしろ分かり過ぎてしまって、ふと泣きそうになってしまったりする。
どうしようもなく酔っ払いで男好きで、ものすごく魅力的なブレッド。
愛する人を傷つけ振り回し、みじめになることしかできない。
本来なら彼と二人、愛に溢れた生活をできるはずなのに、
絶対に解決されない問題のせいで彼と一緒になることはできない。
彼の代わりを求めて結婚したり離婚したり、婚約したり破棄したり。
やっていることは滅茶苦茶。
そして時折やけになって彼に泣きつく。
「こんな話ってないわよね?
あなたを愛していると言ったところで、どうにもならないんですもの。」
「やめましょう、その話をするのは。
いくら話したって、虚しいだけですもの。
あたし、あなたと離れて、遠いところにいってこようと思うの。」
絶対に手に入らないけれど、どうしても欲しいものの近くにいるのは死ぬほどツライことだろう。
だったらいっそ離れてしまった方が楽。
他に目を向けた方が幸せ。
彼女が一つの場所に留まれず、どこへ行き何を楽しんでも満たされないの理解できてしまう。
そして最終的にまた同じ場所に戻ってきてしまうその理由も。
一方、彼女に裏切られ続けるジェイク。
自分に非があるため、何も言えない。
ましてや彼女の不貞の手助けまでしてしまう。
本当に彼女を愛しているのに、彼女の一番求めているものに答えられない辛さ。
生物として彼は死んでしまっているようにすら感じられる。
”眠れぬままに考えていると、思いがあちこちに跳びはねてしまう。
そのうち、ほかのことに的を絞れなくなって、ブレットのことを考え始めた。
すると、それ以外のことはみな頭から消えてしまった。
ブレットのことを考えていると、思いがあちこちに跳びはねることもなくなり、なめらかな波のように動き始めた。
と思うと、突然、ぼくは泣きだしていた。
それからしばらくすると気分が落ち着き、ベットに横たわったまま、電車が通り過ぎて遠ざかってゆく重苦しい音に耳をすましていた。
ほどなく、ぼくは眠りに引き込まれた。”
人間として、生物として根本的なものが欠けてしまっている人生。
自分の希望が叶うことはなく、愛する人を満たすこともできない。
”これでなんとかなるだろう。これでいいのだ。
恋人を旅立たせて、ある男と馴染ませる。
次いで別の男に彼女を紹介し、そいつと駆け落ちさせる。
そのあげくに、彼女をつれもどりにいく。
そして電報の著名には、「愛している」と書き添える。
そう、これでいいのだ。
ぼくは昼食をとりにいった。”
何が変わるわけでもないけれど、これが彼のたどり着いた結論だった。
問題を解決するでもなく、逃げるでもなく、ただ受け入れる。
「ああ、ジェイク」 ブレットが言った。
「二人で暮らしていたら、すごく楽しい人生が送れたかもしれないのに。」
ブレットの体がぼくに押しつけられた。
「ああ」 ぼくは言った。
「面白いじゃないか、そう想像するだけで」