プログレは高校時代によく聴いてました。Yes廻り中心で、Bill Bruford繋がりでKing Crimson行ったり、UK行ったり。
その頃、Genesisは「Genesis」というアルバムを出していて、「Mama」や「That's All」などの、その頃のYes(平たくいうと、Owner Of A Lonely Heart)よりも、更にPopsな印象の楽曲を出していました。
高校生という生き物は、恐らく一生のうちで一番耳年増な時代です。つまりは、学習と体験のバランスが一番取れていない。
なわけで、Genesisというバンドがどういうバンドで、ピーター・ゲイブリエルというカリスマが元々仕切っていたバンドで(恐ろしいことに、同時代はSledge Hammerな時代でもあった!)、Yes同様、かつての姿とは大きく違う、みたいな話は学習しているわけです。
ちなみに言うと、その時代のYesは大好きでした。
- ロンリー・ハート/ワーナーミュージック・ジャパン
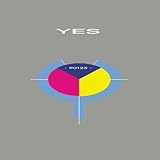
- ¥1,800
- Amazon.co.jp
この作品は、悪いけどよく出来てる。Yesとはクリス・スクワイアのバンドであって、ジョン・アンダーソンのバンドではない、というのがダンナの理解です。そのクリスが、前作の「Drama」(超傑作)でトレバー・ホーンという才能を発掘し、「90125」でトレバー・ラビンというこれまた稀有な才能を発掘した。
また、その時代のKing Crimsonも大好きでした。
- Discipline: 30th Anniversary Edition/Discipline Us
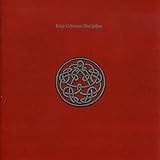
- ¥1,279
- Amazon.co.jp
King Crimsonの全時代の中で、実は一番好きなのがこの時代。スティーヴ・ライヒにインスパイアされたというにはあまりにモロパクリなPhase Guitar。アフリカを意識したリズム・セクション。高校生の知的好奇心を満たすには十分な教科書でした。
さて、本題のGenesisはどうかというと、ダンナがLP盤で買った最後の作品が、実はこれです。
- Seconds Out/Atlantic / Wea

- ¥1,391
- Amazon.co.jp
これは大傑作です。1976~1977のツアーを収録した作品で、当時機材レベルで求められる最高のライブパフォーマンスのひとつだと思います。特に、Firth of Fifthの広がりに圧倒されました。
今回紹介する「Selling England By The Pound」は、1973年、今から40年前の作品です。
Genesisの作品中、「A Trick Of The Tail」とどっちを一位にしようか悩む作品です(この作品についても、いずれ記事にします)。
- Selling England By the Pound/EMI Europe Generic
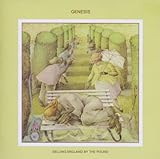
- ¥1,902
- Amazon.co.jp
まずはこの作品のタイトル「イングランドを1ポンド単位で切り売りします(この場合のポンドとは、通貨ではなく重さの単位として)」は、一曲目の「Dancing With The Moonlit Knight」(邦題の「月影の騎士」の由来)から来ています。まずは、この曲について語らざるを得ません。
美しく、激しく、儚く、切ない楽曲です。そして、その歌詞はアイロニーに満ち満ちています。第一節は、恐らくはアーサー王の時代の騎士が"Can you tell me where my country's lies?"と問う場面から始まります。
そして、ナイーブな騎士が"Queen Of Maybe"(恐らくQueen of MayとQueen of Bee(女王蜂)のダブルミーニング)に買収され(もっと言うと買春)、テムズ川が溺死する(!!)、栄光ある英国市民が今やハンバーガーチェーンにようなチープな私欲に満足してしまうほど没落してしまう(食に関しては、それを言う権利はない気がしますが。。。)、そして、英国という島国(つまり船)の船長は「とにかく、踊れ、過去の栄光は全部忘れて踊れ、Moonlit knight(Moonlight Knightではない点に注目)と共に、グリーンシールドスタンプ(日本でいうとブルーチップのようなもの、つまりは消費の象徴)の騎士と踊れ」と叫んでいる。
そんな風に、1970年代のイギリスの情況を嘆く歌詞が、ゲイブリエル独特のシアトリカルな歌唱で謳われます。
そんな感じで、歌詞だけでおなか一杯なのですが、特筆すべきはバンドの演奏力の凄さ。フィル・コリンズのドラムの素晴らしさは溜息が出ます。シンバルワーク、スネアのゴーストノート、いずれもスティーブ・ガッドに匹敵します。タム廻しの大味さで評価を下げている感が否めませんが、変拍子をこれだけ自然に叩ける人は他にはいないでしょう。
そして、「Firth of Fifth」の素晴らしさ。シンフォニック・ロックの原点にして頂点。イントロのピアノからノックアウトですが、"The path is clear though no eyes can see"で広がる景色、365°パノラマな風景が脳裏に浮かびます。スティーヴ・ハケットのギターソロは、全プログレファンの共通認識として、史上最高のソロの一つです。
「The Battle Of Epping Forest」は、今作中最もコミカルな楽曲です。イギリスでも最も古い森、いわば原風景の中で繰り広げられる、ギャング団の抗争。その対置を喜劇として描いており、ゲイブリエル時代のGenesisならではの作品です。
「The Cinema Show」は、フォーキーな第一部(結構きわどい歌詞が特徴)と、トニー・バンクスの歴史的シンセ・ソロが展開する第二部に分かれています。特に、Arp Pro Soloistを最大限使いこなしたソロは素晴らし過ぎます。一聴する限りでは非常にシンプルなソロを弾いている風に聞こえますが、実際弾いてみると結構難しい。更には、一つのソロの中でこれだけ目まぐるしく音色を変えるのも極めて珍しいです。
最終曲の「Aisle of Plenty」で、「Dancing With The Moonlit Knight」のメロディに戻りつつ、消費社会に乗っ取られた後の世界を、これまた皮肉たっぷりに歌ってフェードアウトしていきます(つるかめランドのTescoやCo-opが出てきたり)。
プログレッシブロックの頂点の一つであり、今聴いても色褪せない稀有の作品であり、何より美メロな作品であることが素晴らしい。
「一家に一枚」の作品の一つであることは、間違いないでしょう。