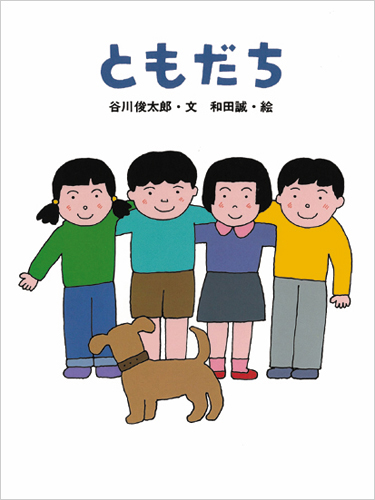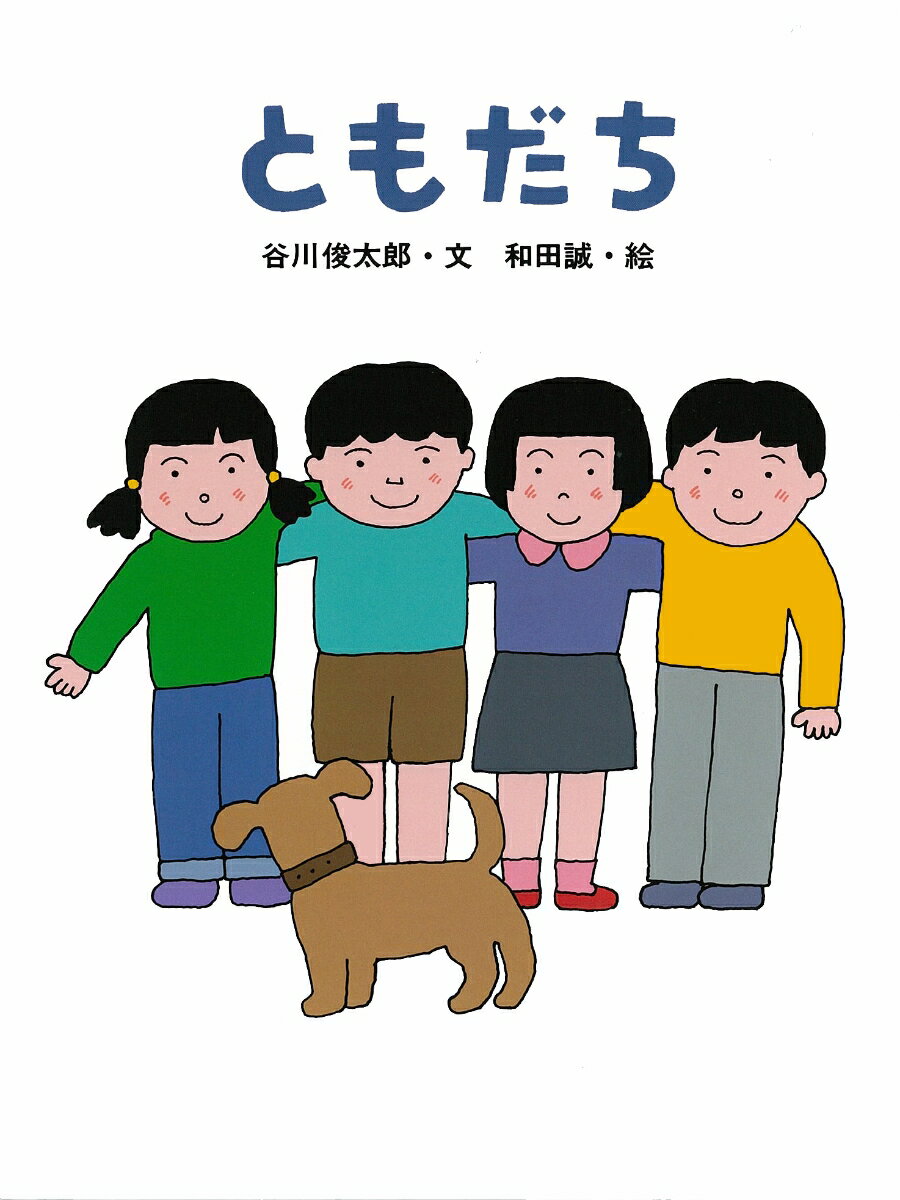本記事タイトルは、先週夜眠る前に息子(8)がボソっと言った言葉です。
そりゃ息子がクラスに友達たくさんいるとは思っていなかったけど、休み時間にスクラッチの雑談をする相手くらいはいるようだったので、私は友達関係を今までさほど心配していませんでした。
なので、息子が友達いない事に悩んでいたというのは青天の霹靂です
でも。今週小学校の授業参観に行って、なぜ息子が友達関係に悩み始めたのか分かってきました。
授業参観の最後に、詩の群読と歌の斉唱がありました。
詩は谷川俊太郎氏の「ともだち」、歌は「ビリーヴ(作詞・作曲 杉本竜一氏)」でした。
「例えば君が傷ついて〜![]() 」で始まる曲ですね。
」で始まる曲ですね。
以下、谷川俊太郎氏の「ともだち」について絵本ナビより引用いたします![]()
「ともだちって」
かぜがうつっても へいきだっていってくれるひといっしょに かえりたくなるひと
「ともだちなら」
いやがることを するのは よそう
「ひとりでは」
もてない おもいものも ふたりでなら もてる
つまらないことも ふたりでやれば おもしろい
ともだちってなんだろう・・・例えば子どもたちがそんな風に思っていたとしたら、こんなにも具体的にわかりやすく教えてくれる答えはないですよね。
谷川俊太郎さんの詩に、和田誠さんのほのぼのとした絵が子ども達の心にぐっと近づいてきます。
幼児〜1年生の時期は、友達の定義が緩かったんですよね。
例えばドレミファどーなつの「一度会ったら友達で、毎日会ったら兄弟さ![]() 」みたいな。
」みたいな。
(昔のおかあさんといっしょの人形劇の歌詞の一部です。覚えてる方いますかね?)
それが2年生も後半に差し掛かってくると、友達とはただ毎日会って話すだけの関係では無く、お互いに助け合える、励まし合える等、高度な関係性に発展したのでしょう。
うん。今のコテツにはかろうじて話し相手がいたとしても、詩のような助け合える友達を作るのはまだ難しい![]()
次回記事では、一読後、積み上げていた発達関係の本を再読して気付いた事などを書こうと思います。
ここまでお読み下さった方、ありがとうございました![]()