石川英輔・田中優子 共著の「大江戸生活体験事情」(講談社文庫)という本がありまして。
著者両人が江戸時代の生活を出来る限り再現して生活してみるレポートから現代のエネルギー事情を考えようという本。
大江戸生活体験事情 (講談社文庫)/講談社
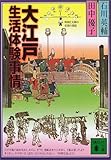
¥560
Amazon.co.jp
これで田中優子さんが筆で文字を書くことについて1章割いていて、筆記具について「現代と江戸時代で最も違うのは筆」「江戸時代の筆は筆の中心に硬い毛を使い、その根元を紙で巻き、さらにそのまわりを柔らかい毛で被う『巻き筆』は主流だった」とある。
その巻き筆を使うと「書くときに腕と手でコントロールできる毛の柔らかさと同時に、硬い毛の弾力を有効に利用できる」そうである。
巻き筆の使い心地について田中さんは「仮名の繊細な線が実に美しくかける」「何ミクロンという単位すら可能ではないのかと思うほど細くかけ、しかも力の入れ具合で自由な弾力が得られる。」とレポしている。
これを読んだ時、昔の人の繊細な筆文字、ぎっしりと細かく「筆」で描かれた書簡などについての謎が氷解した。
現代の、私があのように字を筆で書けないのは、修練もあるけれどまず、「筆」のせいだったのだ。
猛然とその「巻き筆」とやらが欲しくなったが、この本によると現在その「巻き筆」を作っている職人さんは滋賀県の藤野雲平さんという職人さんただ1人で、田中さんは書家の友人の紹介で巻き筆を作ってもらった、とある。
2002年にこの本を読んだ当時は貧乏な陶芸家もどきとしてはそこで諦めた。
紹介で「日本でただ1人」につくってもらわなきゃならないなんてハードル高すぎるじゃないか。
時は流れて2013年。
酔狂にも「写経」を始めた11年後の私は、東急ハンズで1000円ちょっとで買った「写経用筆」の使いにくさに苛立っていた。
使いにくいとその分丁寧に書こうとして自分を見つめるのには良いのかもしれないが、モノつくりという立場からみれば、「弘法だって筆を選ぶ」のだ。
道具で苛立っていては良い仕事はできないのだ。
良い筆が欲しい。
良い筆って、どこで買えるのよ?どんな筆を良い筆っていうのよ??
ふと・「巻き筆」のことを思い出して検索してみた。
・・・・・・あっという間に出てきた。(笑)
14代藤野雲平氏はご健在で、しかもネットで「巻き筆」の通販までされているではないか。
攀桂堂(ハンケイドウ)雲平筆
http://www.umpei-fude.jp/about-us.php
筆は高いもの、と覚悟していたが、写経用の筆なんて3000円台。
10年の憧れを実らせてこのたび無事に写経用と消息筆(書簡用筆)を手に入れた。
良い時代になったなぁ。
使ってみて、どうか。
確かに使い心地が全然違う。
今迄のヘナヘナしてすぐにバサバサに先がなった小筆類は、あれはなんだったのか。
日本国民を書道嫌いにさせようというGHQの陰謀だったのか?
筆ペンみたいにピタッと穂先がいつもそろい、点やハネが乱れにくい。
その気になれば本当に細い線がスーッと書ける。
使い心地は世間に普及している腰の無い「水筆」と違うが、「筆」は「筆」だ。
止め、ハネ、払い、筆を浮かせるようにして紙に近づけたり離したりして太さをコントロールしたり、一画の入り始めから「意志」を持って操作しなければならないこと、などは今まで悪戦苦闘して使ってきた筆となんら変わらない。
ただ、これで酷い字を書いてしまっても、もう筆のせいにはできないと思った。
【追記】
「大江戸生活体験記」では14代が当主、とありましたが、いまHPを見たら今の60才代と思しき当代は15代でした。
ということはブログを書いたりしている若い方は16代になる方なんだろうな。
いつまでも続きますように、攀桂堂。
著者両人が江戸時代の生活を出来る限り再現して生活してみるレポートから現代のエネルギー事情を考えようという本。
大江戸生活体験事情 (講談社文庫)/講談社
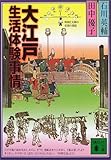
¥560
Amazon.co.jp
これで田中優子さんが筆で文字を書くことについて1章割いていて、筆記具について「現代と江戸時代で最も違うのは筆」「江戸時代の筆は筆の中心に硬い毛を使い、その根元を紙で巻き、さらにそのまわりを柔らかい毛で被う『巻き筆』は主流だった」とある。
その巻き筆を使うと「書くときに腕と手でコントロールできる毛の柔らかさと同時に、硬い毛の弾力を有効に利用できる」そうである。
巻き筆の使い心地について田中さんは「仮名の繊細な線が実に美しくかける」「何ミクロンという単位すら可能ではないのかと思うほど細くかけ、しかも力の入れ具合で自由な弾力が得られる。」とレポしている。
これを読んだ時、昔の人の繊細な筆文字、ぎっしりと細かく「筆」で描かれた書簡などについての謎が氷解した。
現代の、私があのように字を筆で書けないのは、修練もあるけれどまず、「筆」のせいだったのだ。
猛然とその「巻き筆」とやらが欲しくなったが、この本によると現在その「巻き筆」を作っている職人さんは滋賀県の藤野雲平さんという職人さんただ1人で、田中さんは書家の友人の紹介で巻き筆を作ってもらった、とある。
2002年にこの本を読んだ当時は貧乏な陶芸家もどきとしてはそこで諦めた。
紹介で「日本でただ1人」につくってもらわなきゃならないなんてハードル高すぎるじゃないか。
時は流れて2013年。
酔狂にも「写経」を始めた11年後の私は、東急ハンズで1000円ちょっとで買った「写経用筆」の使いにくさに苛立っていた。
使いにくいとその分丁寧に書こうとして自分を見つめるのには良いのかもしれないが、モノつくりという立場からみれば、「弘法だって筆を選ぶ」のだ。
道具で苛立っていては良い仕事はできないのだ。
良い筆が欲しい。
良い筆って、どこで買えるのよ?どんな筆を良い筆っていうのよ??
ふと・「巻き筆」のことを思い出して検索してみた。
・・・・・・あっという間に出てきた。(笑)
14代藤野雲平氏はご健在で、しかもネットで「巻き筆」の通販までされているではないか。
攀桂堂(ハンケイドウ)雲平筆
http://www.umpei-fude.jp/about-us.php
筆は高いもの、と覚悟していたが、写経用の筆なんて3000円台。
10年の憧れを実らせてこのたび無事に写経用と消息筆(書簡用筆)を手に入れた。
良い時代になったなぁ。
使ってみて、どうか。
確かに使い心地が全然違う。
今迄のヘナヘナしてすぐにバサバサに先がなった小筆類は、あれはなんだったのか。
日本国民を書道嫌いにさせようというGHQの陰謀だったのか?
筆ペンみたいにピタッと穂先がいつもそろい、点やハネが乱れにくい。
その気になれば本当に細い線がスーッと書ける。
使い心地は世間に普及している腰の無い「水筆」と違うが、「筆」は「筆」だ。
止め、ハネ、払い、筆を浮かせるようにして紙に近づけたり離したりして太さをコントロールしたり、一画の入り始めから「意志」を持って操作しなければならないこと、などは今まで悪戦苦闘して使ってきた筆となんら変わらない。
ただ、これで酷い字を書いてしまっても、もう筆のせいにはできないと思った。
【追記】
「大江戸生活体験記」では14代が当主、とありましたが、いまHPを見たら今の60才代と思しき当代は15代でした。
ということはブログを書いたりしている若い方は16代になる方なんだろうな。
いつまでも続きますように、攀桂堂。