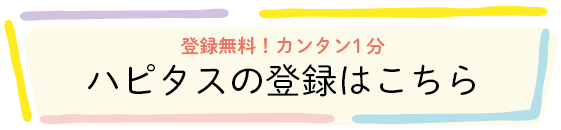おごめ~ん、大分のtakatch親方です(`・ω・´)ゞ
本日は大分地質学会の講演会・総会に参加いたしました♪
入会2年目にしてやっとこさ2回目の参加です。。。(苦笑)(2014年春の巡検@玖珠盆地以来。毎度巡検や総会に興味があるも、先約とかぶる。。。(。>д<))
この会は新年の始めに行われる大きな活動です。
以下、本日の会のうち、内部向けの総会を除く、講演部分の概要を簡単にご紹介いたします。
(※容量が多くなる&難しい内容については私がついていけないため(苦笑)、分かる範囲で簡潔にご紹介しております。ご了承ください。)
- 〈特別講演(1講演)〉
- 〈総会〉※内部会のため割愛。
- 〈講演:個人発表(6名)〉
〈特別講演〉
☆「大分県の蛇紋岩について」(金沢大学:曽田 祐介氏)
蛇紋岩をご存知でしょうか?
私は2014年末、地質の専門家らと化石採集中@佩楯山に、蛇紋岩について教えて頂きました。
今回、蛇紋岩研究をされている金沢大学の曽田氏が、蛇紋岩の概要&大分県内の蛇紋岩についてご講演くださいました。

【まとめ】
(蛇紋岩の概要)
- 蛇紋岩=かんらん石+水(※かんらん石=マントル(地下)にあるはずなのに、なぜか地上にある)
- 堆積岩由来のかんらん石と、マントル質かんらん石とがある。
- 蛇紋岩の研究…戦後間もなく研究が盛んだった→しばらく下火の時期あり(区別がつきにくかったから?)
→4~5年前から再注目(∵1)2つの仮説発生「エネルギーとして活用できるのでは?」「地球温暖化防止につながる?」、2)ラマン法が使えるようになった)
(蛇紋岩の構造)
・原子レベル…1:1層→八面体1枚+四面体1枚
→But!八面体&四面体とで僅かに大きさが異なる(ミスフィット)がある
→ミスフィットに対し、蛇紋岩には3つの解消法(構造)がある。
→「リザータイト(平面上でゆがんで解消)」、「グリソタイル(渦を巻いて解消)」、「アンチゴライト(渦巻かずに波上に繰り返して解消)」
・3つの解消法の区別方法は主に4つ→1)薄片の顕微鏡観察、2)X線、3)電子顕微鏡、4)ラマン分光(※いずれの方法にも一長一短あり。)
(蛇紋岩の安定条件)
※大まかな傾向(現実は結構複雑)
- リザータイト&グリソタイル→低温で安定な蛇紋岩
- アンチゴライト→高温で〃
(蛇紋岩の発生する場所)
- 海(OCC)…ムリオン地形(引き出しを引っ張ったら中身が飛び出したように引き伸ばされた地形)←※調査は厳密さが必要で、難しい
- 沈み込み帯…異方性ある蛇紋岩(海中=波に揺られる→横のつながりは強くとも、縦のつながりは脆い)
(大分県内の蛇紋岩分布)
1)津久見、三重、朝地
・津久見&三重…黒瀬川帯(ジュラ系秩父帯のうち、蛇紋岩など特定の岩石の出る地帯)に属する。
…”かんらん石→高温型蛇紋岩化→低温型〃→変形(現在のジュラ紀付加体と接合)"
・朝地…↑に加え、白亜紀の花こう岩で焼けたものという可能性高し。
2)佐賀関半島
・三波川変成帯に属する。
・半島中央部…かんらん岩の組織をよく残す、”かんらん岩→低温型→高温型→海洋由来?”
・佐志生断層付近…高温型(アンチゴライト)、強い面構造が発達
3)まとめ…大分平野周辺=起源&履歴もばらばらな蛇紋岩がゴロゴロ存在
P.S.2014年末に、私が確認した蛇紋岩@佩楯山(※画像が異なっていれば失礼。)


特別講演・総会・昼食に続き、午後は会員による研究・事例発表が行われました。
〈講演:個人発表(6名)〉
☆「大分県三重町高屋に分布する下部白亜系佩楯山層群腰越層の石灰岩礫(岩)から産出したサンゴ化石について」(佐藤裕一郎幹事)
私の中学時代の恩師です。中学時代、鉱物や化石採集に連れていって頂いた思い出あり☆
私が社会人になってからも、ジオガイド養成講座で大変お世話になっている先生です。
今回は、豊後大野市三重町の佩楯山系で産出したサンゴの化石&その地層の考察発表でした。

▽産出したのは、セリオイド型四放サンゴの化石。
四放とは、サンゴが誕生時に四つの隔壁が生じることに由来。
四放サンゴは古生代に誕生の古い種。骨格はカルサイト(方解石)で、残りやすいのが特徴(一方、三畳紀に入ると六放サンゴが出現。骨格はアラゴナイドで残りにくい。)
また、算出地点である三重町高屋の尾平山の地層について紹介(腰越層(石灰岩礫)や内山層(メランジュ))。
そして、不整合や石灰岩礫の密集地について、その区別や成立について、2つの仮説を立てて考察されました。
私の地元豊後大野での話題であり、佩楯山系にはまだ自分の知らない層群があり、興味を抱きました。
▽参考までに、会場では今回研究フィールドである高屋の岩石展示も。
こうした実物があるのも嬉しいですね♪

☆「足跡化石産地巡検記」(北林栄一氏)
長年教壇に立たれ生徒に教育をされたり、ご自身も化石採集を通じ研究されたり。
その成果が認められ、昨秋叙勲をされたようです。今回は、足跡化石の調査報告をなされました。

足跡化石研究のきっかけは、1994年11月。
愛知県豊橋市の研究家に勧められたことによります。
そして翌年、足跡化石研究の本場:滋賀・三重へ。
足跡化石は、上からの鳥瞰はもちろん、横からの断面(中華鍋のように地面が凹む痕)を確認するとよいことを学習。
その後、大分県を中心に、九州・中国・四国地方でも調査。実は大分県でも、安心院盆地を中心に多くの足跡が発見されたようです!
▽安心院盆地津房川層のゾウ足跡化石。左は上からの俯瞰、右は横からの断面。

学び・まとめは…
- 「大分でも、琵琶湖古層と似た層相を探せば見つかるかも」という視点で大分の地層を確認→実際にたくさん見つかった。
- 実は現生生物の研究も必要(動物園のようなコンクリート地面ではなく、まさに自然の地面上で生活する動物の足跡研究)→現生生物研究のために海外へ赴く人が意外といない現状。
- 若い研究者の台頭に期待!
☆「佐伯市蒲江深島の地質」(堀田秀俊事務局員)
現役高校教諭で、生徒とともに研究されております。
地質学会の事務局担当で、各種連絡やりとりでお世話になっております。
また、2012年のおおいた別府ジオシンポでもご講演されました。
今回は、昨年県下の地質研究をされる高校生とともに訪問した、佐伯市蒲江の深島の地質についてご講演。

深島は、大分県最南端地。2005年の国勢調査では、人口19名。
近年は猫の家&MAP作成で、注目を浴びている島のようです。
▽MAP

深島は、大きく2つの地層で成立。槇峰層ともう1つは失念。。。
槇峰層の特徴=泥質岩(千枚岩・頁岩など)+塩基岩やチャートを頻繁に挟みます。
▽槇峰層ともう1つの層群との境目。

また、深島では水中火山岩類を確認できます。
Ex:枕状溶岩(枕や俵状に溶岩が固まり連なる)、ピローブレッチャー(ブレッチャー=角礫。枕状溶岩の先端にピロー・ローブが堆積)、ハイアロクラスタイト(水冷破砕の一種)。
▽画像中では、4つの枕状溶岩を確認。

以上が、学術的な研究発表。
以下が、県内のジオパーク活動についての事例発表。
☆「姫島ジオパーク活動について」(堀内悠氏)
2013年9月に日本ジオパークに認定された、おおいた姫島ジオパーク。
姫島のテーマは、「火山が生み出した神秘の島」。
堀内研究員が、姫島の地質について詳しくご紹介!

▽姫島は、7つの火山で形成。
もともとそこにあった堆積岩層(丸石鼻層・川尻礫層・唐戸層)の下、火山がドーム状に隆起。
また、火山間で砂州形成(トンボロ現象)もあり、現在の形へ。
さらに、姫島では動物化石(上記の足跡化石も)が発見されております。
また、ジオパーク活動(普及・教育・保護)についても紹介。
教育はもちろん、今後は保護にもさらに力点。
文化的景観保存事業をはじめ、これまで以上に法規制を強化し、資源を保護するそうです。
Cf:姫島のジオサイト(2011年8月、プライベートで姫島を訪問した際の画像)
※5月15日(予定)、大分地質学会の巡検会Iは、この姫島ジオパークで開催予定!
※各ジオサイトの詳細は、姫島GP公式サイトや現地でご確認くださいませ。
▽黒曜石

▽大海のコンボリュートラミナ

▽浮田

▽拍子水

☆「豊後大野におけるジオパーク活動と郷土愛」(大野幸則氏)
私も大変お世話になっております大野氏の発表。
おおいた豊後大野ジオパークのテーマは、「巨大阿蘇火砕流から9万年。大地に祈り、いかされ。」
前半は、大野氏の大学時代の研究内容紹介(宮崎県五ヶ瀬川流域の地質調査)。
後半は、豊後大野ジオパークでの教育活動について紹介。
義務教育でのジオ・郷土学習、CATVでのジオ学習番組制作の例が紹介されました。

Cf:豊後大野GPの主なジオサイト(詳細は姫島と同様)
▽原尻の滝

▽沈堕の滝

▽菅尾磨崖仏

▽出会・轟橋

☆「津久見市の地域資源発掘~2015年の活動報告~」(白水秀子氏)
最後に、これからジオパーク活動に向けて動き始める津久見市の事例発表です。
発表者の白水研究員は、平成生まれと若い☆
2015年4月の大分学研究会ツアー@津久見でも大変お世話になりました。

2015年は、津久見の地域資源発掘=「残しておきたい津久見の風景さがし」の取組を実施。
以下の3つの事業が例。
- 「市民図書館トピック展」=市内外の話題に関する書籍・展示などを紹介(保戸島の空襲・網代島の宇宙塵など)
- 「無垢島自然体験学習会」=子どもたちが宿泊で、化石採集・天体観測など体験活動。
- 「市内めぐり」=残したい津久見の風景探し(文化財再調査)
▽市内巡りで、たくさんの津久見の風景を撮影。
「こんな場所もあるのか~」、「石や信仰の文化が根強い土地だなあ」など発見多し。

今後は、個々の資源をつなげたストーリー・動線づくり(『津久見の文化財』情報更新、看板の整備など)に取り組みたいとのことです。
▽津久見の地質スポット

▽昨年の大分学研究会で訪ねた網代島。このチャートの色彩に大興奮☆
また、宇宙塵がこの網代島で確認されたことも有名。その宇宙塵を発見されたのが、白水氏のゼミ教授とのことです。


▽また、津久見といえば石灰岩!この風景も津久見の象徴的風景。

これから楽しみな津久見ですね!
講演は以上です。
最後に、アラカルト。
▽会場は、野津原の大分川ダムななせ館さん。

▽館内は展示もあり、ダムのことも学べます!(土木と地質は密接な関係あり!)

▽昨年、四国は愛媛での巡検時の岩石。こうした昨年の実績をモデルで確認できるのもありがたい☆(この会にも参加したかったんだけどなあ…。)

▽また、地質に関する著書販売もあり。割安で購入できました♪


…と、以上が総会・講演会の模様でした。
がっつりと地質ですね!
難しい内容もあり。そこは、私の今後の自習が必要。
ただ、「大分にもこんな場所があるんだあ!化石が出るんだなあ!」と新発見や、純粋な興奮もあり。
これはどんどん大分を歩き、地質観察しよう!巡検も楽しみ~♪
せっかく地元がジオパークとなり、それまであまり注目しなかったジオに興味を持ち始めました(=視野の広まり)☆
これからも、地質と触れあって楽しみ、学び、いつしか面白さや楽しさを他人に伝えられるように…☆
以上です。最後まで読んで頂き、ありがとうございましたm(__)m
![[PR]骨盤底筋ガードル「me&Re」](https://stat.amebame.com/pub/ads/rch/bnr/ef0b5a46-0a12-4e0f-b3ac-cd15b313bf94.jpg?ext=j5)