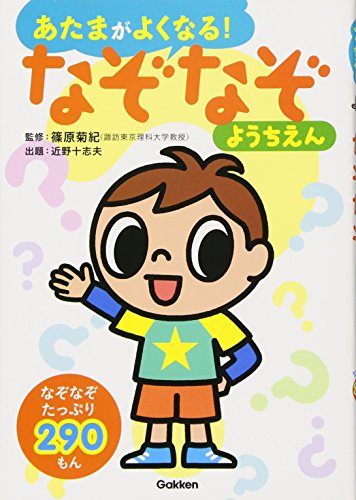小学校受験を思いたったら、すぐにでも普段の遊びや会話に取り入れて、学んで頂きたいことがあります。
子供たちが「英語って楽しい!」そう思ってくれたら嬉しいですよね。
普段の生活から意識して遊ぶことで、その積み重ねが違いにつながると思います。準備は早ければ早いほど良いはず。笑
以下にその例をお伝えします。
◼️しりとり遊び
小学校受験では「ひらがな」自体を書ける必要はありませんが、言葉をひらがなに分解して理解している事は要求されます。
その理解度を図る代表が、ペーパーのしりとり問題です。
基本問題で言うと、以下の絵が書いてあり、しりとりで使わない物にマルをつけましょうのようなタイプ。
🍎(りんご)
🦍(ごりら)
🐪(らくだ)
🐕️(いぬ)
りんご→ごりら→らくだ
使わない犬にマル
のような問題です。
最近では、2文字目しりとり(ごりら→りす→すいか→)、おしりから2文字目しりとり等しりとりのパターンが複雑化しています。
また、このしりとり問題は語彙力との関係が深いのです。絵で書いてあるので、「やご」、「こたつ」や「あさがお」等が分からず、問題が解けない等ということも起こります。
ペーパー対策は、徐々に行うとして、まずはお父さん、お母さんと楽しくしりとり遊びを初めて頂けたらと思います。
◼️なぞなぞ遊び
ペーパー問題「わたしは誰でしょう」や行動観察において、友達同士で「なぞなぞ問題を出し合う」なんて課題があるようです。
後者は、絶妙なヒントを出す「なぞなぞ」への理解が必要なので、この時期の子供にはかなり高度なものです。
我が家では、個人塾で推薦された以下のなぞなぞ本を使って、「答える役」、「問題を出す役」の両者を務めさせて、なぞなぞに楽しく取り組みました。
◼️左右の理解
「地図上の移動」というペーパー問題で必要になりますね。
「二つ目の角を右に…」
「八百屋さんの角を左に…」
等についての問題です。
子供とストライダーに乗って、買い物や公園に行く際は、必ず「次の角を右ね」、「花屋さんを左だよ」と「左右」で指示を出してください。すぐには伝わらないかもしれませんが、そこは継続は力なり!です。
前提として、左右の理解が必要ですね。そこは、「時計回り」、「旗揚げ遊び」や「お箸を持つ手」を意識させる等も試みました。
◼️影の理解
これは、「理科的知識問題」に関わります。子供も大好きですし、すぐ理解できます。「影がこっちに伸びているね。今、太陽はど~こだ?」という問題で遊びます。
夕暮れに子供と手をつないでの帰り道、いつも問題を出しあっていました。
◼️番外編「えいご」
小学校受験とは、直接関係がありませんが、英語遊びでとても楽しく学べる本をご紹介させてください。
これは、男子校の雄である暁星小学校に合格したお母さんが紹介してくれたものです。英語教材としては、有名みたいですね。
とにかく子供に「ギャハハ」とウケるんです。本が上と下で切れていてページをめくると、くも、火山、深海魚、おばあちゃん等が様々な組み合わせとなり、思いがけぬ楽しいキャラクターが現れます。
題名にもなっている”Cheese and Tomato Spider” とか “Strawberry flavored grammy”とか。。笑
読んでいる親も爆笑するキャラクターが現れます。
--------
ペーパーの勉強として構えずに、遊びの中で学べる事はたくさんあります。
小学校受験は長丁場。お子さんを、または、ご両親自身も追い込み過ぎないためにも、いかに楽しく学ぶ機会を作るかは、大切な観点だと思います。
お知らせ
この度、新たなブログを立ち上げました。
子育て情報ブログ
【君たちに伝えたいこと】
https://www.raising.work/blog/
テーマは小学校受験だけでなく、もう少し幅を広げて、子供たちの成長につながるような情報や、また親の喜びを感じられるような雑感を綴っていけたらと思っています。
ぜひこちらのブログもご愛顧いただけたら嬉しいです。
たかし