2015.05.18
木本 茂 (きもと・しげる) 氏
[高島屋社長]
(PP.080-083)
もともと、免税品の売り上げを110億円と見積もって
いたのですが、ふたを開けてみたら上期44億円、
下期96億円の計140億円でした。
今では、中小型店1店舗分に相当する売り上げを
インバウンドで稼いでいます。
中でも新宿店と大阪店の割合が高くて、140億円中
100億円をこの2店舗で占めています。
だから我々もあらゆる手を打っている。
例えば訪日外国人がこの2店舗で免税品を買うと、
空港まで配送しています。
新宿店は成田か羽田、大阪店は関空という具合
にね。 これをやっているのはうちだけですよ。
インバウンド売り上げの7割が中国、香港、台湾の
お客様によります。
そこで活用したいのが上海、台湾、シンガポールの
海外3店舗です。 現地法人を持っているメリットを
生かして、ウェブサイトに訪日を促す仕掛けを入れ
ました。
また、日本の高島屋で使えるクーポン券を現地で
発行しています。
東南アジアでもどんどん知名度を高めていきたい
ところです。出店に際し、大きな強みになっている
のが「シンガポールに高島屋がある」ということです。
シンガポールも最初の10年は本当に青息吐息で、
10億円規模の赤字を出していた時期がありました。
でも、やっぱり先行投資したことが今、大きなリターン
となってきている。 2014年度の営業利益は連結
ベースで320億円、そのうち約60億円をシンガポール
が稼いでいます。 もう、超優等生ですよ。
しんどいですね、上海は。シンガポールと違って、
2014年度は20億円の赤字です。
円安元高の影響もあり、前期より2億円近く悪化して
います。
2017年に、タイ・バンコクに出す新店は売り場面積が
3万6000平方メートルなのですが、この規模で資本金
が36億円です。
さらに合弁でやっているので、我々の出資分は約18億円
です。18億円で3万6000平方メートルの百貨店ができて
しまうのです。日本で同じ規模のものを作ろうと思ったら、
まず桁が違うでしょう。
2011年、売り場を1.4倍に増床してリニューアルした大阪・
なんばの高島屋大阪店には400億円近く投資しました。
極端な話、海外ならば10店舗ぐらい出せちゃう規模の
お金を、国内では1店舗に投じていかなければならない
のです。
今年度は成長に向けた投資を国内事業に800億円、
海外事業に500億円と見積もっています。
名目の数字だけ見ると国内の方が額は大きいのですが、
実際はやっぱり海外の方が投資効率が良いうえ、
利益を生み出していくポテンシャルが高いだけに、
それなりに配分しています。
銀座とか札幌とか、観光客がよく来る地区にたくさん
店舗を持っている企業はうらやましいですね。
うちも諦めているわけではないし、色々策を打ってますが、
観光客の動きがそうなっている以上、結果がなかなか
出せない。
例えば横浜店。利益ベースで見ると一番稼いでいる店舗
ですが、インバウンドの売り上げは7億円しかありません。
人の流れは、すごく重要だと思います。
そういう観点から見ると、新宿店は追い風ですね。
旧国鉄の貨物操車場跡地に建てられただけに、
新宿駅からぽつんと離れている印象がありました。
ただ、2016年に南口に新しい駅舎が完成すると、
これまで駅周辺のあちこちに点在していたバスターミナル
が(新宿店に近い)新南口辺りに集約されます。
これは大きいですよ。
一方で、紀伊国屋書店に近い明治通り周辺のエリアでは、
三菱地所による再開発計画が進んでいます。
大きなオフィスビルが建つ予定です。今交渉中ですが、
うまくいけば紀伊国屋の入り口とつながるでしょう。
もう、プラスの材料しかありませんね。
新宿エリアは、競合がみんな悲鳴を上げている中で、
うちだけはプラスの材料ばかりです。
新宿店はこれから「収穫期」に入ります。
一時期は阪急阪神百貨店のエイチ・ツー・オー(H2O)
リテイリングと経営統合する話もありました(2010年に断念)。
未来永劫、統合は絶対にないということはありませんが、
今は、業務提携で実利を得た方がいいという結論に落ち
着いたのです。
ここ数年、トレンドの変化が大きい婦人雑貨が好調です。
制約はありますが、その中で弾力的に売り場作りや品ぞろえ
を変えている効果が出ています。こういう強いところをどんどん
強くしていくことに、百貨店の活路を見いだすことができる
でしょう。
インバウンドで一番恩恵を受けているのは、コンビニでもなく、
ショッピングモールでもなく、百貨店です。
その要因は、やはりワンストップで買い物ができる点にあると
思っています。今、その強みが顕在化している状況です。

高島屋社長 木本 茂 氏
(『日経ビジネス』 2015.05.18 号 P.081)
「日経ビジネスDigital」 2015.05.18

キーセンテンスは、
人の流れは、すごく重要
です。
人の流れを保つことも、変えることも、
企業努力だけでは限界があります。
木本さんのお話のように、外部要因である、
再開発や交通手段の変更などによって大きく変化
します。
今まで多くの顧客が来店していた店が、
近隣に大型店ができ、交通網が整備された途端に、
客足が減少したというケースはよくあります。
また、その逆も当然あります。
今までほとんど来店客がなかった店に、
交通の便が良くなり、来店客が急増したというケース
もよく耳にします。
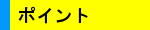
ポイントは、
デパートは長期的視野に立っての経営
が肝要
ということです。
木本さんは新宿店やシンガポール店を例に挙げて、
説明しています。
新宿店の場合
(P.083)
「永遠に利益が出ない」と言われてきましたが、
ようやく、投資が生き金になってきました。
1996年の開業以降、毎年100億円以上の賃料を
払ってきて、それがかなりの負担になっていました。
しかし、不動産の一部を取得し、自社物件化する
ことで負担はだいぶ減りましたね。
シンガポール店の場合
(P.080)
シンガポールも最初の10年は本当に青息吐息で、
10億円規模の赤字を出していた時期がありました。
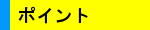
ポイントは、
国内外で投資効率に大きな差がある
ということです。
「18億円で3万6000平方メートルの百貨店ができて
しまう」のに対し、「売り場を1.4倍に増床してリニュー
アルした大阪・なんばの高島屋大阪店には400億円
近く投資」が必要だったそうです。
物価や人件費、土地の価格に内外価格差がある
からです。
高島屋は現在、海外に3店舗を持っていて、
今後さらに出店していこうとしています。

インバウンドを当てにしているだけでは大きな成長
は見込めないからです。
リスクを負い、成長著しい新興国に打って出て、
その増益分で国内をカバーするという構図が出来
上がりつつある、と見ています。
私はめったにデパートで買い物はしませんが、
高島屋横浜店は横浜駅に隣接していて、
立地条件に恵まれていますが、
インバウンド客が訪れるかと言われると、
木本さんが指摘されたように少ない、と言わざるを
得ません。
確かに、横浜中華街や横浜スタジアム、山下公園、
ランドマークタワー、横浜アリーナなどの観光地は
あります。
ですが、国内のお客様は増加しても、
海外からお客様を呼び込むことに尽力しているとは、
とても思えないからです。
新宿地区では、伊勢丹との競争が激化することでしょう。
百貨店利用者(私は違います!)にとってはありがたい
ことです。
新宿コマ劇場跡地に、新宿東宝ビルが完成し、
歌舞伎町は浄化されつつあるので、さらに集客力を
高めることでしょう。

歌舞伎町にできた新名所 新宿東宝ビル
(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 PP.050-51)
「日経ビジネスDigital」 2015.05.11
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書