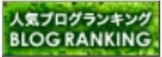株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
中田敦彦さんの【国債で減税していいのか?】動画の間違いを徹底的に訂正します。
中学生でもわかる消費税の大ウソとは!国民は騙されてるのか?三橋貴明【赤坂ニュース315】参政党
昨日の徹底訂正動画の冒頭で紹介しましたが、ジョン・ケネス・ガルブレイスは貨幣について、
「お金が創り出される過程はあまりに単純なので、逆に納得しがたい」
という明言を残していますが、本当に単純です。
誰かがカネを借りれば、貨幣は創出される。
例えば、わたくしが、こゆきさんから10万円借りました。もちろん、借用証書を供出します。
こゆきさんが持っている「10万円の借用証書」が、他の人への支払いに使えるならば、貨幣です。貨幣成立の条件の一つに、譲渡性があります。
まあ、実際にはわたくしの借用証書は流通せんのですが、小切手の場合は話は別です。小切手は、普通に貨幣として流通します。小切手の譲渡性は、「小切手振出人の当座預金」によって担保されているのです。
いずれにせよ、貨幣は貸借関係の成立で創出され、貸借関係の解消で消滅します。今時「貨幣は物々交換の利便性を高めるため~」は、さすがに恥ずかしい。物々交換経済なんて、成立するはずがないのです。
「自分の生産物と、相手の生産物との生産時期が異なる」
「自分の生産物が、相手の需要と異なる」
「相手の需要が、部分的(牛肉は欲しいが、牛一頭はいらない)」
「たまたま、自分が生産できなかった」
ちょっと思いついただけで、これだけ「需要を満たせない」可能性があるわけです。需要が満たせないと、人間は死にます。
(動画でも解説しましたが、異なる共同体同士の物々交換はありました)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【皇統論:第七十九回】建武の新政、【歴史時事:第七十九回】スペインの奴隷、がリリースになりました。

https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ちなみに、物々交換でないならば、どのように財やサービスを流通させていたのかと言えば、互酬と分配です。互酬にせよ、分配にせよ、共同体、しかも構成員の信頼性が高い共同体なしでは成り立ちません。
以前、
「狩猟時代、人間は生き延びるために共同体を作る必要が(論理的に)あった」
といった話をしましたが、
なぜ弱い人間が生き残ったのか?[三橋TV第1052回]三橋貴明・菅沢こゆき
経済あるいは「貨幣」も共同体なしでは成立しないのです。貨幣は「貸借関係」であるため、人間が二人以上いる必要があります。
動画のロビンソン・クルーソーとフライデーの例(元々はイングランド銀行の例)は、島に二人いるから成り立つ。フライデーがやってくる前のクルーソーの島では、貨幣は成立しない。
つまり、貨幣とは共同体の産物なのです。「権利」が共同体の産物であるのと同じです。
思えば、
「狩りが巧い人間が生き残った」
「権利は普遍的(創造主が認めたから(笑))」
「貨幣は物々交換の利便性を高めるために生まれた」
上記三つって、共同体否定なんですよね。あるいは、「個人」依存。
現実には、狩りの天才であっても、運が悪く、獲物にめぐりあえなかったら死ぬ。共同体がない場合、権利を認めてくれる存在がないため、権利は存在しない(島に一人で暮らしていたクルーソーには何の権利も無かった)。貨幣は共同体内の貸し借りという人間関係により創出される。
何となく、問題の根底が見えてきませんか?
本日のエントリーを読み「なるほど!」と、思って下さった方は、
↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。