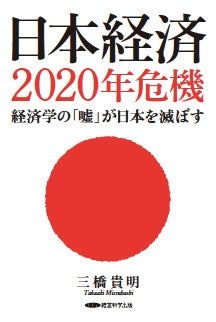株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
チャンネルAJER
『MMTと令和の政策ピボット(前半)』三橋貴明 AJER2019.4.30
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
一般参加可能な講演会のお知らせ。
【令和元年7月5日(金)三橋TV公開収録&懇親会】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『MMTと令和の政策ピボット(前半)』三橋貴明 AJER2019.4.30
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
一般参加可能な講演会のお知らせ。
【令和元年7月5日(金)三橋TV公開収録&懇親会】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
三橋TV第98回【私の政局予想は必ず外れるんだからね!!】
もはや「記念」として保存しておきたい記事の数々。
自民党の岸田文雄政調会長は31日、党本部で連合の相原康伸事務局長と面会した。相原氏は、今年10月に予定される消費税増税の着実な実施と軽減税率制度の「廃止」などを盛り込んだ要請書を手渡した。岸田氏は要請内容には言及しなかったものの、「経済・社会の活性化はオールジャパンでしっかりと考えていかなければいけない」と強調した。(後略)』
『インタビュー:消費増税延期の選択「あり得ない」=三村日商会頭
日本商工会議所の三村明夫会頭は、ロイターとのインタビューで、消費税増税を巡って安倍晋三首相の周辺から延期を示唆する発言が出たことについて「増税まであと数カ月に迫る中で、上げない選択はあり得ない」と述べ、予定通り実施すべきとの考えを示した。(後略)』
日本商工会議所の三村明夫会頭は、ロイターとのインタビューで、消費税増税を巡って安倍晋三首相の周辺から延期を示唆する発言が出たことについて「増税まであと数カ月に迫る中で、上げない選択はあり得ない」と述べ、予定通り実施すべきとの考えを示した。(後略)』
労働組合の連合会である日本労働組合総連合会(連合)、加盟企業125万社を超す全国の商工会議所の連合会である日本商工会議所(日商)と、労働者や中小企業の「組合の組合」を抑えた財務省の手法は、見事としか言いようがありません。
本来、自分たちのビジネスや生活のために、反グローバリズム、反緊縮財政、反消費税に走りやすい(というか、走らなければならない)政治勢力を、頭を抑えることで黙らせる。素晴らしい手腕です。
面白いことに、もう一つの反グローバリズム的な「組合の組合」である全農(全国農業組合連合会)には、財務省のご説明(洗脳)は届いていないようです。どうせ、株式会社になったらカーギルに買収されるから、どうでもいいや、と、思っているのかも知れませんが。
さて、デフレ脱却を目指す政権が、デフレ促進策(しかも極めて強力)である消費税増税を繰り返す狂った日本ですが、昨日も解説した通り、主流派経済学的にはデフレは悪ではないのです。悪は、モノ不足・サービス不足の証であるインフレです。
主流派経済学がインフレを敵視するのは、産業革命前の収穫逓減の時代に「学問」としてスタートしたためです。結果、産業革命を経て、生産性が極端に上昇し、収穫逓増の時代に入っても、21世紀になっても、主流派経済学は、
「そんなことをしたらインフレ率を制御できなくなる」
と、政府の財政政策に反対し続けています。
佐藤健志先生の仰る「経路依存性」です。しかも、こちらは18世紀から21世紀まで継続している依存性なわけですから、日本の財務省どころじゃないです。
ところで、経済学は伝統的に「不確実なもの」を排除する傾向があります。経済合理性以外の人間の価値観、効用最大化が必ずしも善ではない現実(軍隊の効用が最大化するって、それ戦争だ)などはスルーし、美しいモデルを組み立てることに必死になるのが経済学者(主流派)です。
というわけで、経済学者は「生産性向上」も好みません。理由は、よくわからないためです。
潜在成長率(潜在GDPの成長率)の構成要素(労働投入量、資本投入量、全要素生産性)を見れば、よくわかります。潜在成長率は、統計可能な「労働投入量」「資本投入量」と、事後的に計算される「全要素生産性(以下TFP)」に分解されます。
TFPは、実際のGDPという「結果」から、労働投入量と資本投入量を差っ引くことで計算します。
「え? ということは、労働投入量や資本投入量が変わらなくても、経済成長した場合、『それはTFPの影響』で片づけられるのでは? TFPって、結局何なんだ?」
と、思われたかも知れませんが、その通りです。そして、よくわかりません。労働者の習熟、技術進歩、環境(インフラなど)改善など、実際の経済は労働者数や資本量では説明できない成長(GDP拡大)を遂げるのです。この、観測不可能な生産性向上効果のことを、TFP、と呼んでいるのです。
実際の「結果」を見れば、TFP(要するに生産性向上効果)がどれほど経済成長に大きな影響を与えているかが分かります。
【日本の潜在成長率と要素別寄与度(%)】
とはいえ、主流派経済学者はTFPや生産性向上が嫌いです。なぜならば、後になって見なければ分からず、事前の予想や観測が不可能であるためです。(モデル化できない、という話)
結果、主流派経済学者は(ポール・クルーグマンまでもが!)経済成長のためには労働人口を増やせばいい。日本は移民受入が必要だ、と、口を揃えたように主張するのでございます。これが、明日の話に繋がります。
さて、実はTFPを引き上げる手段は簡単で、単に財政政策でGDPを拡大すればいいのです。現在の日本は労働人口が頭打ちです。政府の財政で需要が拡大すれば、
「仕事が増えた」
ということで資本投入量が増大し、かつ生産性も劇的に向上します。結果、GDPは成長します。
その時点で、GDPの拡大分から労働投入量増加、資本投入量増加分を差し引いた残りがTFPというわけでございます。
主流派経済学者は、やたら潜在成長率を重視する割に、確実にTFPや潜在成長率を引き上げる政府の財政拡大は拒否する。本当に、意味不明な連中です。
「そんなに、インフレが、嫌なのか?」
嫌なのですよ。数百年の経路依存性が主因でございますので、もはや合理的な理由はありません。
【歴史音声コンテンツ 経世史論 始動!】
ところで、主流派経済学者は、
「銀行が貸し出す際に、おカネ(銀行預金)が発行される」
という現実もまた、嫌で嫌でたまりません。理由は、銀行が民間に貸し出すか否かは、生産性向上と同様に不確実であるためです。必ずしも、合理的な理由でおカネが貸し出される(預金通貨が生成される)わけではないのです。
「銀行が貸し出す際に、おカネ(銀行預金)が発行される」
という現実もまた、嫌で嫌でたまりません。理由は、銀行が民間に貸し出すか否かは、生産性向上と同様に不確実であるためです。必ずしも、合理的な理由でおカネが貸し出される(預金通貨が生成される)わけではないのです。
例えば、経営者と銀行員との個人的なつながりで、貸し出しがなされるケースも普通にあります。すると、マネーストック(現金紙幣+銀行預金)は増えてしまう。
逆に、おカネが貸し出されれば確実に所得増(GDP成長)に結びつく案件が、経営者の説明下手で頓挫してしまう。本来、拡大すべきMSが増えない。
要するに、不確実なのです。
というわけで、主流派経済学は「おカネ」について実体経済から切り離してしまうことにしました。何しろ、増えるのか減るのか、事前にはさっぱり分からないおカネの要素など持ち込むと、美しいモデルが描けなくなってしまいます。
おカネを実体経済から切り離し(貨幣ヴェール論)、別次元の存在として捉えることにしたのです。仮想的な「おカネのプール」をこしらえたのでございますよ。
となると、デフレーションは、
「あ? デフレが嫌だって? カネが足りないからデフレなんだよ。おカネのプールにカネをぶちこみゃ、解決するわ! 間違っても、政府の裁量的な財政拡大など、やるんじゃないぞ、あ?」
と、おカネの種類や信用創造を無視し、マネタリーベース(現金紙幣+日銀当座預金+硬貨)を増やせばデフレ脱却できると、主流派経済学者は主張したのです。要はフリードマンのマネタリズムですが、フリードマンはまさに大恐慌という超デフレーションを、FRBが十分にMBを増やさなかったため起きた(実際は違います)と説明しました。
とはいえ、経済学者も、本当は分かっているのです。マネタリーベースとマネーストックは、「異なるおカネ」であることを。
マネーストック(銀行貸し出し)が増え、消費や投資として費やされれば、デフレ脱却です。それに対し、マネタリーベース(日銀当座預金)を拡大したところで、その時点では需要は1円も増えず、デフレ脱却など不可能です。
要するに、デフレの解決策は簡単で、政府が国債発行+財政支出をすれば、MSも需要(消費+投資)も確実に増え、デフレ脱却できます。とはいえ、
「そ、それだけは嫌だ!!!!!」
というわけでございまして、主流派経済学は「マネタリーベースを増やすだけで、マネーストックや消費、投資が増える」という理屈を編み出す必要に迫られたのでございました。
お分かりですね。
「日銀がインフレ目標を設定し、量的緩和をコミットメントすれば、期待インフレ率が上昇し、実質金利が下がり、MSが増え、消費や投資が拡大してデフレ脱却できる」
という、いわゆるリフレ派のデフレ脱却策は、「おカネのプール論」「財政支出だけは嫌だ!」という主流派経済学のバカげた呪いの賜物なのでございます。
というわけで、元日銀副総裁の岩田規久男教授の量的・質的金融緩和によるデフレ脱却策には、
【「量的・質的金融緩和」の波及経路】
「納得した!」と、思われた方は、
↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。