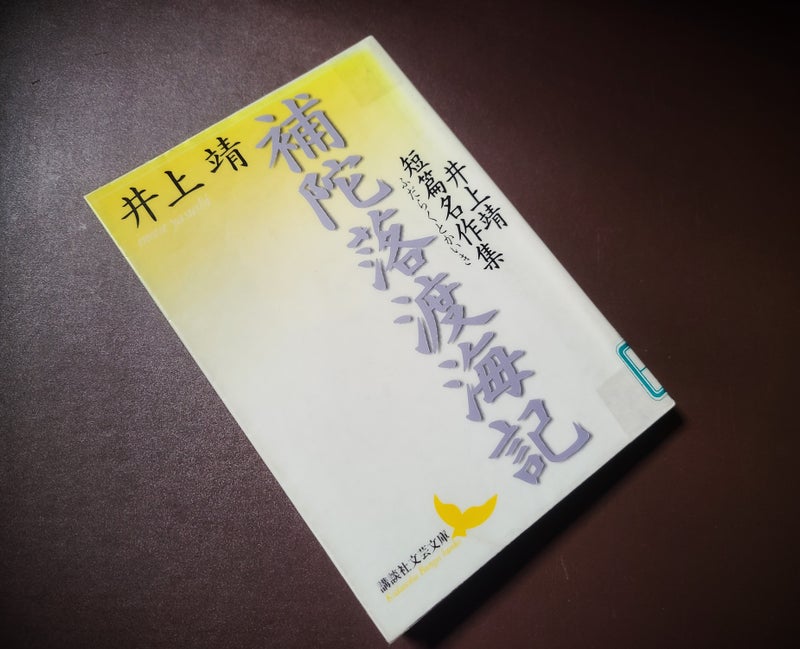熊野古道でずっと気になっていたのが「補陀落渡海」だ。
「遥か南方海上にある観音浄土を目指し、僧侶が人々の願いを抱いて浜ノ宮海岸から船出をする」と言えば聞こえはいいが、要は「捨身」である。しかも、本人の意思とは無関係で行われていたとか聞いたこともあり、真相を知りたかった。
この「補陀落渡海」のことを理解せぬままに、聖地の補陀落山寺に訪れてはまったく無意味だろう。再建された堂宇や渡海船のレプリカを拝む前に、どうしても読んでおきたかった一冊なのだった。
『補陀落渡海記』
(著:井上靖、発行:講談社文芸文庫)
本書は、昭和の文豪・井上靖が描いた短編小説9話をまとめたもので、本編は金光坊という住職の補陀落渡海における死に向かう恐怖と葛藤を描いた作品である。
補陀落渡海は儀式として平安期に始まり、時代とともにいつしか補陀落山寺の歴代住職が行わねばならない責務のようにすり替わっていった。生前に積み重ねてきた功徳は関係なく、61歳になれば皆必ず渡海するものとして世俗的に概念が根付き、とりわけ戦国時代には「乱世で失われた人々の信仰心を取り戻す」というような意味合いも付加されていたらしい。
金光坊は、一度は渡海の運命を受け入れたものの、覚悟が決まらないまま船出したが九死に一生を得て奇跡的に生き延びてしまい、後輩僧侶や良く知る住民たちの手で舟に結わえつけられて再び海へ流されるという壮絶な往生を遂げた。
この出来事を境に、それまでの慣例的な渡海制度はなくなり、物故した住職の遺体を船に乗せて海へ流す水葬儀礼を渡海と称して続けられることになったという。
金光坊の死後唯一、自分の意思によって生きたまま渡海を行ったのが、その死を見届けた清源上人だった。本編の最後では「清源は三十歳になっており、補陀洛寺の記録に依ると、両親のための渡海となっているが、勿論、金光坊の渡海に同行したこの若い僧のその時の心境がいかなるものであったか、それを知る手懸りは何一ついまに残されていない。」と括られている。
短編小説ということもあって、何度も読み返した本作であるが、印象的だったのはこれまでに補陀落渡海を行った歴代僧侶の「顔(表情)」の描写であった。
それは金光坊から見た「顔」であり、それぞれに好きも嫌いもあった「顔」が月日とともに何度も現れては消えていく。渡海が近づくと、そのどれにもなりたくない(もっと別の信心深い僧侶としての顔を持ちたい)と思うようになり、1ヶ月前になると、そのどれでも良いのでなりたくなったという風に心変わりしてしまう。「いつでも容易になれると思っていたのに、それこそが甘い考えであった」ということに気づき、私は「この時こそ死が現実的に自分ゴトになった瞬間」であると感じられ、背筋がゾッとしたのだった。ここから先の金光坊の心境は、とにかく不安定で大きく揺れ動いている。他人のちょっとした言動や振る舞いに激しく怯えたり、怒涛の如く怒ったり、途方に暮れて抜け殻のようになったり…制御出来なくなった感情が波のように押しては返す。
金光坊辞世の句
求観音者 不心補陀 求補陀者 不心海
(観音を求むる者は 心に補陀あらず 補陀を求むる者は 心に海あらず)
ポップカルチャーによる聖地創造から一転、どんより感は否めないが…実際に訪れる熊野古道と補陀落山寺へ思いを馳せながら、聖地巡礼の考察をさらに深めたいと思う。
でわ!