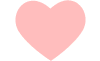「はい?」
用心深く振り向く。
こんなときのためにサングラスをかけてきた。
もしか、「この男の奥さんですか?」と言われたら、
すぐさま走って逃げられるように、スニーカーだし。
振り向いた視線の先、
男が立ってた。
上下スウェットって、
何?ちょっとタバコが切れたからコンビニ行ってくるってお父さんの格好だ。
いくつだろう。
同い年くらい?
超顔色悪いんですけど。
「その花束は、この方に?」
男は、この、で車を指差した。
なぜ感動的な奇跡の母子にではなく、
いたいけな親子を轢き殺そうとしている男に?
そう言いたいのだろう。
男の質問を無視することにして、
手を合わせる。
ここに来るのは今だって大変なのだ。
また次来るのは、いつになるかわからない。
「あの、もし、僕の勘違いじゃなかったらなんですけど。」
男はなおも食い下がる。
なんだ?
このラフな格好でナンパでもないだろうに。
「あの、あなた、この方の、奥さんですよね?」
来た。
危険だ。
逃げなければ。
もうあんな目には合いたくない。
「あ、あの!!」
踵を返し、猛ダッシュで駅に向かって走り出したあたしの背に男が叫んだ。
「あの、驚かせたんならすいません!僕!!」
聞いてられるか。
か弱い母子を轢き殺す悪魔の男の妻。
どうしてあたしが、
そんな目で見られなきゃいけないの。
あんた達が、
夫の、何を知ってるって言うのよ。
「待ってください、僕は!!」
夫は、あの人は、
悪魔なんかじゃない。
「僕は、彼女の夫で、あの子の父親です!!」
え?
恐る恐る振り向く。
顔色の悪い男が、
精一杯の笑顔をあたしに向けた。
「良かった。探してたんです、僕、あなたを。」
それは、本当に、
安堵の笑顔だった。