
進化するグーグル (青春新書INTELLIGENCE)/林 信行

¥767
Amazon.co.jp
ぼくの評価



(おなじみGoogleを取り上げた一冊。著者によって切り口が違ったり、持っている情報が違うので新しい発見があっておもしろい)
日々Googleの情報をやたらと追いかけていると本書のような書物にいずれたどり着くのだが、最近はビジネス書から拾う目新しい情報が徐々になくなってきているのが現状だ。
そこで今回は最近発売された2冊も含めて、書いていきたいと思う。
日経ビジネス Associe (アソシエ) 2009年 10/20号 [雑誌]
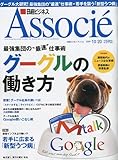
¥590
Amazon.co.jp
日経ビジネス 2009年10月19日号

※こちらは商品リンクがなかったので、読んでみたい方は書店やコンビニ等で自力で探してください(笑)
まだ発売されて間もないのでたぶん売ってるはずかと・・・

おそらく本書の内容の80%~90%はすでに知っている情報だったと思うが、それでも残りの10%~20%を知るだけでも購入した価値があると感じてしまうのはぼくぐらいなもんだろう

まぁ、それだけGoogleの情報に飢えているというか期待しているわけで

では、本書で知った新しい視点、事実等を紹介していこう。
1.Googleがこだわる日本市場
特に新事実というわけではないと思うが、Googleは日本にこだわっている。
その証拠にGoogle初となる海外オフィスは東京だ。
東京オフィスが開設されたのは2001年8月1日のことだが、現在の最高経営責任者(CEO)エリック・シュミットを迎えたわずか5日前のことである。
Googleが本格的に世界進出を考えたときに真っ先に候補に挙がったのは日本なのだ。
だからこそYahoo!にいまだ水をあけられているのが耐えられないはずだ。
先ほどの日経ビジネスでもエリック・シュミットの記事に
「日本は非常に魅力的な市場だ。今は2位にとどまっているが、必ず1位になりたい」
と、意気込んでいる。
では、なぜGoogleはこれだけ知名度が上がったにも関わらず日本では1位になれないでいるのだろう。
ここからはぼくの完全な主観だが、一番の要因は日本特有の民族性だと思っている。
まず日本という国は島国なので国境もなく、他国との隔たりがまだまだ意識的に大きい。
だがGDPは世界2位である。(近く中国に抜かれるのは必至といわれるが)
日本人という種族は異国人との接触に抵抗を感じる人がまだ多く、移民の受け入れにもまだまだ抵抗がある。
そしてGDPからもわかるように民族としてプライドが高い種族だということだ。
さらにイノベーションを推奨するような風潮や環境があまりない割には技術力があるという偏った側面も持っている。
このちょっと変わった日本人という種族がインターネットで始めて触れたサイトがYahoo!であり、Googleではなかった。
ただそれだけだと思う。
総括すると、新しいモノやサービスを受け入れるのに時間がかかる種族が日本人なのではないか。
頭の中ではGoogleの方が優れているとなんとなく分かっている人でも、実はブラウザのHomeをYahoo!からGoogleに変えるのに抵抗がある人がまだまだ多いのではないだろうか。
変化や異分子を多少嫌うがあまり、本能的に受け入れるのに時間がかかるからだ。
しかし日本人のすごいところは一度受け入れると適応するのがおそらく抜群に速い。
あっという間に使いこなしてしまうのも日本人の特徴なのではないかと思ったりもするのだ。
2.Googleplexに招かれる世界の有名人
Googleには世界中から講演を依頼され、多くの著名な人物が招かれるという。
例を挙げれば、元米国副大統領アル・ゴア、チベット仏教のダライ・ラマなど世界中からGoogleplexに講演に訪れているようだ。
そしてGoogleplexの壁には講演した著名人の写真がずらり飾られているという。
本書にGoogle社員チャード・メンの記念写真のリンクがあったので紹介したいと思う。
チャード・メン(グーグラー)と著名人たち
http://picasaweb.google.com/chademeng/
かなりの人数だが、ざっと見渡して日本人はおそらく2人だったと思う。
それよりこれを見てぼくがなにより嬉しかったのはこのブログですばらしいと絶賛した著者が2人いることだ。
1人目は2人いる日本人のうちの1人である竹中平蔵氏だ。
竹中氏はぼくが経済を初歩から学びたいと思って経済の本を探していたところ竹中氏の本に出会い、
少し前にハマったのだった。(詳しくはこちら)
竹中氏の説明はとてもわかりやすく経済を学びたい初心者にとってはこの上ない教師だと思う。
最近賑わっている空港のハブ化問題も元々は竹中氏が提唱していた政策なだけに、
郵政民営化は逆行して残念に思っていると思うが、ハブ化はぜひ実現していただきたいものである。
そして2人目はマルコム・グラッドウェル氏である。
これは最近のことなので、記憶に新しい。
特にこちらの書物はたいへん興味深く読ませていただいた。
ぼくが敬愛する人物とGoogleが好む人物がかなり近く、似たようなベクトルだったということがわかっただけでも個人的にはかなり嬉しい


(やっぱり買ってよかった
 )
)3.社員が社長に「Googleに慣れた?」と聞く、どこまでもフラットな組織
日経AssocieにGoogle日本法人社長、辻野晃一郎氏のインタビュー記事があったのだが、おもしろいエピソードがあった。
辻野氏は入社したばかりのころ、エレベーターに乗り合わせたエンジニアにこう聞かれたという。
「新しい仕事には慣れましたか?」と。
辻野氏はこれに対し、
「ああ、結構大変だよ」で済む組織ならその方が物事が速く進むのでいい、と記事で言っている。
このエピソードは普通の会社で考えたらありえないやりとりだろうが、まさにGoogleならではだろう。
Googleは肩書きこそあれど、周りの企業から見れば異常なくらいフラットな組織だ。
元々創業者2人が「何かをしろ」と指示されるのが嫌なタイプだということもあるのだろうが、組織形態もとことんイノベーションとWeb2.0的なVelocityを追求しており、社員個人が持つ可能性をただの1mmもつぶさないための組織を模索した究極の形なのだと思う。
『社員一人一人が主役です』と語る企業はたくさんあるが、Googleこそ真に社員(グーグラー)一人一人が主役として活躍している本物の組織だろう。
4.Chrome OSはエリック・シュミットに思いとどまるよう説得されていた!?
日経ビジネス冒頭のラリー・ペイジの記事によると、OS参入は何年も前から考えていたようだ。
しかしどうやらエリック・シュミットに思いとどまるようしばらく説得されていたとある。
これからIT業界はクラウドコンピューティング(以下クラウド)に大きく舵を切っていくことを考えると、Googleが所有するストレージ規模と技術力を考えればブラウザに参入したのは至って当然のことのように感じる。
だがさすがにOSへの参入はソフトウェアの中でも最上級に参入障壁が高い。
これまで幾度となくマイクロソフトに挑んでは敗れていった企業が山ほどあることからもそれは明白だ。
しかしそれは徐々に過去の話になりつつあるとぼくは感じている。
これから約5年~10年後にはIT業界の売上の30%をクラウドの売上が占めるという試算もあるように、クラウドが大きく絡んでくるとOSのシェアもわからなくなってくる。
まずOSのシェアでカギを握るのが企業の導入だろう。
これまではWindowsを使用することをベースとした複雑に構築されたシステムがあり、OSを変えるという発想すらあまりなかったが、クラウドになってデータの多くがあちら側(クラウド側)に移行すれば、OSをWindowsにこだわる必要がこれまでと比べると断然低くなってくる。
むしろ自社で導入するクラウドに適したOSやブラウザの方が重宝される可能性の方が高まってくると見るのが当然といえば当然だ。
あとは経営者とシステム部門の頭の固さ次第というところだろうか。
先ほどのGoogleが2位という話のところでも書いたのだが、ブラウザとOSとクラウドの移行の話も欧米などでは複数のOSをまたいで縦横無尽に使い分け、データのほとんどをあちら側(クラウド側)に置いて事業を展開する中、日本の企業はいまだWindows一本で自社サーバという企業がまだまだ多くを占めるといった光景もちらりと見え隠れするような気もして心配だ

ご存知の方は多いと思うが、クラウドのランニングコストは圧倒的に安い。
だがその事実をはっきりと自覚し、多くの日本の企業が実際に実務で使用するようになるまで何年かかるのだろう。
そこは未知数だ。
しかしクラウドでOSが変わる!と言いつつも、もちろんマイクロソフトだって最後の砦であるOSのシェアまで奪われるのは是が非でも阻止してくるのは目に見えている。
先日発売されたクラウドを想定して作られたWindows7も現時点ではかなり好調な出だしをしているし、OSだけでなくクラウドの核となるデータセンターにも積極的に投資していることからも、今後Chrome OSがどう出てくるのかはIT業界のみならず世界中が注目に値するだろう。
OSシェアの統計情報をWebで探ってみると(「Windows シェア」で検索された上位10位の中から)
記事1 http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/foreign/2009/01/05/14620.html
記事2 http://japan.cnet.com/blog/trans/2009/08/05/entry_27024157/
たいていの記事は「Windowsは今後シェアを落としていく」という見方が多いことが分かる。
Macの躍進などもあるだろうが、やはり世界規模でIT、特にPCに関するリテラシーが向上してきたことが大きいことと、さらに価値観が多様化・複雑化している現代においてはOSやブラウザまでもを個人や企業が選んで使用していく時代が来てもなんら不思議はないと思うのだ。
さらにそこにクラウドというレバレッジが効いて、OSやブラウザのシェアがかつてない変化を見せていくという構図も十分に考えられる。
来年にも発表されるというChrome OSだが、例えば2~3年後くらいに社内のOSをすべてChrome OSに切り替えた先進的な企業を見つけたとしたら、その企業は完全にクラウドに移行している可能性が極めて高く、イノベーションやテクノロジーを好むITベンチャー企業などにその姿が早々に見られるかもしれない。
そしておそらくその企業は、社員が起動に数秒しかかからない無料のChrome OSを搭載したネットブックorノートパソコンを常に持ち歩き、プリインストールされているGoogle Chromeで文書作成にGoogle Docsを使用し、Gmailで顧客からのメールをチェックしながら、Web上のGoogleカレンダーで社員の動きを共有するというGoogleに囲まれたインフラを基にビジネスを展開しているかもしれないのだ。
Google公式チャンネル by Youtube
http://www.youtube.com/user/Google?gl=JP&hl=ja



