オルガニスト、ダニエル・コルゼンパによるバッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻(WTC1)全曲。チェンバロ、クラヴィコード、オルガンという3種の「クラヴィーア」を弾き分けることによって作品の本質に迫っている。1982~83年録音。本記事ではCD1の第1~12番までを取り上げる。
このアルバムの大きな特色は、曲によって楽器を弾き分けている点にある。今までそのようなコンセプトによる録音がなかったため、リリース当時は注目されたようだ―現在ではロバート・レヴィン盤や武久源造盤がある―。10年後の1994年には第2巻のレコーディングがなされ、時代考証に沿ってジルバーマンのチェンバロやフォルテピアノも加わった演奏となったが、録音状態の不調のためか―プレリュードの冒頭の音が欠けているらしい―、第1巻とセットになった4枚組CDが海外盤のみでリリースされている (入手困難らしく、中古でも高値になっている) 。
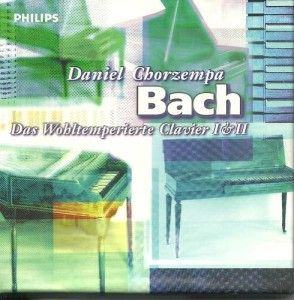
当盤CD1での楽器選択は以下の通り―。
平均律クラヴィーア曲集第1巻
第01番 ハ長調 (クラヴィコード) プレリュード、4声のフーガ
第02番 ハ短調 (チェンバロ) プレリュード、3声のフーガ
第03番 嬰ハ長調 (クラヴィコード) プレリュード、3声のフーガ
第04番 嬰ハ短調 (オルガン) プレリュード、5声のフーガ
第05番 二長調 (チェンバロ) プレリュード、4声のフーガ
第06番 ニ短調 (クラヴィコード) プレリュード、3声のフーガ
第07番 変ホ長調 (チェンバロ) プレリュード、3声のフーガ
第08番 変ホ短調 (クラヴィコード) プレリュード、嬰ニ短調 3声のフーガ
第09番 ホ長調 (チェンバロ) プレリュード、3声のフーガ
第10番 ホ短調 (クラヴィコード) プレリュード、2声のフーガ
第11番 へ長調 (チェンバロ) プレリュード、3声のフーガ
第12番 ヘ短調 (オルガン) プレリュード、4声のフーガ
渡邊學而氏によるライナーノーツにも少し説明されてはいたが、コルゼンパがどのような意図でこのナンバーをその楽器で演奏したのか、想像しながら聴くことも可能だ。おそらく、平均律を弾き込んでいる方や、作品を隅々に渡って熟知されている方、各楽器の特性を御存じの方なら、奏者の意図を把握することができるのではないだろうか―そこまではいかなくとも、WTC1作曲当時のバッハが想定したと思われる3種類の「クラヴィーア」が代わる代わる登場し、彼独特の精緻な音楽が紡がれてゆくのをひたすら楽しむのもまた良しである。
僕はとりわけオルガン演奏のナンバーに心惹かれた。全24曲中5曲しか用いられていないが、その5曲が全て短調で声部の多い楽曲という特徴がある―オルガン特有の持続する性質がピッタリのナンバーが選ばれたのだろう。「オルガニスト」コルゼンパの本領発揮といったところか。使用されているオルガンは1732年製の小型室内オルガンで、製作者不詳となっている(マティアス・シュルツェ作?)。ポジティフ・オルガンに近い音色で、親近感が持てるようなサウンドに感じられた。大音響が降り注ぐ大聖堂のパイプオルガンも確かに素晴らしいであろうが、教会だけではなく家庭でも弾けるという、バッハがこの曲集に込めたであろうコンセプトに合ったセレクトである。
おそらくはこんな感じのオルガンだったのではないだろうか―。
音色は当盤のオルガンと似ているように感じられた。
全24曲中10曲―と最も登場頻度が高いクラヴィコードでの演奏が聴けるのも当アルバムの目玉の1つ(チェンバロは9曲)。ライナーノーツによれば、バッハはこの曲集をクラヴィコードの音域(通常4オクターヴ)の範囲に収まる仕方で作曲しているとのこと。大変興味深い。多くの人々に弾いてもらうべく「教育用」の側面も現れているほか、バッハ自身がクラヴィコードを気に入っていたのではないだろうか―弦楽器のようにヴィブラートが掛け「魂を込められる」楽器だったからだろうか。コルゼンパが演奏に選んだチェンバロはカール・コンラート・フライシャーによる1716年製作、4オクターヴ49鍵の一段鍵盤の小型チェンバロ。そしてクラヴィコードの方は、ヒエロニムス・アルプレヒト・ハスによる1742年製作、5オクターヴ61鍵の大型クラヴィコードとなっている―楽器のトータルバランスを考慮した結果であろうか―。いくら大型とはいえクラヴィコードには変わりないのだから、出てくる音は絹のような質感と弦楽器を思わせる音感、小音量の繊細なサウンドである―他のクラヴィコードよりはスケール感があるのかもしれないが。分散和音がナチュラルに響き、100%の蕎麦を口にしているような感覚。弦の干渉音も聞こえ、全体としてはボソボソとした音質―録音の質や聞く際の音量も関係していることだろう。小音量の楽器による演奏はオーディオのヴォリュームを絞って聞くのが適切である―。モダン・ピアノの磨き上げられた響きとは大違いだが、現代においては「非日常」を体験するいい機会かもしれない(かつてそれが「日常」であった時代が確実に存在したわけだが)。クラヴィコード演奏の後にチェンバロが登場すると、少しばかり安心感を覚えたのも正直なところ。鍵盤楽器の進化の過程を目の当たりにするようだった。
イタリア、イギリス、フランスのチェンバロ(ハープシコード、クラヴサン)。
そしてクラヴィコード。当盤での楽器は全てドイツ製である。
バッハ/平均律第2巻に比べ、この第1巻はポピュラーで親しみやすく思える。第2巻の20年前に作曲された第1巻の特に前奏曲には多くの初稿が存在し、第1巻成立の2年前に「息子の教育用」として書かれた「ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア曲集」に含まれていたものを採用したそうである。どうりで優しい(易しい)メロディが際立っているわけだ。そしてポピュラリティの最大の理由は最初のナンバー「第1番ハ長調BWV846」にあるに違いない。そのプレリュードはバッハ作品の中でもとりわけ有名で、おそらく誰もが耳にしていることだろう。さり気ないアルペジオで始まるその音楽はミニマル・ミュージックの先祖にも聞こえるし、聴いているうちに心が整っていく感じすらする。当初、器楽曲におけるプレリュードには、指慣らしや調律のテストの意味合いがあったとされている。当盤ではクラヴィコードで演奏されるが、ややたどたどしくもある。驚いたのは続くフーガであり、その主題の音数が14で「BACH」(2+1+3+8)と同じ数。そしてこのテーマが24回繰り返される―全24曲のこの曲集の冒頭にふさわしい。そして主題が25回目に現れる時、「天に達する」が如く楽器の最高音に達して終わるというのだ。武久源造氏の動画を(改めて)観て知ったことであった。
武久氏は平均律を(オリジナルの意味に近い)「適正律」と言い直す。ジルバーマンのフォルテピアノによる。ここでは第1番、2番、5番が解説とともに演奏―。
チェンバロを弾いたシュタイアー盤によるプレリュード。ミュートをかけた
演奏解釈はクラヴィコードを意識したのかも―。
初稿版のプレリュードBWV846a。クラヴィコードによる演奏で―。
即興で生まれたというグノー/アヴェ・マリア。当初は「バッハの第1前奏曲による瞑想曲」だったのが、歌詞を載せて完成。マリア・カラスの歌唱で―。
バッハ/無伴奏チェロ組曲第1番BWV1007~プレリュード。アルペジオ進行がBWV846とそっくりである。ここではあえてハープシコードでの演奏で。
「第2番ハ短調BWV847」でもアルペジオが活躍する。トッカータのような劇性を伴うため、当盤のようにチェンバロでの演奏は効果的かもしれない(モダン・ピアノではリヒテルが猛烈なスピードで弾いていたのを思い出すが、彼の演奏で全曲を聴きとおしたことは一度もない)。音楽史史上初と思われる「嬰ハ長調」を用いた第3番BWV848は、シャープの多い調性が音楽にこれまでにないキラキラ感を与える。コルゼンパは再びクラヴィコードで演奏、きめ細かい音の連なりをさらりと弾きこなしている。スペースを置かずフーガに突入するなど、前のめり的な情熱も感じる。
鈴木優人氏によるBWV847の解説。台所で皿洗いしている姿も観れる。
チェンバロを演奏したレオンハルト盤によるBWV848。前奏曲ではミュート効果を用いる。
「第4番嬰ハ短調BWV849」ではオルガンが登場、一気に引き込まれる。元々オルガン曲だったのでは、と思うほど充実し崇高さに満ちたプレリュード、第1巻では2曲しか存在しない5声のフーガの荘厳さにはただただ聴き入るばかりだ。聞く誰もが「宗教的瞑想さ」を感じずにはいられまい―バッハが神学性を込めようとしたかどうか。現にテーマにはBACH音型と十字架モティーフが認められるという。最後の音が引き伸ばされるのもオルガンならではだろう。
当盤音源より。オルガンの響きもいい―。
ショパンが弾いたかもしれない1843年製プレイエル・アップライトピアノによる演奏。嬰ハ短調の曲はショパンにも多い。彼もバッハ平均律を常に弾いたことだろう。
「第5番ニ長調BWV850」を1842年製プレイエルで―。
BWV850のフーガと共通性のあるパルティータ第4番ニ長調BWV828~序曲。
ルセのチェンバロ演奏で。どちらもフランス序曲風の付点リズムを伴う。
仄かな哀愁が漂う「第6番ニ短調BWV851」。プレリュードでの前打音はクラヴィコードだと自然に聞こえる。第1番ハ長調と第2番ハ短調のプレリュードがそうであったように、第5番ニ長調と第6番ニ短調のプレリュードとは対応関係にあるようだ。チェンバロによる穏やかでやわらかい曲調の「第7番変ホ長調BWV852」、そのプレリュード冒頭は、同じ調性のBWV552と全く同じように聞こえる。そして印象に残る「第8番変ホ短調BWV853」へ。アルペジオとトリルが目立つ陰惨な雰囲気のプレリュード。クラヴィコードだと少し明るくなるかと思いきや、そうではなかった。「鍵盤音楽における最初の夜想曲であり、星空のような透明感がある」と評されるだけある。続く嬰ニ短調のフーガではさらに音楽の森の深奥へと向かう。この深い瞑想と諦観を孕む音楽はハンマークラヴィーアでの演奏が忘れられない。
BWV852の前奏曲をロバート・レヴィン盤で。彼はオルガンで弾いている。
前奏曲とフーガ変ホ長調BWV552~前奏曲。マリー=クレール・アランの演奏で。
BWV853を1825年製(とされる)ブッフホルツのピアノで―。
「第9番ホ長調BWV854」の甘い情緒(アフェクト)、パストラーレな雰囲気。これもまた第1巻人気の理由の1曲かもしれない。前奏曲もフーガも短いながら親しみやすい。チェンバロの響きも美しい。これと対を成すような「第10番ホ短調BWV855」は問いを投げかけるようなプレリュードが後半からのパッショナートな展開に驚く。半音階が炸裂するフーガがなかなかに大胆な音楽に聞こえるのはクラヴィコードのおかげだろうか。
BWV854を1728年製作Christian Zellによるチェンバロで―。
こちらはWTC2~第9番ホ長調BWV878。コルゼンパはここでジルバーマンの
フォルテピアノ(1776年製作)を用いて演奏している。
シロティ編曲による前奏曲BWV855a。編曲に際し、ホ短調→ロ短調に移調。
BWV855の初稿(W.F.バッハのための音楽帳に含まれている)に基づく。
「第11番ヘ長調BWV856」のプレリュードはパスピエを思わせる快活な音楽。フーガにもその雰囲気は引き継がれる。このはじけるような明るさにはチェンバロが相応しいだろう。CD1最後の「第12番ヘ短調BWV857」は第4番嬰ハ短調や第8番変ホ短調のような暗さ、厳粛さよりも感情により訴えてくるような切ない音楽。コルゼンパはここでオルガンを演奏しているが、まるでコラール前奏曲のように響き、フーガも神聖な思いにとらわれる。「ヘ短調」は「受難」と結び付けられやすいが、神学的に捉えれば無論「イエスの受難」ということになろう。
4種類のオルガンを用いてWTC全2巻を録音しているデザンクロ盤より。
To be continued。。。
