この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
三枝憲正邸は、
閑静な住宅街の一角を占めている。
小高い丘が塀の向こうに覗く。
政財界に隠れもない名士は、
その息子夫婦と愛孫と共にここにある。
長く邸宅を囲む塀が
んぜか板塀であるのは、
憲正が洋館住まいをしながらも
日本邸宅に強い愛着をもっているからだ。
警護の都合、執務の都合により
洋館で過ごす時間が長いが、
趣味の謡やら茶やらと
点在する庵には趣向が凝らされている。
青畳の香は、
ことに憲正の愛するものだ。
勝手口の潜り戸を抜ける小さな影は
この気温であるのに
憲正贔屓の畳屋の上っ張りを着込み、
迎える女衆に物腰柔らかく
腰を屈めている。
ほんの数分で、
小柄な男は女衆の案内で
庵の一つに向かって
丁寧に庭石を踏んでいく。
身の軽さに似合わぬ白髪が作業帽から短くはみ出ている。
まだ紫陽花は美しいが、
その色の変化を楽しめるのも
もう残りわずか。
今は百日紅が咲き零れて盛りへと向かっている。
「では、
こちらの畳を見てくださいな。
終わりましたら台所に声をかけてくださいね。」
女衆はにっこり微笑んで踵を返し、
初老の職人は腰を屈めてそれを見送る。
やおら庵を見上げると、
沓脱にきちっと靴を脱ぎ、
縁に上がると
その板戸に手をかけスルスルと開いた。
年季の入ったそれはやや灰色がかっていたが、
現れた障子は白く
その桟は真新しい木地が涼やかだ。
その障子をいっぱいに開き、
職人は丁寧に
畳面を、へりを、見定めていく。
一渡り見終えると、
今度は障子をぴたりと閉める。
障子を通した日の差し込む色を見るという流れのようだ。
それを待ち兼ねたというように
カタン
と
小さな音が響いた。
職人はくるりと振り向き、
床の間を前に
びしっと膝をつく。
ただ一幅の掛け軸のみをあしらった床の間が
微かに震えた。
ぱたん………。
竹林と虎を描いた掛け軸が
跳ね上がる。
床の間であった段に
躙口ほどの高さの穴がぽっかりと空いた。
斉木政五郎が
すっと両の手を前についた。
ぬっと頭が突き込まれたかと思うと
巨体が身を屈めて
その部屋に現れる。
「斉木政五郎、
まかりこしました。」
「ああ
五分で頼む。」
「鷲羽の客分に面白い奴がいましてな。
お嬢様は、
惹かれておいでかもしれません。」
「ほう。
高遠豪といったな。
なかなかだ。
わしも目を引かれた。
だが、
かもしれぬとは、
どういう意味だ。
お前らしくもない。」
「お嬢様はあいつの願いを受けて
あっしらの高校でやる演し物に加わってくださるそうです。
その承知なさるお声がね、
引っ掛かりました。
情があった。
聴講生には総帥もおいでだが、
お嬢様の情は高遠に向いていました。
まあ海のものとも山のものとも
つきませんがね。」
今ごろは、
もう落ち合っているだろう。
綾子の世間知らずのお嬢様ぶりに
西原などは目を回しているかもしれない。
そう思うと
政五郎の顔に穏やかな笑みが浮かぶ。
「見事なお嬢様でございますな。」
それは世辞ではなかった。
鷲羽の衆は、
一同、
三枝の姫君に心服している。
「興津の姫は
鷲羽の衆となった、
そうあるのだがな。
鷲羽海斗のつれないことよ。」
三枝憲正が吐息をつく。
「綾子様がその姫とお考えですか?」
「だから、
嫁にと申し出た。
断られたがな。」
「口伝だけのお話で?」
「役目もある。
我ら興津は枝を張るのよ。
そう誓って名を三枝と宣したという。
世に力をもつこと、
役目には欠かせない。
鷲羽海斗、
力ある男だ。
誰もが欲しい。
もちろんわしも欲しい。」
「たしかに。
ところで、
枝を張るのは何のためでしたかな?」
斉木政五郎は、
そこでことばを止め
三枝を見つめた。
「鷲の止まり木。
この三枝、
信義は守る。
守ってきたつもりだがな。」
「鷲羽は興津と共にある。
こちらも信義は守ってきました。」
今度は三枝が問うた。
「まわりくどいな。
何を言いに来た。」
「高遠豪、
日の長の器です。
………どう思われます?」
三枝憲正がニヤリと笑った。
「綾子はわしの自由にはならん。
それでこそ興津の姫だろう?
そしてな、
興津はな、
いやこの三枝は、
鷲羽と共にあるのであって、
綾子の婿と共にあるわけではない。
三枝憲正、
そこも分からぬほどに老いぼれてはおらんぞ。
だが、
鷲羽の男どもときたら
どいつもこいつも巫の虜だ。
綾子も苦労する。」
「じゃあ、
あっしも安心して
見届けさせていただきます。
綾子さまも
まだお若い。
若い者は苦労するものでございますよ。
三枝の枝、
頼りにしております。
どうかよろしゅうに。」
政五郎は頭を下げ、
憲正はふたたび巨体を縮め
狭苦しい穴をそろそろと降りていく。
政五郎は
端の障子からするりと抜けると、
手際よく板戸を閉め、
庭石を案内を受けた台所へと戻り始めた。
画像はお借りしました。
ありがとうございます。
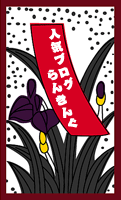
人気ブログランキング
